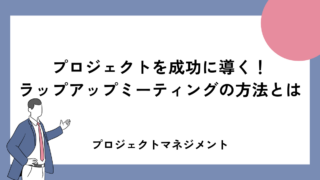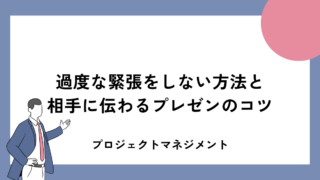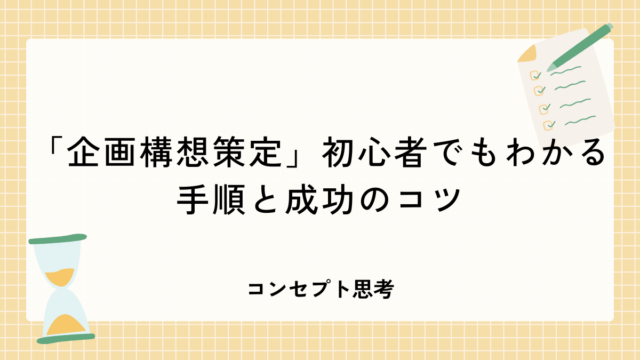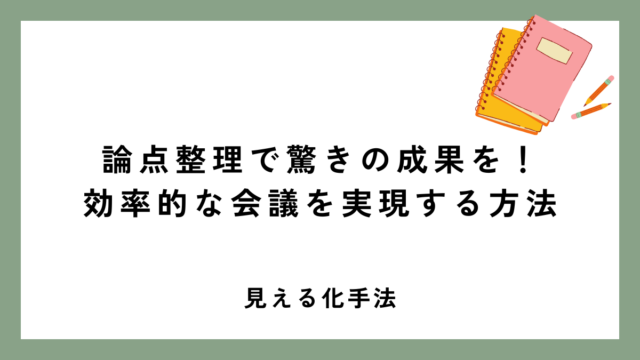プロジェクト成功を引き寄せる!スコープ設定を極める方法
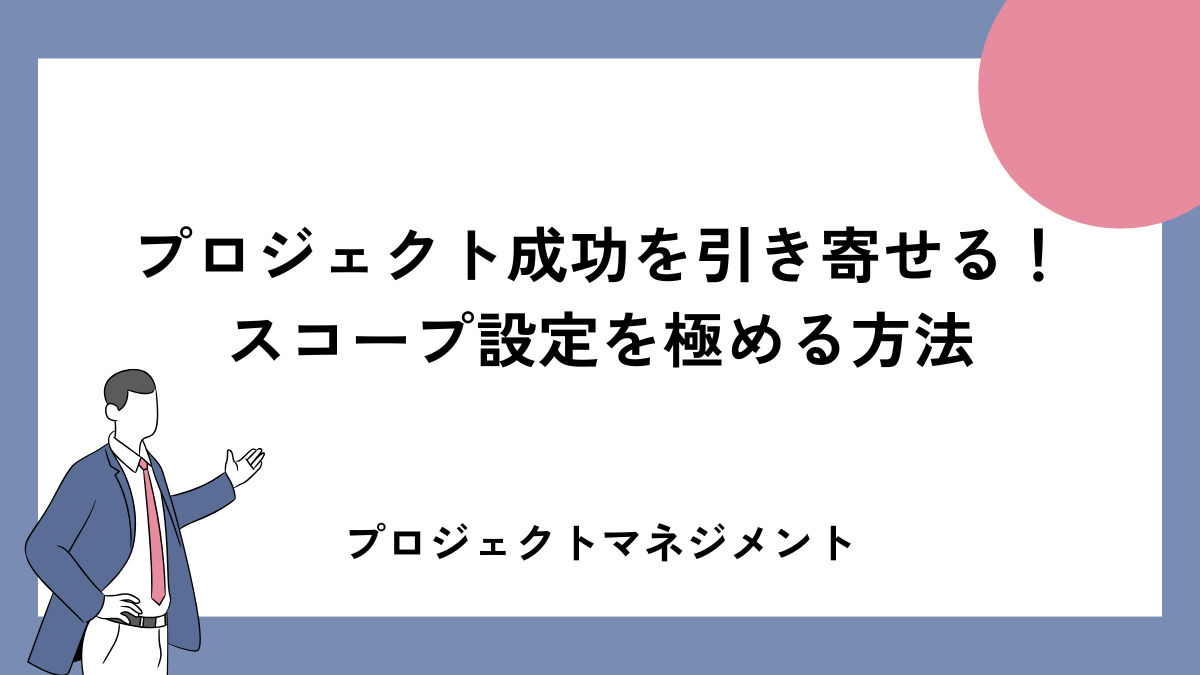
(2025/3/31 更新しました)
プロジェクトが始まれば、いろいろなことをやりたいですよね。
人間の心理として当然です。
メンバーの要望も かなえてあげたいですよね。
一方で、全てに対応していたら コスト・時間もかかります。
プロジェクトも迷走しますよね。
今回は、プロジェクトの構想段階で重要な「スコープを決める方法とスコープを維持するためのコツ」について紹介します。
私は、25年以上のプロジェクトリーダーとしての実績があります。
その経験に基づいています。
プロジェクトスコープの基本概要
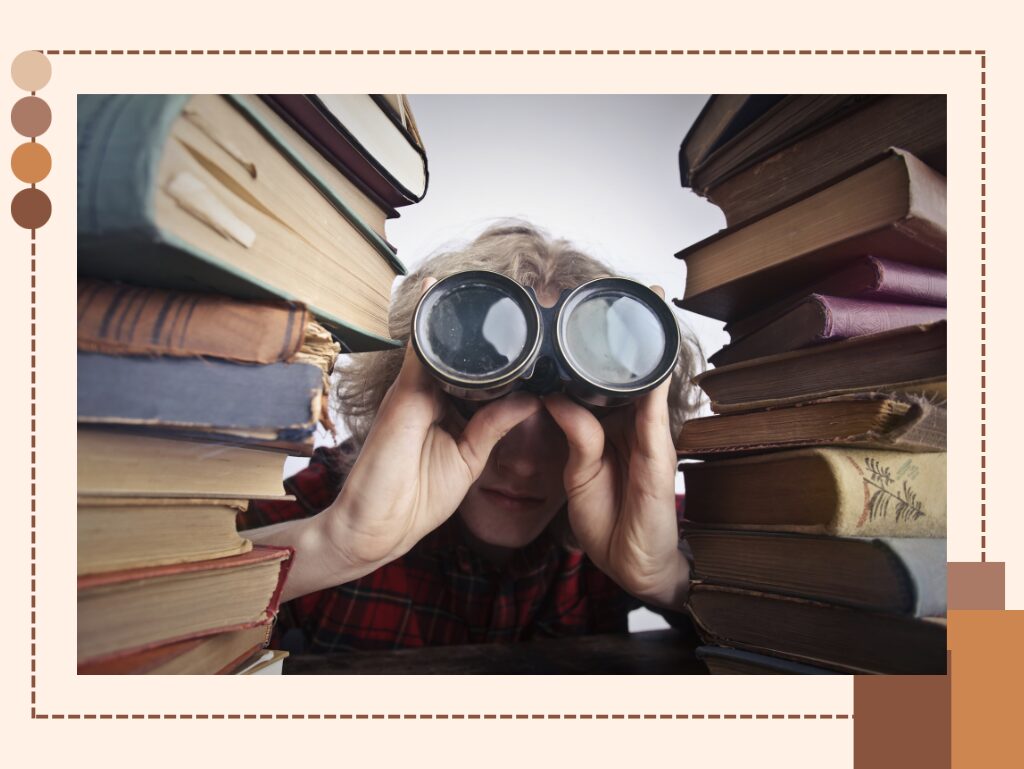
プロジェクトスコープとは:意味と重要性
プロジェクトスコープとは、プロジェクトで達成するべき目標や成果物、必要な作業の範囲を定義することを指します。
このスコープを明確に設定することで、プロジェクトメンバーやステークホルダーが共通の理解を持ち、効率的かつ効果的にプロジェクトを進めることが可能となります。
また、プロジェクトスコープは、「何をするか」「何をしないか」を具体的に示す点でも重要です。
これにより、不必要な作業やスケジュールの変更を防ぎ、リソースを効果的に活用できます。
スコープ定義の主な要素
プロジェクトスコープを定義する際には、いくつかの重要な要素が含まれます。
まず、プロジェクトの目標と最終成果物を明確にすることが求められます。
例えばシステム開発ならば、「どこまでの範囲」で「どういう機能」を持ったシステムにするのかになります。
また、関連部署との関係も明確にする必要があります。
例えば業務プロセス改革であれば、「どの業務」を「どう改革するか」協議をして行く必要があります。
チームビルディングにも関係してきますよね。
最終的には、スコープ記述書として文書化します。
通常は、プロジェクト構想書の中に含まれる文書です。
この文書は、プロジェクトの基本情報や前提条件・制約条件・成果物の受け入れ基準などを示し、ステークホルダー間での合意形成を支援します。
通常は、プロジェクト決裁という形になりますよね。
他にも、プロジェクトに含まれない作業や要件を明確にする「除外事項」の記載も必要です。
要は「やらないこと」を宣言することですね。
これらの要素を明確化することで、作業範囲の不明瞭さによる計画の混乱を防ぐことができます。
スコープ設定のメリットとリスク回避
プロジェクトスコープを適切に設定することには、多くのメリットがあります。
1つ目は、プロジェクトチームが効率的にリソースを活用できることです。
限られたリソーセスを適切に分配し、優先順位を持って取り組むことで、ムダな作業やコストの超過を回避できます。
2つ目は、プロジェクトメンバー・ステークホルダーとの合意が確保でき、プロジェクト進行中の不必要な変更要求を減らすことです。
一方で、スコープ設定が不十分である場合、計画の混乱が発生する可能性があります。
これは、作業範囲が曖昧で計画以上の変更や追加作業が発生し、予算や期間を大きく超過するリスクを招きます。
スコープを正確に定義し管理することで、プロジェクトの成功確率を大幅に向上させることができます。
スコープ設定の具体的ステップ
要求事項の収集と整理
プロジェクトスコープに限らず、要求事項の収集と整理は欠かせない重要なステップです。
この作業では、プロジェクトに関わる利害関係者(ステークホルダー)から要件や期待を漏れなく引き出す必要があります。
ヒアリングやインタビュー、アンケートなどの手法を活用することで、多角的な観点から要求を収集していきます。
通常は、課題リストなどで管理することになりますよね。
そして、要求事項を整理し優先順位をつけることで、プロジェクトを効率的に進める基盤が整います。
このプロセスで曖昧な点を早期に解消することが、後々のトラブルを防ぐ助けとなります。
わからないことは再度ヒアリングをするなどして、正確に把握することです。
明確なプロジェクト目標の設定
プロジェクトの成功には、明確なプロジェクト目標を設定することが重要なステップとなります。
この目標は、プロジェクトチームが一貫した方向性で進めるための指針となるだけでなく、実現可能なレベルで設定することが求められます。
具体的には、優先順位をつけた要求事項についてプロジェクトの目的を踏まえ「どこまでやるか」などを検討することになります。
そして、具体的な目標にしていきます。
例えば業務の効率化の場合、「何をやることによって30%効率化する」という目標になります。
適切な目標設定は、プロジェクトの羅針盤となります。
成果物の明確化と要件の洗い出し
次に、プロジェクトの成果物を具体的に定義し、そのための要件を洗い出す必要があります。
最終成果物は「プロジェクトで絶対に達成しなければならないもの」のことであり、明確にすることによってスコープの選定基準ができあがります。
要件洗い出しの手法としては、プロジェクトメンバーによるブレインストーミングやワークショップが効果的です。
ステークホルダーやチームメンバーと協力しながら、何が必要で、どこまでがプロジェクトの範囲内なのかを整理していきましょう。
選定基準は、プロジェクトの目標と最終成果物です。
これらの情報を詳細にまとめることで、計画のズレを防止し、プロジェクト成功への土台を築くことができます。
実作業範囲(作業スコープ)の可視化
作業スコープは、プロジェクトの具体的なタスクやアクションの範囲を指します。
この範囲を可視化することにより、メンバーが「何を行うべきか」「何を行わないべきか」を正確に理解することができます。
作業スコープを可視化する手法として、通常のプロジェクトマネジメントではWBS(作業分解構成図)を紹介しますよね。
WBSって、建築物とか相当大きいプロジェクトで使うツールです。
普通のプロジェクトであれば、Excelでの管理で十分です。
大日程を書いて、フェーズごとに実施するタスクを書くぐらいでマネジメントは可能です。
但し、次フェーズは、具体的に作業を詳細化すると良いですね。
私の事例でも、基本Excelで作成しています。
これにより、プロジェクトの全体像が把握しやすくなり、プロジェクトマネジメントの基盤ができます。
スコープ記述書の作成方法
スコープ設定の最終ステップとして、スコープ記述書を作成します。
この文書は、プロジェクトの範囲を明示し、関係者全員が同じ理解を共有するための重要なツールとなります。
スコープ記述書に含めるべき要素は、以下の通りです。
テンプレートもネット上にありますよね。
- プロジェクトの背景・目的
- プロジェクトの目標
- 成果物の内容
- 受入れ基準
- 制約条件
- 前提事項
この文書を詳細に作成することで、スコープ変更の際も迅速な対応が可能となり、プロジェクトの信頼性を高めることができます。
ステークホルダーとの合意形成の重要性
プロジェクトスコープを作成する際、ステークホルダーとの合意形成は極めて重要な要素です。
この合意形成が不十分な場合、後になってスコープの変更が頻発したり、プロジェクト全体に混乱を引き起こす可能性があります。
ステークホルダーと定期的にコミュニケーションを取り、意見を十分に聴取しながら、全員が納得できるスコープを確定することが成功の鍵です。
プロジェクト構想の段階では、構想を始める時・中間での経過状況・最終決裁の3回は、トップマネジメントとのコミュニケーションの場がありますよね。
有効に活用することです。
また、合意形成プロセスそのものを文書化しておくことで、変更管理プロセスをスムーズに運用できるようになります。
正確な合意の記録は、プロジェクト進行時のトラブル軽減にも寄与します。
スコープを維持・管理するためのコツ
スコープ変更管理プロセスの導入
プロジェクトを進行していく中で、スコープの変更・追加の要求は避けられないものです。
そのため、スコープ変更管理プロセスを事前に設定しておくことが 成功の鍵となります。
プロセスの構成要素は、以下です。
- 変更リクエストを文書化(リスト化)
- メンバーでの影響の検討
- 決断
このプロセスを導入することで、変更がどのようにプロジェクト全体に影響を及ぼすかを評価し、関係者との合意を得たうえで、適切な調整を行うことができます。
プロジェクトリーダーの腕の見せどころです。
また、大きな変更の場合は、ステークホルダーに説明・最終承認を得る流れを作っておくことも必要ですね。
このようにスコープをマネジメントすることで、予算オーバーや納期遅延を防ぎ、プロジェクトの成功率を高めることができます。
スコープの進捗管理と調整方法
プロジェクトスコープを管理するためには、定期的な進捗の確認とスコープの現状を可視化することが不可欠です。
タスクの進捗を測定し計画から逸脱していないか確認することで、早期に対応することが可能になります。
また、関係者全員との定例ミーティングを設け、現在の状況を共有するのも効果的です。
状況に応じて必要な調整を迅速に行うことで、プロジェクト全体がスムーズに進行します。
私の事例では、週に1回 定例ミーティングを行うことが多いです。
コミュニケーションの重要性とその手法
スコープを維持・管理するうえで、コミュニケーションは最重要課題の一つです。
プロジェクトスコープを関係者全員が正しく理解し、目標に向けて共通認識を持つことが求められます。
適切なコミュニケーションがなされない場合、スコープが曖昧になり、プロジェクトが思わぬ方向に進んでしまう可能性があります。
効果的な手法として、情報共有のための定期的なミーティングや進捗報告書の活用があります。
また、ステークホルダーの意見を引き出すために定期的なミーティングを設定するのも有効です。
私に事例では、週に1回のメンバー定例ミーティング、各フェーズごとのトップマネジメント報告を実施することが多いです。
こうした透明性のある情報交換を実現することで、スコープ管理が確実に行われます。
また、メンバーが意見を言いやすい環境を作ることも重要です。
全員の納得のもと進行することで、質の高いプロジェクト成果物が可能になります。
まとめ
今回は、プロジェクトの構想段階で重要な「スコープを決める方法とスコープを維持するためのコツ」について紹介しました。
私自身の経験からも、スコープを正確に定義することは、プロジェクト成功の鍵となります。
そして、実際のプロジェクトでは「変更管理」も重要なのです。
構想段階でスコープを決めて、プロジェクトを成功させましょう。
さて、今回は「プロジェクトスコープ」について紹介しましたが、「プロジェクトのコンセプト」は もっと重要ですよね。
以下の記事では、「プロジェクトのコンセプト」について紹介していますので、こちらの記事も併せて読んでみてください。
投稿記事:プロジェクトの羅針盤!コアコンセプトの作成・決定方法
投稿記事:成功するコアコンセプトに導く!突破する価値観を築くコツ