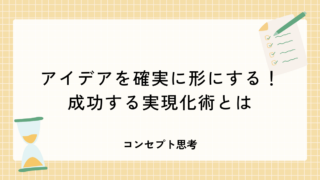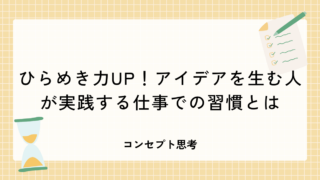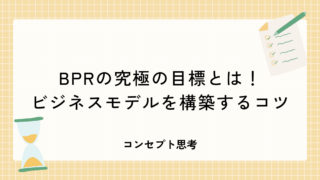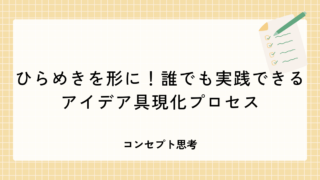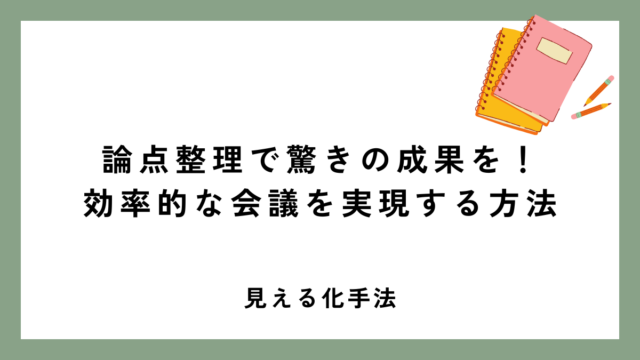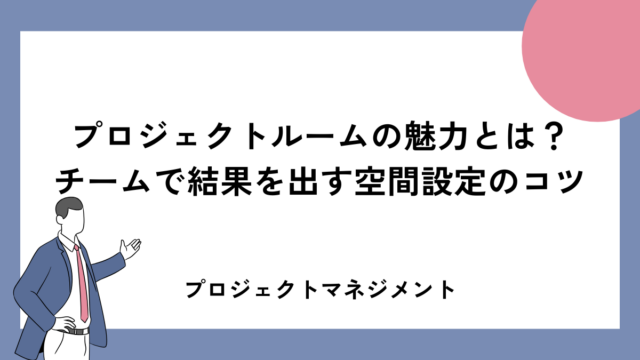チームの結束力を高める!魅力的なビジョンの作り方
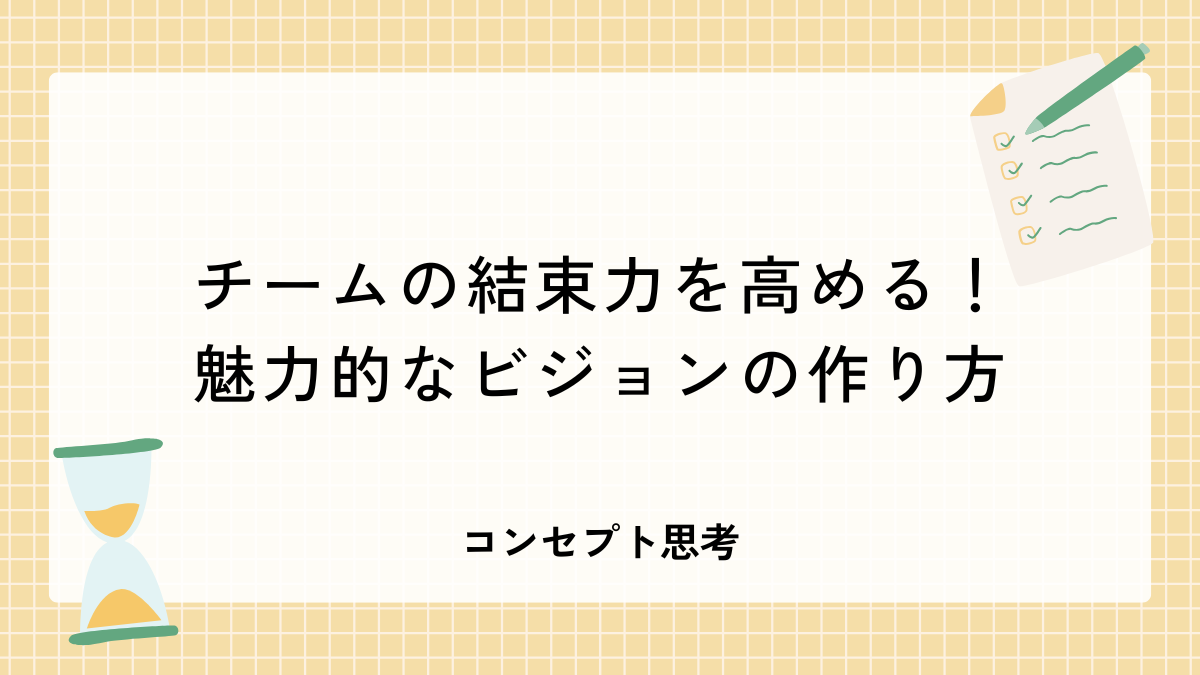
(2025/4/3 更新しました)
魅力的なビジョンには、人を動かす力がありますよね。
人を動かすビジョンを策定してみたいと思いませんか?
ビジョンは、全社だけのものではありません。
プロジェクトも、ビジョンが人を惹きつけます。
今回は「人を動かす魅力的なビジョンを策定する方法」を紹介します。
私自身が実際にプロジェクトで実践していた方法になります。
私は、大企業で25年以上のプロジェクトリーダーとしての実績があります。
その経験に基づいています。
ビジョンとは何か:基本を理解する

ビジョンの定義と役割
ビジョンとは、自社やチームが中長期的に目指すべき将来の方向性や理想像を明確化したものです。
単なる目標数値ではなく、自社やチームが達成したい理想的な状態を指し示します。
また、ビジョンは組織全体の共通認識を形成し、メンバーの行動基準を示す役割を担います。
優れたビジョンは、メンバーが共通の目的を認識し、目標に向けて一丸となるための強力な指針となります。
ビジョンとミッションの違いとは
ビジョンが未来の目標や理想像を示すのに対し、ミッションは組織の存在意義や果たすべき役割を定義します。
たとえば、ある開発チームが「常にイノベーターであり続ける」というビジョンを持っていたとします。
この場合、ミッションは「革新的な製品を提供し続けること」として定義されることがあげられます。
ビジョンとミッションは互いに補完し合う関係にあり、両者を明確に定義することで組織全体が効率的に動く基盤が整います。
なぜチームにビジョンが必要なのか
ビジョンがあることで、チームは共通の目標に向かって一致団結することができます。
特に変化が激しい現代において、目指すべき明確な方向性を示すビジョンは、メンバーが迷わず行動するための指針として機能します。
また、ビジョンを共有することにより、チームの結束力が高まり、メンバーの主体性とモチベーションを引き出すことが可能です。
成功するプロジェクトに共通するビジョンの特徴
成功するプロジェクトには、次のような共通するビジョンの特徴があります。
まず、ビジョンがそのチームにとってリアルであり、目指せば達成可能なものであることです。
抽象的で遠すぎる目標ではなく、日々の取り組みと連動した具体的なビジョンが求められます。
次に、多様なメンバーが共感できる内容であることも重要です。
これにより、チーム全体が一体となって行動する力が生まれます。
また、目標を達成したその先の価値が明確であり、「なぜこのビジョンを追求するのか」といった目的がメンバーに深く浸透していることも共通点に挙げられます。
魅力的なビジョンを作るためのプロセス
ビジョン策定手順
ここからは、私自身が実際にプロジェクトで実践していた方法を紹介します。
大きな流れは、以下になります。
- 事前準備:組織の現状を分析する
- キーワード挙げ、体系化する
- 5年・10年先の絵を描く
- 大きな括りで思いついたことを○○コンセプトと名付ける
- そのコンセプトを深掘りする
- コンセプトを5年・10年先の絵に織り込む
実際には、1〜5を往復しながら進めていきます。
そして、最終的に出来上がった「5年・10年先の絵」が ビジョンです。
以下に各ステップの概要を紹介します。
ビジョン策定の準備:組織の現状を分析する
魅力的なビジョンを策定するには、全体像を意識しつつ段階的に進めることが重要です。
まず大切なのは、全社ビジョンや方針を深く理解し、それをプロジェクトの設計に活かすことです。
次に、チームの現状を正確に把握することが不可欠です。
現状分析を行うことで、現在の課題や強み、チームを取り巻く環境を明らかにし、未来を見据えた方向性を具体化できます。
例えば、業務データや従業員の意見を収集し、成功している領域と改善が必要な点を整理することが重要です。
また、競合他社や市場動向の調査を行うことで、自分たちの強み弱みを確認することも必要です。
このプロセスを経ることで、チームの方向性がより明確になります。
キーワードを挙げ体系化する
次のステップは、外部環境や業界のトレンドを把握することです。
先ずは、未来を描く前に 関連しそうなキーワードを挙げていきます。
最近よく使われているキーワード、今後予想されるキーワードを抽出していきます。
現状の課題もキーワードにします。
先ずは自分が知っている世界で挙げていきます。
そこで、一旦俯瞰してみましょう。
- 自分の業界だけに絞られていないでしょうか?
- 偏っている・抜けている領域がないでしょうか?
- 課題は網羅しているでしょうか?
- もっと深掘りする必要があるものはないでしょうか?
不足を感じた全てにおいて、キーワードを探していきます。
書籍や雑誌など読みあさって、関連するキーワードを 更に肉付けします。
ビジョンの初期段階では、チーム全員が参加するブレーンストーミングを通して、アイデアを引き出す方法も有効です。
上記で実施したキーワードを叩き台として、さらに多角的な視点を取り入れていきます。
次に、収集したキーワードを 体系的に描いていきます。
グループ分けをしたり、矢印でつないだり、関係が見えるように描きます。
そうすると、おぼろげながら 将来の「ありたい姿」のイメージが浮かんでくると思います。
5年・10年先の絵を描く:コンセプトと具体的な絵の往復
先ずは、粗いレベルの絵を描きます。
キーワードの体系図から、思いついたイメージを 絵にしていきます。
例えば、ビジネスプロセスならば「こんな仕事のやり方をしている姿」を描きます。
言葉を連ねるのではなく、絵にすることが重要です。
それによって、不足している部分も見えてきます。
視覚効果を利用するのです。
キーワードの体系図を見ながら、思いついたことを 絵に追加・修正を加えていきます。
未来には、ありゆる未来・ありたい未来・あるべき未来など分類がありますよね。
私は、基本的には「ありたい未来」を描きます。
ここで必要なのは、抽象化と具体化を繰り返すことです。
キーワードの体系図を見ながら、コンセプトとして抽象化します。
そして、それを絵にすることにより具体化します。
コンセプトと具体的な「ありたい姿」を同時に創っていく作業となります。
それにより、独自の未来が描かれていきます。
ある程度できあがったら、チームで共有し 更に絵を練り上げていきます。
こうしたプロセスを通じて、チーム全体で共有できるビジョンができあがります。
コンセプトの抽出方法
ビジョンは、将来の「ありたい姿」です。
そして、ビジネスであれば 差別化も必要ですよね。
そこで、コンセプトを考える際には いろいろなビジネスツールを利用します。
私がよく利用するものを、今回3つ挙げます。
- SWOT分析(コアコンピタンス分析含む)
- 時系列分析
- ビジネスモデル手法(お客様との接点含む)
以下、順番に説明します
SWOT分析
定番の分析手法ですが、ビジネスの特徴を捉えるには 一番良い方法です。
あなたのビジネスのコア・コンピタンスを 考えることもできます。
但し、この分析手法で出てくるコンセプトは、かなり大括りのものです。
なので、私はビジョン策定の初期段階で利用することが多いです。
自社の強み・弱み、外部環境の機会・脅威をクロスさせて、大括りのコンセプトを導き出します。
この際、現状分析をした時点ではなく、5年・10年先からの視点が重要です。
そして、具体的な絵に織り込みましょう。
現状分析も大切ですが、それは戦略を考える際に行うことです。
時系列分析
「キーワードを集めて、体系化する」でも説明しましたが、挙げたキーワードを時系列に並べる
分析手法です。
全体のトレンドを把握するものです。
但し、時系列分析は 従来の延長線上になるリスクがあります。
あくまで傾向として捉え、「組織に当てはめたら こんなことができるかも」といった非連続のコンセプトを意識して考える必要があります。
根底にある流れを捉え、飛躍を考えます。
例えば、全然異なる業界のトレンドを あなたのビジネスに当てはめたらどうなるかを検討するのも有効です。
ビジネスモデル手法
私自身は、大括りのコンセプトを深掘りしていく際に 活用しています。
いろいろな手法が提案されていますよね。
こういうツールは、読んだら 一度は使ってみるべきです。
必ずフレームワーク紹介されていますよね。
例えば、ビジネスモデル・キャンパス。
自らの組織に当てはめて作成してみると、新たな視点も出てきます。
特に、差別化を検討する際に有効なので、おすすめします。
但し、フレームワークで 新しいコンセプトが生まれるものではありません。
視点に漏れがないか、検討していないことはないか、気づきを得るものだと思ってください。
フレームワークでアイデアが出るのならば、世の中のビジネスは成功だらけです。
まとめ
今回は「人を動かす魅力的なビジョンを策定する方法」を紹介しました。
実際に私自身がプロジェクトリーダーとして実践していた方法です。
プロジェクトは生き物です。
魅力があるビジョンには、必ず人が惹きつけられます。
魅力あるビジョンを作成して、プロジェクトを成功に導きましょう。
さて、今回の記事の中で「コンセプトの抽出方法」について紹介しました。
以下の記事では、さらに詳細に紹介していますので、こちらの記事も併せて読んでみてください。
参考投稿記事:抽象化と具体化を繰り返す!コンセプト思考とはアイデアを引き出す手法