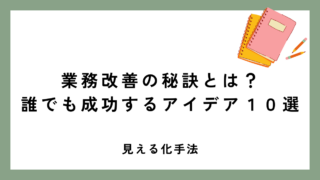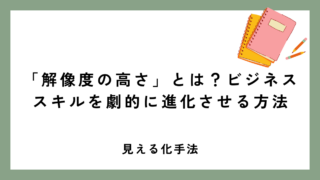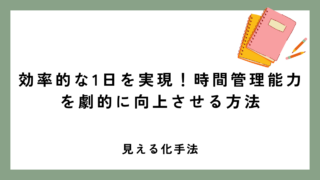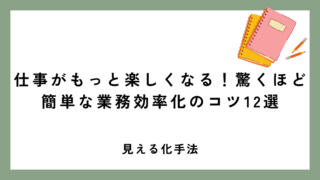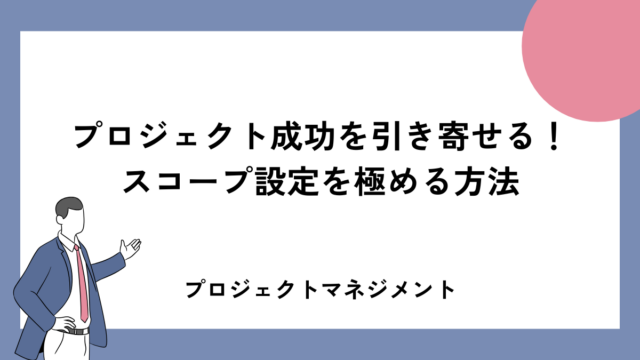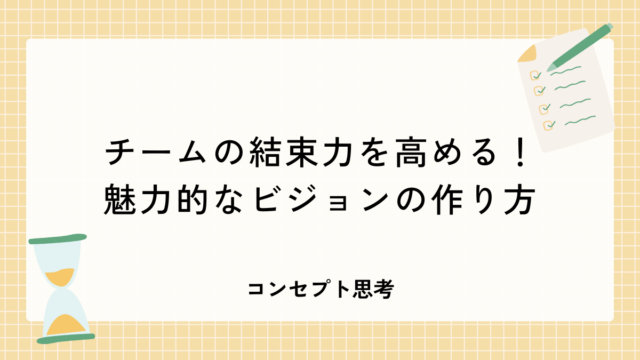論点整理で驚きの成果を!効率的な会議を実現する方法
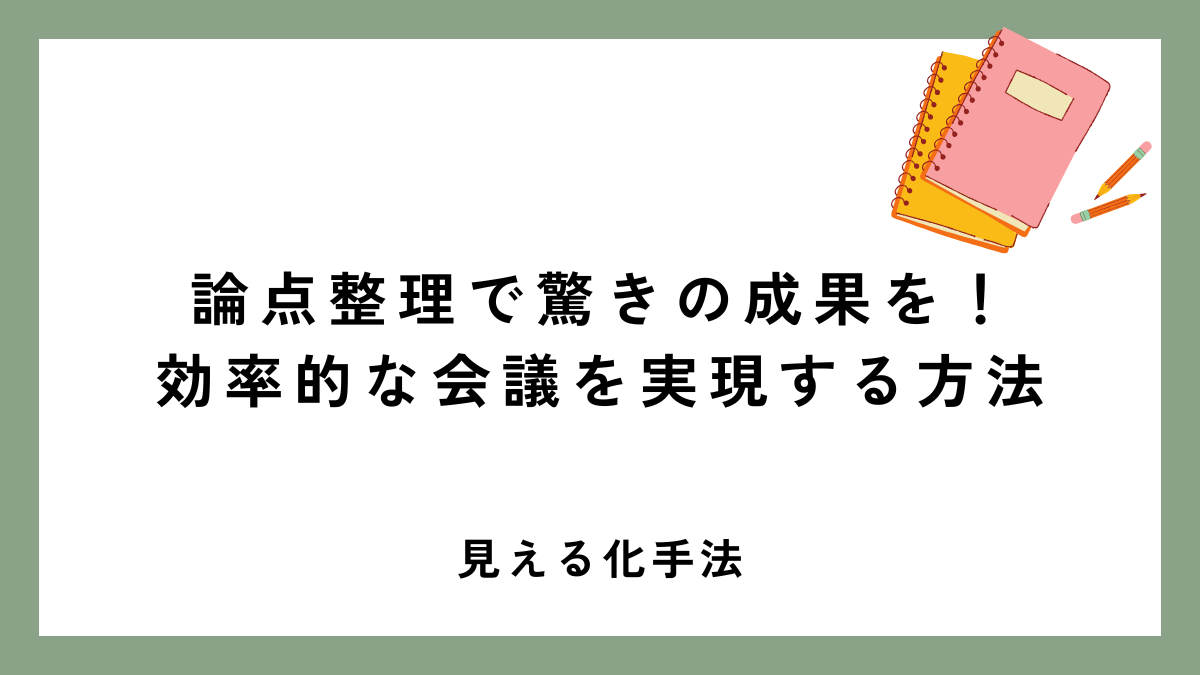
(2025/4/1 更新しました)
日本の生産性が低い原因として「会議が多い」と言われていますよね。
確かに、私の会社時代も 多くの会議がありました。
ダラダラとした会議、結構閉口したものです。
こうした会議が多い理由のひとつに「決まらない」があります。
原因は、論点が整理されていないからですね。
今回は「効率的な会議を実現する方法としての論点の整理」について紹介します。
少し工夫するだけで効率的な会議ができると思いますので、一読ください。
尚、私の在籍していた会社は「会議のやり方」で書籍にもなっている会社です。
そこで培った経験に基づいています。
会議のスタート地点:論点整理の重要性を理解する

会議が失敗する原因と論点整理の役割
会議が失敗してしまう主な原因には、目的が曖昧であること、議題が多すぎること、参加者に必要な情報が事前に共有されていないことなどが挙げられます。
これらの要因により、議論の焦点が定まらず、効率的な結論や成果につながらない状況が生まれています。
以下のような会議よくありますよね。
- これ何のための会議なの?
- 何が決まったの?
- 集まる必要あるんだっけ?
このような問題を防ぐために重要なのが「論点整理」です。
論点整理とは、会議の中で扱うべき課題やテーマを事前に明確にし、議論の流れを構造化しておくことを指します。
これにより、どの問題をいつ、どの順番で検討するかが明確になり、参加者全員が同じゴールを共有できるようになります。
論点整理は会議を効率的にするための基盤とも言える重要なプロセスです。
論点がぼやけることで起きるデメリット
会議で論点がぼやけてしまうと、いくつかのデメリットが発生します。
まず、議論が拡散し、結論を導き出すのが難しくなります。
その結果、参加者にとって意味のある合意形成が得られず、結局再度会議を開く必要が生じる場合もあります。
また、議論の質が低下し、生産性が大きく損なわれることもあります。
特に日本のビジネス現場では「会議が多い」という課題が指摘されていますよね。
実は、論点整理不足による時間の浪費が組織全体の生産性に悪影響を与えているのです。
そのため、会議の生産性を高めるには、論点整理という基本的な取り組みが必要なのです。
費用対効果を考えるマインドセット
会議にどれぐらいのメンバーが参加するでしょうか。
10人の会議を1時間する場合、時給 3,500円ならば 35,000円のコストがかかっています。
一人の月給の1/10ぐらいですよね。
1回の会議には、これだけのインパクトがあるのです。
こうしたコスト意識を持つことで、効率的で意味のある会議を実施をしようとするマインドが培われます。
会議を設定する際には、コスト計算することを心掛けましょう。
準備がカギ!論点整理のステップと事前準備
事前に考えるべき6つの視点
効率的な会議を実現するためには、事前準備の段階で5つの視点を意識することが重要です。
1つ目は、会議の目的を明確にし、それが「決定」「情報共有」「意見集約」などのどのタイプに該当するのかを判断することが大切です。
2つ目は、テーマを適切に絞り込むことです。
議題を詰め込みすぎると、1つ1つの論点を深く掘り下げられず、表面的な議論で終わる可能性が高くなります。
時間切れになることもありますよね。
そのため、達成すべき目標に基づいて優先順位をつけ、重要な論点に集中することが求められます。
3つ目は、適切な参加者を選定することです。
例えば会議の目的が「決定」ならば、決定権のある人は必須ですよね。
「意見集約」であれば、関係する部署の実務者の方が良いかもしれません。
会議の人数はコストになることを念頭において、適任者を選定しましょう。
4つ目は、参加者の職層や専門知識のレベルを把握し、必要な情報を適切に提供できるよう準備をしましょう。
マネジメント層と実務者とでは、決定するのに必要な情報は異なりますよね。
5つ目は、議題を実現可能なアクションへと導くため、達成すべきゴールを具体化することです。
今回の会議で「決めるべき最低限のレベル」を明確にしましょう。
私の場合は、優先順位を付けた「決めることリスト」を事前に準備していました。
決めるべき最低ラインの目印も付けています。
それに合わせて資料の準備をし、そして順番に決めていけば「最低限のレベル」はクリヤすることができます。
6つ目は、会議が生産的に進行するかを見直し、準備した内容を再確認することです。
要は、しっかりと準備できたかの確認です。
アジェンダを使った効果的な整理術
アジェンダは、会議の進行と論点整理をスムーズにするための重要なアイテムです。
アジェンダには、会議の目的や趣旨、議題と時間配分を明確に記載し、参加者全員が事前に目を通せるよう共有しましょう。
会議の目的が「決定」ならば、アジェンダにもその旨を書きましょう。
これにより、目的とは異なる意見を防ぐことができます。
さらに、会議の冒頭でアジェンダを再確認することで、参加者に会議の全体像を理解してもらうことで、主体性を促す効果があります。
アジェンダは会議を活性化させるだけでなく、時間配分や論点整理をサポートする効果的な方法です。
会議中に論点をまとめる!ファシリテーションのスキル
議論を活性化させるためのファシリテーターの役割
会議を効率的に進める上で、主催者の役割は非常に重要です。
主催者は、ファシリテーターとしての役割を行う必要があります。
ファシリテーターは、議論の方向性を整え、参加者全員の意見を最大限に引き出す役割を担っていますよね。
例えば、特定のメンバーの意見に偏らないように公平な議論を促したり、発言しづらい参加者に声をかけることで、より多角的な視点を引き出すことです。
また、論点整理を行いながら会議の進行をサポートすることが、活発な議論と具体的な結論に大きく貢献します。
混乱を防ぐ話題の体系整理テクニック
議論が迷走しないためには、話題を体系的に整理するテクニックが有効です。
まず、会議の目的に沿った大枠のテーマを明確にし、その下に細分化された議題や論点を整理します。
この際に活用できるのがホワイトボードです。
論点として出てきた意見を体系的に整理していき、参加者が今何を話し合っているのかを把握しやすくします。
そして、「重要度の高い問題」から順番に議論を進めることで、意見の集約を図っていきます。
体系的に視覚化されると、客観的に思考するようになるので 効果的な方法のひとつです。
さらに、「決めるべき最低限のレベル」があれば、そこに誘導することも効果的な方法です。
要は、ホワイトボードに書いてある「決めるべき最低限のレベル」を中心に、議論するのです。
議論の発散を防ぎ、意見の集約もやりやすくなります。
私がよく使っていた方法で、ほとんど「決めるべき最低限のレベル」は達成しています。
また、事実と意見を明確に分けることも混乱を防ぐコツですね。
たとえば、データに基づく客観的な事実を先に共有し、その上で議論する方法を取ると、意見が集約されやすくなります。
時間配分と論点の優先順位付け
会議の生産性を高める上で、時間配分と論点の優先順位付けは欠かせない要素です。
限られた時間の中で効率よく成果を上げるためには、会議の冒頭で全体の時間をどう使うかを明確に示し、優先度の高い論点から取り組むことが必要です。
但し、揉めそうな議題がある場合には、最初は軽い議題から始めると良いです。
会議の始めは、まだ参加者はウォーミングアップ中の場合が多いですよね。
まず軽い議題をさっさと処理し重い案件に入ると、より良い議論ができることが多いです。
また、議論が進行する中で論点が追加された場合、必ず元の目的や優先度と照らし合わせることです。
目的や優先度から離れている場合は、追加論点は今回の会議からは切り離し、別の会議として実施することを提案しましょう。
これにより、重要な論点が後回しになるリスクが減るとともに、時間配分が乱れることを防ぐことができます。
ファシリテーターが、時間を適切に管理することで、会議は効率的かつ成果のあるものになります。
まとめ
今回は「効率的な会議を実現する方法としての論点の整理」について紹介しました。
やはり一番は、事前準備です。
事前準備をしっかりやれば、必ず効率的で意味のある会議は絶対にできます。
ぜひ、あなたなりに工夫して 実施してみてください。
さて、今回の記事の中で「ホワイトボード」について記載しました。
以下の記事では「ホワイトボードの体系的・構造的な書き方」について紹介していますので、ぜひこちらも併せて読んでみてください。
投稿記事:3分割法で伝える力を磨く!ホワイトボードの書き方のコツ