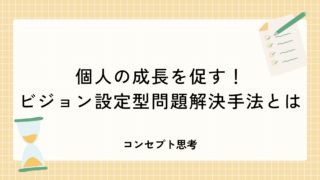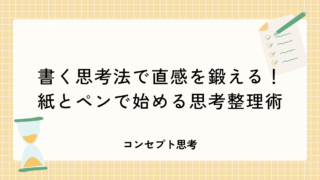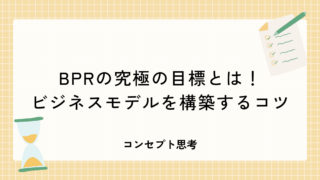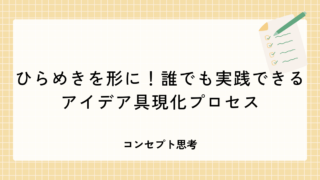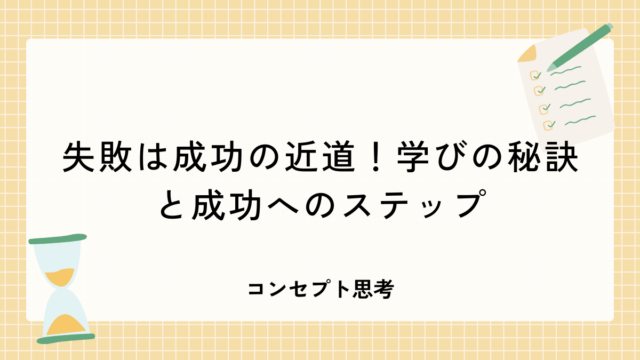ひらめき力UP!アイデアを生む人が実践する仕事での習慣とは

(2025/4/20 更新しました)
「新規のビジネスアイデアを出してください」
こういう機会ありませんか?
私も在職中は、3年サイクルぐらいであった記憶があります。
急に言われても、アイデアなんて すぐには出てこないですよね。
日頃から興味を持ち 頭を使っているから、アイデアは 出てきます。
また、アイデアを実際の行動にした経験があるから視野も広がるのです。
やはり、アイデア出しには習慣が大事なんですよね。
今回は「アイデア出しの基礎づくりの方法と実際の日常の仕事で習慣化すると良い行動」について紹介します。
私自身は、会社側から言われるまでもなく、常に自分でアイデアを出し実現してきた実績があります。
こうした経験に基づいています。
アイデアを生み出す基礎づくり

自分のインプット習慣を見直す
アイデアを出せる人になるには、まずインプットの質と量を見直すことです。
単純に情報を増やすだけでなく、多様な情報に触れることが効果的です。
本・記事・映像だけでなく、人との会話や日常の出来事からも、新たな視点を得ることができます。
仕事でも普段会話することにない他部署の人たちと話すことで、自らの領域とは異なる視点を持つことができますよね。
特に読書は、新しい知識を得るだけでなく、自分の思考を深める大切な習慣です。
毎日少しの時間でも読書を続けることで、年間数十冊の本を読むことにつながり、それが新たな発想のきっかけを増やします。
私も、年に100冊以上は読んでいます。
インプットで得た知識を どう解釈し内面化していくのかを常に意識することが重要ですね。
日常にひらめきの種を散りばめる
アイデアは特別な作業の結果ではなく、日常の中からも生まれます。
そもそも「アイデアは、既存のアイデアの組み合わせ」と言われていますよね。
例えば、いつもと違う道を歩く、1日に一つ新たなことに挑戦する、普段なら読まないジャンルの本を読むなど、行動の変化が発想力を刺激します。
また、アイデアは、日常のさりげない時間に生まれることがありますよね。
例えばカフェで聞こえてくる人々の会話や、店舗で見た人々の行動、偶然目にしたキーワードなど日常の中で新しい刺激をキャッチするアンテナを立てることも大切です。
アイデアを出せる人は、偶然をチャンスとして活用する能力に長けているものです。
私自身は、キーワードをつなげて発想することが多いので、偶然見つけたキーワードを大切にしています。
アウトプットを習慣にすることの重要性
どんなに多くのインプットがあっても、アウトプットしなければ最終的なアイデアにはならないですよね。
何かを記録したり、話したりする行為は、頭の中で混沌としている情報を整理し、自分なりの視点や意見に変えていくプロセスです。
特に、すぐにアウトプットすれば、記憶にも定着しますよね。
何かの機会に記憶から出てくる可能性が大幅に高まります。
また、アイデアは 結局は量です。
数多く出すことによって、徐々に質は上がります。
なので、より多くアウトプットした方が、独創的で革新的なものに進化する可能性があります。
私自身は、インプットした情報は なるべく早い時期に人に話すようにしています。
メモに記憶することもしていますが、人に話す方が会話になるため 次のインスピレーションが出やすくなるからです。
また、ビジネス書で紹介しているツールは、必ず仕事に適用しています。
発想の視点を増やすことができますので、おすすめの習慣です。
「既成概念」を疑うクセをつける
新しいアイデアは、必ず既成概念を覆すものです。
なので、既存のものをそのまま受け入れるのではなく、「そうでない何か」を考える習慣が必要です。
特に今は、便利なものがありふれている世の中なので、意識して考えないと受け身の生活に慣れてしまいます。
たとえば、日常で使っているものや、守られているルールを「なぜこうなっているのか?」「別の方法なないのか?」と考えるだけで、固定概念から脱却した思考が生まれます。
特に仕事では、決まったやり方・ルールで日々廻っていますよね。
これが普通と思った瞬間から、思考は停止します。
アイデアを出せる人は、現状をそのまま受け入れるのではなく「もっと良くする方法はないか?」と常に考え続けています。
それこそが、アイデア創出の原動力です。
私は、同じことをやることが大嫌いな性格です。
なので、2回目には絶対に違うやり方で実施します。
それが積もれば、イノベーションにつながるアイデアが出てくるのです。
創造力をUPするための日常の仕事での習慣化
自分自身の感情を大切に、そして行動する
仕事をしていれば、
- なんで こんなやり方をしているのだろう
- 私だったらこうするのに
- あ、これ面白いかも
こうした経験 普通にあると思います。
そして、これらの言葉の共通点は すべて自分自身の感情から発せられています。
論理より先に、感情ですよね。
また、この感情には 不快(不平・不満など)・快が含まれています。
で、この感情に気づくことが大切なのです。
ビジネスって、結局は問題解決です。
人の不快を解決し、快を増やすことです。
自分自身にこうした感情がなければ、アイデアなんて出てくるはずがないのですよね。
なので、仕事中に「感情につながる経験」をいっぱいすることは とても大切なのです。
また、もうひとつ大切なことは「感じたら行動する」ことです。
自分の業務の範疇ならば、すぐに実践できますよね。
自部署内であれば、調整で実施することができます。
感じたことを全て行動しようといっているのではありません。
感情が動いた案件の中で、自分がやりたいと思ったものだけでも十分です。
行動は 経験になります。
小さな経験を積み重ねるうちに、視野が広くなってきます。
周りが どんどん見えてくるようになるのです
また、実践している姿は 周りの人も 意外と見ています。
手を差し伸べてくれる人も出てきます。
やがて、大きなことにも 挑戦できるようになります。
そうなれば、視野の高い・難易度の高いアイデアも出てくるようになるのです。
自部署のメンバーに興味を持ち教えてもらう
同じ職場で働いていて、関係がないということはありません。
必ずなんらかの関係はあります。
上流・下流工程という関係もあります。
直接工程・間接工程という関係かもしれません。
一緒に働いて成果を出している仲間です。
先ずは、興味を持ちましょう。
そして、なんらかの仕事上の関係があった際は どんなことをしているのか聞いてみましょう。
雑談程度で十分です。
その上で、聞いていて興味があったことは もっと教えてもらいましょう。
興味を持って聞いてきた人に、むげに断る人って そんなにはいません。
経験上、熱心に教えてくれる人の方が多いです。
お互いの業務の関係を 確認しましょう。
お互いに共有することで、信頼関係を築くこともできます。
こうして、自部署の仕事への理解を深めるのです。
視野が広がれば、出てくるアイデアも変わります。
他部署が何をやっているか興味を持ち教えてもらう
他部署に行くことも多いと思います。
打ち合わせが終わったら、少しだけ雑談をしましょう。
- 相手が 今どんなことをやっているのか
- 他部署で関心があることは何か
- 会社方針に対して、どんなことを実践しているのか
ちょっとだけ 聞いてみるのです。
そして、興味があることがあれば 時間を取らせない範囲で見せてもらいます。
百聞は一見にしかず です。
もし、もっと知りたければ 別途時間を取って教えてもらいましょう。
同じ会社であれば、向かっている方向は同じです。
参考になるものは、なんでも吸収しましょう。
これによって、全社視点で考えることができるようになります。
また、何かアイデアを提案した時には、協力してくれるかもしれません。
実際の私自身の経験では、自部署より他部署の協力があって実現できたアイデアの方が多くあります。
自部署の方が、既成概念に捉われているものなのです。
まとめ
今回は「アイデア出しの基礎づくりの方法と実際の日常の仕事で習慣化すると良いこと」について紹介しました。
私自身は、会社側から言われるまでもなく、常に自分でアイデアを出し実現してきた実績があります。
仕事を淡々とこなすだけでは、自分だけの狭い範囲でしか アイデアは生まれません。
自分の仕事をこなしつつ、少しでも興味を持って視野を広げましょう。
そして、面白いアイデア・ビジネスモデルを創造しましょう。
今回「アイデアを出す習慣」について紹介しましたが、実際にアイデアを出すには「書くこと」が重要です。
以下の記事では「書く思考整理術」について紹介していますので、ぜひこちらも併せて読んでみてください。
投稿記事:書く思考法で直感を鍛える!紙とペンで始める思考整理術
また、アイデアは「具現化」することも大切ですよね。
以下の記事では「出てきたアイデアを具現化するためのプロセス」について紹介していますので、ぜひこちらも併せて読んでみてください。
投稿記事:ひらめきを形に!誰でも実践できるアイデア具現化プロセス