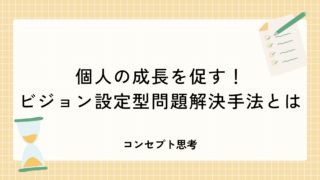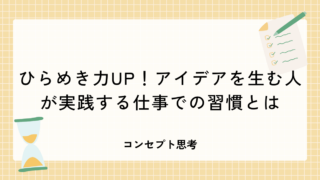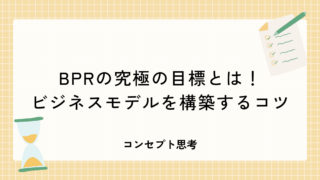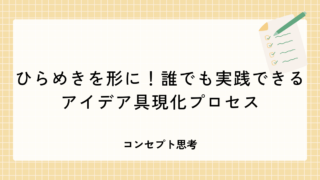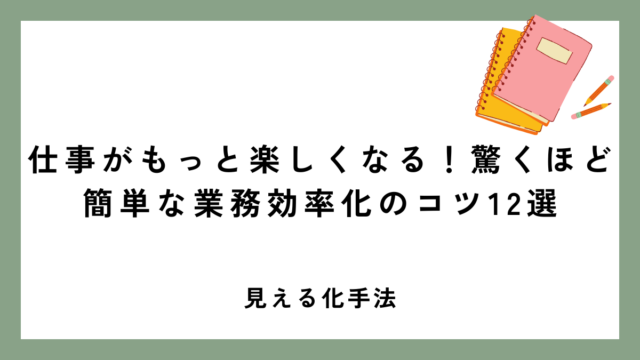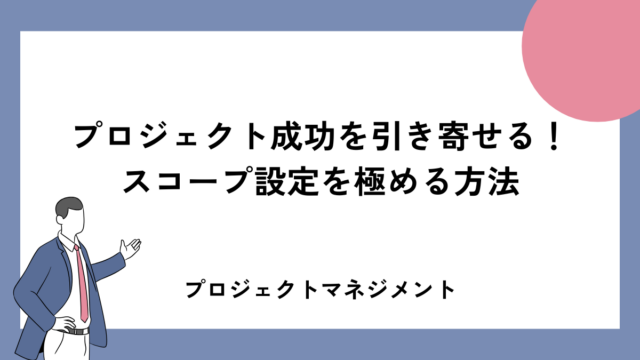「企画構想策定」初心者でもわかる手順と成功のコツ
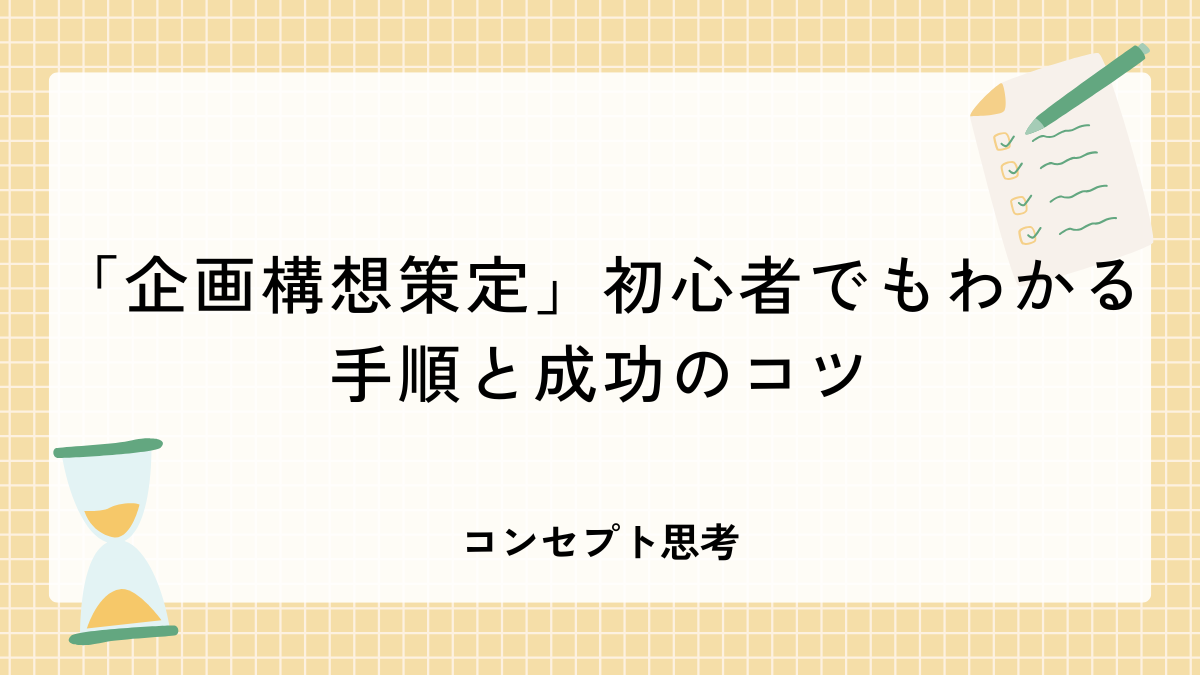
(2025/3/30 更新しました)
企画を考えるのは面白いと思いませんか?
実は、個人からでも 明日のビジネスを生み出すことができるのです。
なぜなら、最初のアイデアは 先ずはたった一人から生まれますよね。
であれば、抜本的・本質的に変化を起こす「破壊力・突破力がある企画」を創りたいと思いませんか?
今回は「抜本的・本質的な変化を起こす企画構想の策定」について紹介します。
初心者向けに書いていますが、経験を積めば「破壊力・突破力がある企画」もできるようになります。
尚、私は 業務プロセス改革プロジェクトで、新しいビジネスモデルを創った経験があります。
それ以外にも、あなたが普段目にしているものもあります。
そんな経験に基づいています。
構想策定とは何か?基礎知識を押さえよう
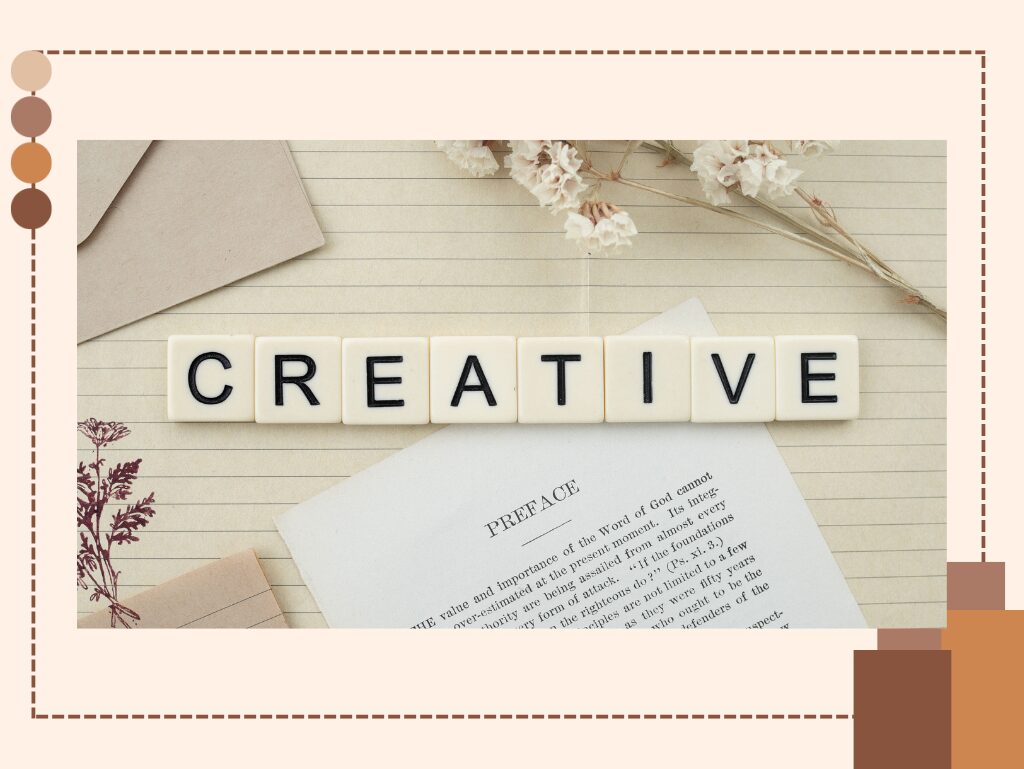
構想策定とは
構想策定とは、プロジェクトや業務改革を成功に導くための最初のステップであり、企画や方向性を明確化するプロセスです。
システム開発や業務プロセス改革・DX化を進める際には特に重要で、具体的な計画設計や実行に先立ち、目的や目標を整理する「最上流工程」として位置付けられます。
初期段階で方向性が曖昧のまま進めると、後に軌道修正が必要になり、余計なコストや時間を生む原因となります。
私が見てきた失敗するプロジェクトの原因は、多くはこの工程での検討不足です。
それほど、プロジェクトの成功を左右する重要な工程です。
構想策定の重要性とは?
構想策定の重要性は、プロジェクト成功の基盤を築くことにあります。
この段階で確固たる方向性を示すことで、チーム全体の目標意識を統一し、その後の検討がスムーズに進むだけでなく、リスクを最小限に抑えることが可能となります。
また、現状分析を通じて課題を深く理解し、明確なゴールを設定することで、ムリ・ムダ・ムラのない計画を立てることができます。
たとえば、ITシステム導入では、必要な機能やスコープを明確化しないと、仕様変更や作業の遅延につながる可能性が高まります。
業務プロセス改革でも、どの範囲を実施するか明確にしないと、導入時には大混乱になります。
構想策定は、成功に導く基盤となると共に、失敗を防止する鍵となるプロセスなのです。
構想と計画の違いを理解する
構想と計画の違いを理解することは、プロジェクトを正しく進めるための第一歩です。
構想は、プロジェクトの大枠を決定する段階であり、ビジョンや目的、達成すべき目標を示します。
一方、計画は、構想を具体的なタスクやスケジュールに落とし込むプロセスです。
たとえば、「業務効率を25%向上させる」という構想がある場合、それを実現するための具体的な手順やリソース配分を計画として詳細に策定します。
構想段階では柔軟性と創造力が求められる一方、計画段階では実行可能性や現実性が重視される点が大きな違いです。
この違いを認識することで、各ステップにおいて集中すべき課題を明確にし、効率的に進めることができます。
構想策定の進め方:基本的な手順を解説
1. 現状分析からスタート
構想策定において最初のステップとなるのが現状分析です。
このプロセスでは、現在の業務プロセスやシステムの状況を正確に把握することが求められます。
何が抜本的・本質的な課題で、どの部分を改善する必要があるのかを明確にすることで、効果的な構想を検討するための基盤が築けます。
現状分析の質がその後の計画全体の成否に直結するため、漏れなく進めることが重要です。
とはいっても、現実には組織の中は問題でいっぱいです。
私が在籍していたエクセレント・カンパニーと称される会社でも、問題だらけなんです。
例えば、こんな事例ありませんか?
- 以前から変わらない意思決定の方法
- 環境が変化しているのに変わらない業務・組織
- 新たな仕事(製品・サービス)が全く増えていない組織
まずは、気づくこと・疑うことからがスタートです。
そして、様々な視点で深掘りしましょう。
この繰り返しにより、必ず抜本的・本質的な問題を見つけ出すことができます。
私が起こしたプロジェクトのほぼ全ては、このプロセスを通じて始めています。
2. 課題の抽出と目標設定
現状の課題が明らかになったら、それを踏まえて解決すべき具体的な課題を抽出します。
その際には、それぞれの課題の優先順位を付けることがポイントです。
その上で、トップダウン視点で ビジョン(ありたい姿)を考えて描きます。
構想そのものは個人からのボトムアップですが、思考はトップダウンで行います。
そして、それを達成するための目標を設定します。
目標設定は曖昧なものではなく、具体的で測定可能な内容にすることが求められます。
ビジョン・目標は、プロジェクトの羅針盤です。
チームの士気を鼓舞し、モチベーションが高まるものを描き共有しましょう。
ちなみに私の場合は、ビジョン・コンセプト・目標の3つを決めています。
ビジョン・目標で進むべき道を示し、コンセプトで士気を鼓舞するイメージですね。
3. 構想の骨子を具体化する
課題と目標が明確になった後は、それを実現するための構想の骨子を形にする段階に進みます。
要は、解決策の検討になります。
そして、実現するための戦略・戦術を考えていきます。
例えば、業務プロセス改革の構想の場合、最初の1年目は 試行錯誤です。
2年目で芽が出て、3年目で置き換わります。
私の経験からは、これぐらいのステップで動きます。
組織内でのタイミングも考慮しながら、戦略・戦術に落としていきましょう。
また、このプロセスでは 構想の全体像や方針を明確にし、それをプロジェクトチームや関係者に共有できる形で整理していきます。
プロジェクト構想書の素案ですね。
たとえば、ITシステム開発の場面であれば、導入するシステムの概要や主要な機能を定義することが骨子の具体化にあたります。
関係者の意見を取り入れ、多角的に検討することが成功の鍵となります。
4. 実現可能性を検証し計画を策定
最後に、構想が実現可能かどうかを検証し、具体的な計画を策定する段階です。
このステップでは、リソース・スケジュール・コストなどを考慮しながら、計画全体の実現性を確認します。
また、検討した構想が解決すべき課題に対してどれほど効果的かを評価し、不足があれば調整を行います。
いわゆるプロジェクト構想書としての成果物にします。
こうして立てられた計画をもとに、プロジェクトが具体的に始動します。
構想策定を成功させるコツと注意点
チーム内での一貫したコミュニケーション
構想策定を成功させるためには、チーム内での一貫したコミュニケーションが欠かせません。
プロジェクトに関わるすべてのメンバーが共通のビジョンを持ち、目標や課題に対する認識を共有することで、構想の方向性を定める土台が整います。
そのためには、定期的にミーティングを行い、進捗状況や課題を共有する場を設けることが重要です。
また、メンバーそれぞれの意見を尊重し、複眼的な視点を取り入れることで構想の検討がより抜本的・本質的で実現可能なものとなります。
一方で、人には適性があります。
アイデア出しには少数のメンバーで行い、定期ミーティングでチーム全体で議論する方法も有効です。
私は、アイデア出しの時は 少数精鋭のメンバーで行っていました。
現状分析の質を高めるポイント
構想策定の第一ステップである現状分析は、プロジェクトの成功を左右する重要な工程です。
現状を正確に把握するためには、既存のデータや業務プロセスを細かく検証し、課題や改善点を具体的に洗い出す必要があります。
一方的な主観に頼るのではなく、データや事実に基づいた分析を行うことで、より質の高い成果を期待できます。
また、関係者からの意見を集約し、多様な視点を反映させることで、見落としを防ぎつつ構想の精度を高めることができます。
少なくてもプロジェクトのスコープ内にいる実務者には、必ずヒアリングするべきです。
優先順位を明確にする方法
構想策定における課題や目標が多岐にわたる場合、そのすべてを同時に進めるのは現実的ではありません。
特に、規模の大きいシステム開発や業務プロセス改革・DX化を進める際には、一度で全て解決するのは困難です。
そのため、どの課題を優先的に解決するべきか明確にすることが大切です。
優先順位を決める際には、プロジェクト全体への影響度やリソースの活用状況を総合的に判断する必要があります。
私のおすすめは、プロジェクトで最も影響がある部分から実施することです。
アイデアが革新的であるほど、抵抗は大きいですよね。
小さく始めて実績を作り、大きく育てることが重要だと考えています。
解決策の考え方
どうせやるのならば、抜本的・本質的な問題解決を選ぶべきですよね。
集まった問題は相互に依存しています。
大きな括りで、全体を俯瞰しましょう。
そして、AもBもCも解決する何かを考えましょう。
チームでのブレーンストーミングやKJ法・マインドマップなどのツールを活用して、多角的に検討することをおすすめします。
私は、それら以外に「書く思考整理術」など、いろんなツールを活用して検討しています。
まとめ
今回は「抜本的・本質的な変化を起こす企画構想の策定」について紹介しました。
初心者向けに書いていますが、経験を積めば「破壊力・突破力がある企画」もできるようになります。
私自身も、そうしてステップアップしてきています。
企画を考えるのは、面白いものです。
どうせならば、抜本的・本質的に変化を起こす「破壊力・突破力がある企画」を創りましょう。
さて、今回は「構想策定」について紹介しましたが、実際に具現化・実現化して行くことも重要です。
以下の記事では「アイデアの具現化・実現化」について紹介していますので、ぜひこちらの記事も併せて読んでみてください。
参考投稿記事:ひらめきを形に!誰でも実践できるアイデア具現化プロセス
参考投稿記事:アイデアを確実に形にする!成功する実現化術とは