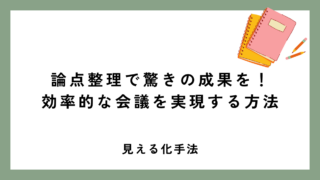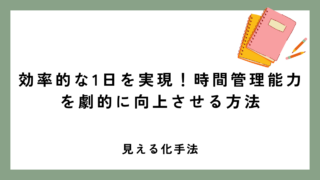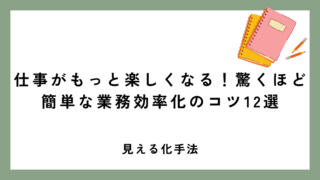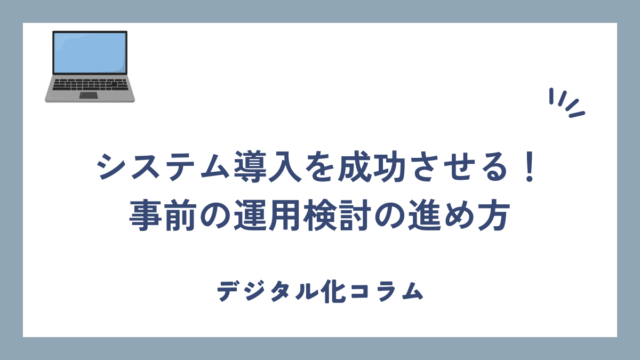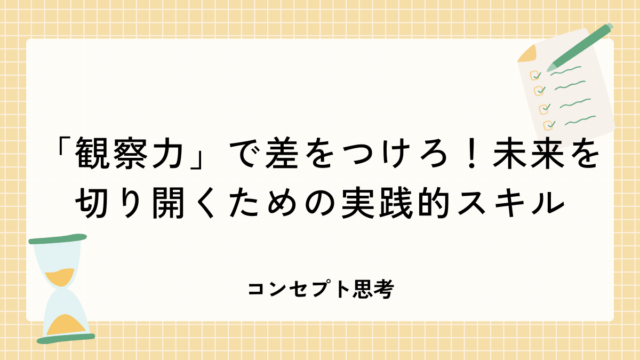未来の働き方を変える!業務効率化の実践アイデア
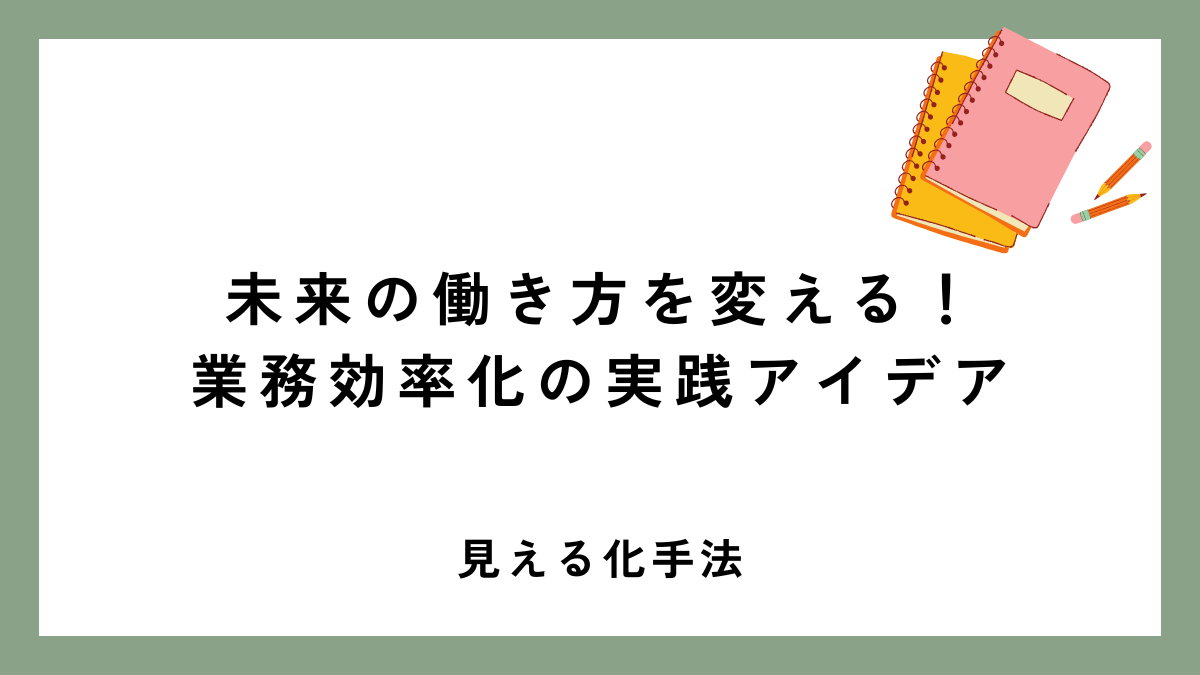
(2025/3/25 更新しました)
働き方改革って、長時間労働ばかりが取り上げられた印象ありませんか?
そして、労働時間ばかりが注目されて、働き方が何も変わっていないのに残業時間だけが制限されていると思いませんか?
これでは、「働き方改革って何?」ですよね。
働き方改革の1番の目的とは、生産性を向上させることです。
そして、人の役割を再考することです。
AI・ロボットなどのテクノロジーの進化により、人の役割は 確実に変わります。
今回は「働き方改革のための業務効率化と役割分担再考の進め方」について紹介します。
私自身は、大企業で20年以上プロジェクトリーダーをやっていました。
ほとんどのプロジェクトはBPRです。
もし今も在籍していたとしたら、絶対に実施しているプロジェクトになります。
働き方改革の背景と業務効率化の重要性

働き方改革が求められる理由
近年、日本社会では少子高齢化や働き手不足の深刻化が進行しており、生産性の向上と柔軟な働き方の実現が急務になっていますよね。
この背景をもとに国の政策として、働き方改革を推進し、労働環境の改善を図っています。
長時間労働の是正やワークライフバランスの実現が強調されていますが、1番の目的は生産性向上です。
これらにより、企業が効率的な業務運営を試行する動きが広がっていますよね。
業務効率化の目的とメリット
業務効率化は、業務フローの最適化を通じて、生産性を向上させることを目的としています。
この方法により、ムダな時間やリソースを削減し、コスト削減や労働力の適切な活用が可能となります。
また、業務負担が軽減されることで、従業員の満足度が高まり、モチベーション向上や離職率の低下といったメリットも得られます。
これらの効果は、企業の競争力の強化にもつながります。
一方で、従来の効率化とは異なる方法も出てきています。
AI・ロボットによる業務効率化の可能性
AI(人工知能)・ロボットは働き方改革の鍵となる技術として、大きな期待を集めています。
AI・ロボットを活用することで、日常的なルーチンワークや煩雑なデータ処理を自動化し、従業員がより本質的な業務に集中できる環境を整えることができます。
例えば、AIチャットボットの導入により、顧客対応の効率化や24時間対応を可能にし、サービスの質を向上させることも行われていますよね。
少し前に日産の最新工場がTVで紹介されていましたが、熟練工でしかできなかった作業をロボットが行っています。
犬が工場の番人になっている風刺画を見たことありませんか?
不審者の侵入を、つまり人が入ってくるのを防いでいる絵です。
AI・ロボットとの共存を考えていく時期になっています。
つまり、役割分担の再考です。
スキルと意識改革の重要性
業務効率化及び役割分担の再考を実現するためには、技術的なツールの導入だけでなく、従業員一人ひとりのスキル向上と意識改革が欠かせません。
具体的には、効率化のための方法や最新ツールの活用スキルの向上が挙げられます。
RPAも その一つですよね
また、従業員自身が業務課題を意識し、解決策を積極的に模索するマインドセットを養うことも重要です。
意識改革を進めるためには、経営層から従業員まで全員が効率化の必要性を共有し、成功例や改善事例をフィードバックする文化を創る必要があります。
だいぶ前に流行ったナレッジシステムも、有効なツールになるのかもしれませんね。
業務効率化と役割分担再考の進め方
進め方としては、以下の手順になると考えています。
- 現行業務フロー作成
- 各業務の付加価値判定
- 役割分担判定
- 必要な能力判定と人材開発
- 役割分担の見直しと新側業務フロー作成・展開
各手順のポイントとなる視点について、概要を紹介いたします。
現行業務フロー作成
まずは現行の業務フローを作成し、見える化することが 基本です。
いきなり全業務に展開をするのは難しい場合は、基幹業務から実施します。
業務の効率化の視点からは、第3階層まで落として作成すれば十分です。
一方で、RPAの導入も不可避だと思います。
その場合には、適用する範囲を決めて、第4階層まで落とす必要があります。
業務フローの階層については、以前の投稿を参照ください。
(下に投稿記事記載します)
各業務の付加価値判定
業務にどれだけの付加価値があるのか 判断することになります。
単純に、情報を加工しているだけでは 作業ですよね。
作業は 代替できます。
仕事の目的・目標を明確にした上で、最低限の判定基準として 以下3つ挙げます。
- アウトプットの質
- 人の関与度合い
- 人の関与度の質
役割分担判定
最低限、以下 4つに分ける必要があると考えます。
- 現時点の技術で代替できるもの
- 自ら開発し代替するもの
- 代替技術を待つもの
- 人がやるもの
人がやるものは、「人しかできないもの」を選択することです。
必要な能力判定と人材開発
各業務の付加価値判定で、人の関与する業務の質がわかってきます。
そして、役割分担判定で、当面「人がやるもの」を決めました。
それに基づき、必要な能力を体系的にまとめます。
そして、能力開発計画に落とし込み、教育プログラムを作ります。
実際の教育そのものは、社内で全てを準備する必要はないと思います。
今では、リカレント・リスキル教育を実施しているビジネスがたくさんあります。
役割分担の見直しと新業務フロー作成・展開
分担を見直した後の新業務フローを作成します。
そして、展開・周知徹底を図ることです。
最初は混乱も発生しますが、貫くことが重要です。
最初に戸惑うのは 人であれば当然ですが、人には 柔軟性があります。
やがては、さらなる工夫を考えるようになります。
そのためにも前述した意識改革が必要になってきますね。
継続的な見直し
AI・ロボットは、日進月歩で進化します。
定期的に見直しが必要です。
特に、役割分担で「代替技術を待つ」にした業務は、市場をウォッチすることです。
また今回は、 既存のビジョン・戦略・ビジネスモデルを前提として 手順を紹介しました。
実際には、ビジョン・戦略・ビジネスモデルが変わることもあるでしょう。
抜本的に、業務フローから見直すことも 発生すると思います。
その場合でも、実施する手順は同じだと考えています。
まとめ
働き方改革の1番の目的とは、生産性を向上させることです。
そして、人の役割を再考することです。
2035年に向けて、働き方は 抜本的に改革されます。
AI・ロボットなどのテクノロジーの進化により、人の作業は代替されていくでしょう。
今回は「働き方改革のための業務効率化と役割分担再考の進め方」について紹介しました。
もし今も元会社に在籍していたとしたら、絶対にやりたかったプロジェクトですね。
少し残念です。
さて、今回の記事の中で「業務フローの階層」について書きました。
以下の記事で詳細を紹介していますので、こちらの記事も併せて読んでみてください。
投稿記事:活用目的によって使い分けよう!業務フロー図の作成レベルと適用範囲