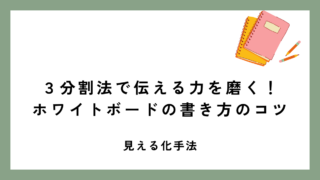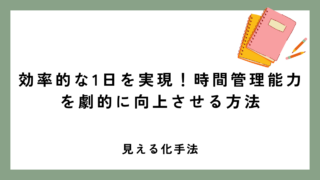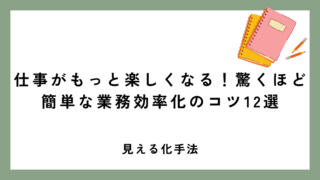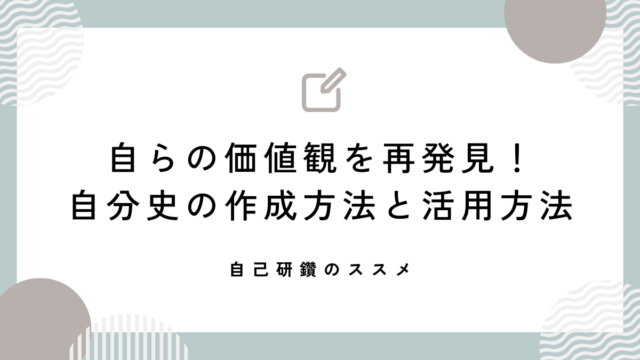活用目的で使い分けよう!業務フローの作成レベルと適用範囲
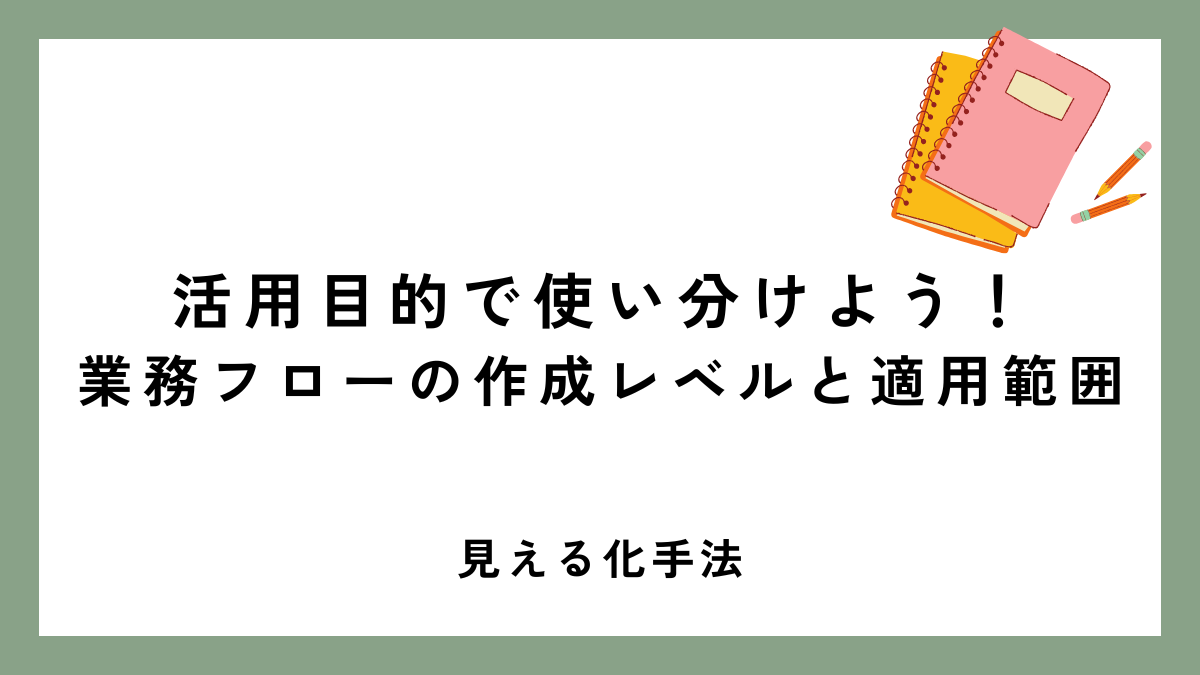
(2025/7/2 更新しました)
業務改革に着手したいけど
「どのレベルまでの業務フローを作成すれば良いのかわからない」
ビジネスモデルを変革したいけど
「どこまで既存の業務を取り上げたら良いか悩んでいる」
これらの検討をする際に、必要になるのは業務フロー図ですよね。
理由は、ビジョン・戦略があっても、実際に動かすのはプロセスだからです。
業務フロー図は、ツールのひとつです。
ツールは、使い方・活用の仕方次第で 万能ツールになります。
今回は「業務フローの作成レベルとレベル毎に活用できる適用範囲」について紹介します。
私自身は、海外で賞を取ったビジネスモデルを構築した経験もあり、多くの業務改革プロジェクトを経験しています。
その経験に基づいています。
業務フローの作成レベルと適用範囲

業務フローを どのレベルまで、または、どの範囲を詳細化するのかは、実施する目的によって異なります。
業務改革であれば、ある特定の業務に焦点を当てることもありますし、ビジネスモデルであれば組織全般に焦点を当てることになりますよね。
まずはレベルについては、私の場合は「3階層に分けて考える」ことを 基本にしています。
目的によって、1階層レベルだけ 2階層レベルまで といった使い分けですね。
但し、最終的には実務が回ることが必須のため、担当レベルが理解できるように3階層目まで描きます。
また、作成範囲は、部署全体であれば その部署の業務全般になりますし、ある特定の業務であれば その範囲になります。
実際は、業務は相互に関係していますので、どこで切るかは 難しい問題です。
目的を考慮しつつ、経験で切り取っています。
但し、必要に応じて 追加・削除すれば良いので、それほど神経質にならなくても大丈夫ですね。
では、順番に作成レベルについて紹介していきます。
レベル1:ミッション・ビジョン・戦略・ビジネスモデル
部署間(会社間)の関係がわかるレベルで記載します。
自部署(自会社)の目的、位置付けを明確化にしていきます。
会社の組織図が これに当たります。
ある特定の部署の場合は、部署内の組織図です。
当たり前ですよね、そのために組織になっているのですから。
実際に業務フロー図にすると、業務フロー図の矢印は 双方向になります。
依頼し、回答すると言ったイメージです。
例えば、設計部署と評価部署の場合であれば、設計部署から見れば 「評価依頼をする」、評価部署から見れば 「依頼を受け、評価結果を回答する」 です。
なので、矢印は、実際に どういうプレーヤーが存在するのか、どう関係しあっているかを 明確にできれば十分です。
各機能(部署)が どう結ばれて、価値を上げているのかを描きます。
大体、レベル1では フローというよりは 絵を描くイメージです。
ビジネスモデルキャンパス、ご存知でしょうか。
これを絵に描いたイメージですね。
進め方は、現行フローを描き、アイデアを出しながら 新側を描くことになります。
基本、行ったり来たりの繰り返し作業です。
出てきたアイデアによって、現行フローに追加したり 部分的に詳細化するからです。
このレベル1で活用できる範囲は、以下です。
- 会社全体(各部署)のミッション・ビジョン・戦略を考える
- お客様視点を変えることにより、ビジネスモデルを考える
関係部署含めたDXにつながるものもあると思います。
私の事例では、ある部署のビジョン創りや新ブランドの戦略を練ったのも、このレベルで実施しています。
レベル2:事業・業務改革・ビジネスモデル
自部署(自会社)の中で、室や課レベルの業務の関係を記載します。
それぞれが、どういう役割でつながっているのかを明確化します。
例えば、前例「設計する」で言えば、基本構想を作成する(企画)、基本設計をする(設計)のレベルです。
関係を時系列に矢印でつないでいきますが、この際 、大まかに どういう情報が流れているかも 記載することが必要です。
イン・処理・アウトを明確にするのが業務フロー図作成の基本です。
これにより、各処理でどういうアウト(価値)が生まれているのかがわかります。
逆にいえば、処理のアウトで「提供価値がわかるレベル」で作成するということですね。
わかりやすくいえば、その部署で重要とされている書類・帳票が アウトとなるレベルで作成することです。
この階層で活用できる範囲は、以下です。
- 自部署(自会社)での抜本的な事業・業務改革を考える
- お客様に視点を変えることにより、ビジネスモデルを考える
考え方は、そのアウト(価値)をつくるのに必要な処理はどうあるべきかです。
私の場合は、通常 以下5つの視点で検討しています。
- 同じ価値をあげるのに 処理を合体できないか
- 同じ価値をあげるのに 違うやり方はないか
- 同じ価値をあげるのに 関係部署を巻き込めないか
- 同じ価値を上げるのに やることを変えられないか
- もっと価値を上げられないか
徐々に範囲を広げて考えます。
抜本的改革を実施するならば、③④まで考える必要があります。
ビジネスモデルならば、⑤まで必要ですよね。
実際の私の事例では、 DXによるビジネスモデル開発は このレベルで実施しています。
レベル3:事業・業務改革・システム開発
各担当の業務レベルまで落とします。
尚、この場合の業務は、作業ベースではなく それらを括ったものです。
(業務フローは、業務手順ではないです)
例えば、前例「基本構想を作成する」で言えば、データを分析する、アイデア出しをする、基本構想書を作成する などのレベルです。
関係を時系列に矢印でつなぎますが、この際 どういう情報が流れているかを、帳票記載項目ぐらいまで、記載することが必要です。
イン・処理・アウト + 情報は、業務フロー図作成の基本です。
特に、複雑に処理が絡み合うので、矛盾がないように イン・アウトへの注視が必要です。
作成方法については別投稿していますので、そちらを参照ください。
(下に投稿記事を記載します)
この階層で活用できる範囲は、以下です。
- 自部署(自会社)での事業・業務改革、改善を考える
- システム開発を行う
最終的に、新側の業務フローを社内・部署内に展開する際にも 利用します。
レベル3まで落とさないと、担当者が動けません。
私の事例では、システム開発の際にも作成していますし、業務改革では 数え切れないぐらい作成しています。
レベル4以下
作業ベースになります。
通常、ここまで落としませんが、RPAを導入する場合は必須です。
また、特定の問題を解決する際には、その部分だけ切り取って作成します。
費用対効果を考えて、実施しましょう。
まとめ
今回は「業務フローの作成レベルとレベル毎に活用できる適用範囲」について紹介しました。
ビジネスモデル変革や事業・業務改革では、業務フローで考えることが必要です。
ビジョン・戦略があっても、実際に動かすのはプロセスだからです。
私の場合は、3階層レベルに分けて考えることを 基本としています。
レベル1から順番に落としていけば、問題の本質は見えてきます。
問題の本質が分かれば、アイデアは 必ず出てきます。
活用目的によって使い分け、新たなことに挑戦していただければと思います。
さて、本文中にも記載しましたが、以下の記事では「業務フローの作成方法」について紹介しています。
ぜひ、こちらの記事も併せて読んでみてください。
参考投稿記事:業務フロー作成の劇的効率化!知らないと損する成功のコツ