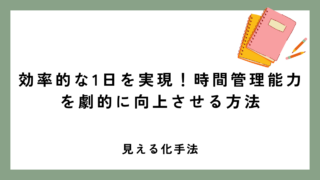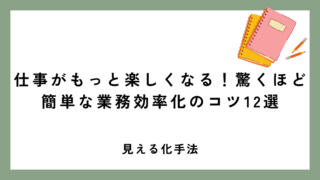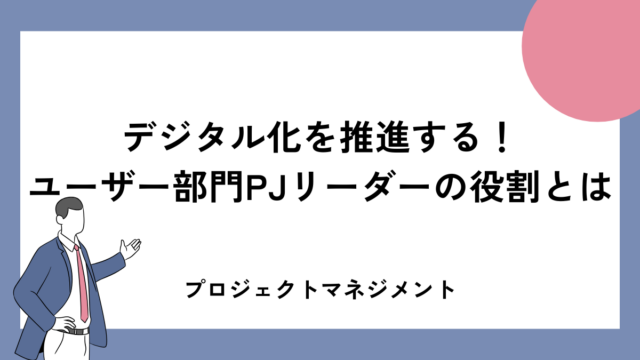業務標準化の目的と効率的な適用範囲・改訂のタイミングとは
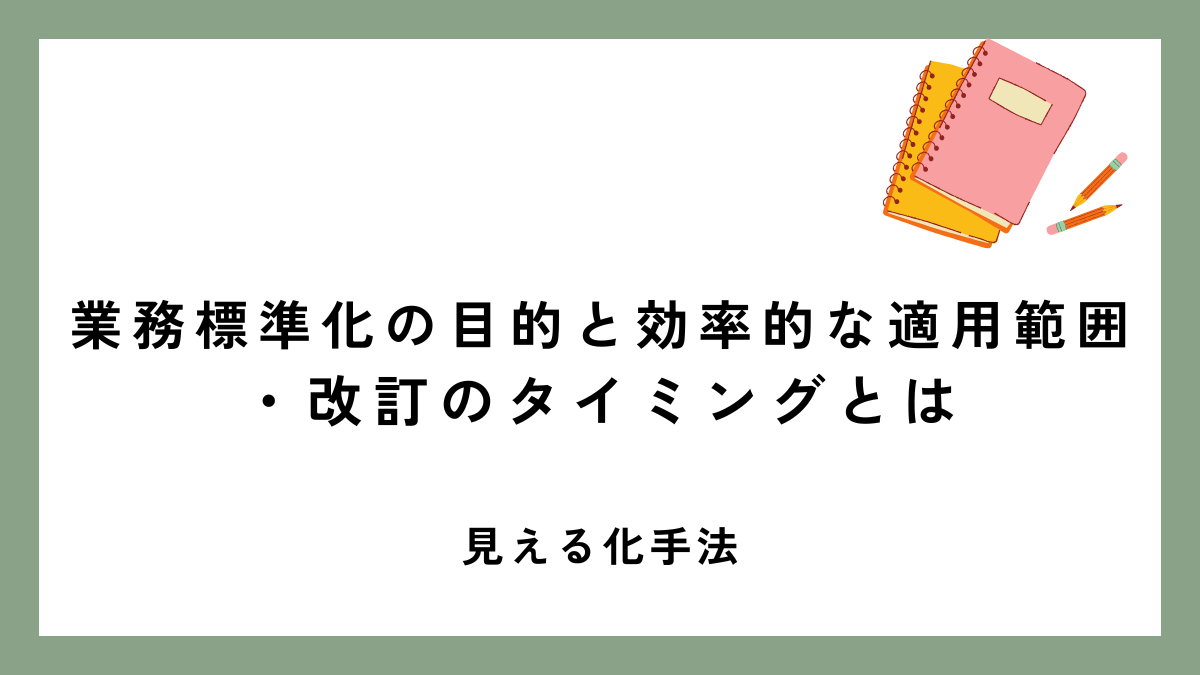
(2025/5/6 更新しました)
あなたのビジネスでは、業務の標準化していますか?
「とりあえず回っているので、必要性を感じない」
「標準化のための時間が取れない」
「作っても 改訂が面倒」
確かに 今だけを考えれば、こうした意見もありますよね。
でも、ビジネスって 今だけではないですよね。
常に、進化することが必要です。
とは言っても、全部の業務に適用するの?
確かに、効率的・効果的に行いたいですよね。
今回は「標準化の意義と効率的・効果的に実施するための業務の適用範囲・改訂のタイミング」について紹介します。
私自身、大会社の標準化委員をしていたこともあります。
その経験に基づいています。
標準化の意義とは

組織って、業務プロセスの集まりです。
そして、それぞれのプロセスは、過去から積み上げてきたものです。
でも、人って 工夫する生き物なんですよね。
時間が経つと、人によって やり方が異なってきます。
徐々に、暗黙知も 増えていきます。
やがて、個々の業務が見えなくなります。
また、環境の変化により組織間で抜けているところも いずれ顕在化します。
こういう状況になると マネジメントにまで影響しますよね。
業務標準化の意義は、大きくは以下3つです。
- 誰でも同じ品質で効率的に業務ができる
- 組織内で 相互依存関係が共有される
- 次の業務改善・業務改革につながる
以下に順番に紹介しますが、重要度は順番に大きくなっています。
誰でも同じ品質で効率的に業務ができる
標準化のドキュメントには、業務の実施方法が書いてあります。
作成した時点でのベストプラクティスです。
読むことにより、いつ・どんなことをするのかがわかります。
後は、適宜周りに聞くことにより、誰でも同じ品質で効率的に業務を回すことができます。
一般的な標準化の意義・目的ですね。
組織内で相互依存関係が共有される
業務は、ひとりでは廻りません。
常に前後工程と関係しています。
標準化のドキュメントで、相互依存関係を共有することができます。
困った時の相談先も わかりますよね。
それと、組織の中の自分自身の業務の位置付けもわかります。
自分自身の組織内での役割を知ることは、モチベーションに影響します。
ほとんどの人は、組織の役に立ちたいと思っているものです。
改善意欲・改革意欲を生み出す土台になります。
次の業務改善・業務改革につながる
標準化は、作成した時点で 最新のものです。
明日になれば、もう最新ではありません。
実際に業務を行っていれば、効率化のアイデアも出てきます。
また、環境の変化があれば 当然業務も変わります。
いわゆる改善・改革が発生します。
標準化の1番の意義は、次の業務改善・業務改革を起こすことです。
改善・改革は、ベースラインを変えることですよね。
ベースライン=標準化です。
また、標準化は 今まで行ってきた改善・暗黙知を 一旦 見える化することでもあります。
改訂した時点で、最も効率の良い業務プロセスということですね。
そして、ベースラインがあれば 組織の状態もわかります。
例えば、5年も同じ業務プロセスを実施していれば、明らかに異常ですよね。
改善が常に起こっている組織を作ることは、マネジメントの重要な要素です。
効率的・効果的に実施するための適用範囲の考え方
とはいっても、全ての業務を標準化するのは 時間・コストがかかりますよね。
場合によれば、改善・改革の効果以上に コストがかかるかもしれません。
上記に示した「標準化の3つの意義」を踏まえて、適用する範囲を決めましょう。
意義で紹介した3つのポイントを最低限網羅するのは、基幹系業務です。
最低限、各組織の基幹系業務は標準化すべきです。
基幹系業務というのは、各組織の機能単位で成り立っている業務です。
つまり、各組織の最終成果物に直結するものです。
例えば製品の提供であれば、機能単位には企画・設計・評価・販売がありますよね。
そして、各機能単位は ほぼ組織のメンバーが関わっています。
これであれば、成果物の品質を担保する必要性もあり、組織の中の自分自身の位置付けもわかりますよね。
また、業務改善・業務改革の多くは この基幹系業務に関わっています。
改善・改革の効果が大きいからです。
さらに余力があるのならば、枝葉にあたる各組織・各機能の主業務について標準化します。
業務フローの階層で言えば、基幹系業務のひとつ下の階層(レベル4)に当たります。
改訂のタイミング
個々の業務改善毎に改定していたのでは、時間・コストがかかります。
適切なタイミングとして、以下3つ紹介します。
- 前後工程含めた改善・改革があった場合
- 法律改定や問題が発生し織り込むことが必須な場合
- 定期的な改訂
個々の業務ではなく前後工程含めた改善・改革があった場合
人は、自分の担当業務は改善していきます。
少しでも効率的にやりたいからです。
なので、個々の業務の方が暗黙知が溜まっていきます。
とはいえ、小改善の都度改訂を行うことは、ひとりの担当者だけに負荷を与えることになります。
また、小改善では費用対効果も ほとんどありません。
改訂のタイミングは、前後工程を含めた括りになる業務単位で改善・改革があった時がベストです。
複数人で実施ができ、負荷分散できます。
また、この単位であれば、費用対効果はあるはずです。
例えば先ほどの例で言えば、企画と開発業務のやり方が変わったという単位です。
法律改定やトラブルが発生し織り込むことが必須な場合
経営にインパクトを与えますよね。
絶対に改定しなければならないタイミングです。
定期的な改訂
定期的な見直し期間を定め、時期がきたら そのまま継続か改訂かを判断することです。
必要であれば、改訂します。
必ず 見直し時期がきたら 判断が発生しますので、鮮度は確保されますよね。
私が在職した大会社は、この方法を取っています。
ただ、この方法は「改訂を管理する」という間接業務が発生しますよね。
大きな会社でないと難しいと思いますが、システム化という手もあります。
文書管理のシステムであれば、古い日付順に並べることは簡単ですよね。
そして、5年も同じ業務が続くということはあり得ないと思います。
5年をスパンとして管理することも効率的・効果的な方法です。
まとめ
業務の標準化は、役割分担・業務プロセスを 見える化します。
今回は「標準化の意義と効率的・効果的に実施するための業務の適用範囲・改訂のタイミング」について紹介しました。
標準化の1番の意義は、次の改善・改革を起こすことです。
また、今まで行ってきた改善・暗黙知を、一旦 見える化することでもあります。
そして、皆と共有し 次の改善のベースラインにします。
改善が常に起こっている組織を作ることは、マネジメントの重要な要素ですよね。
さて、今回は「業務標準化の適用範囲・改訂のタイミング」について紹介しましたが、「業務標準をいかに作成するか」も重要ですよね。
以下の記事では「業務標準のわかりやすい作成方法」について記載していますので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。
関連投稿記事:たった3つのコツで変わる!わかりやすい業務標準の作成方法