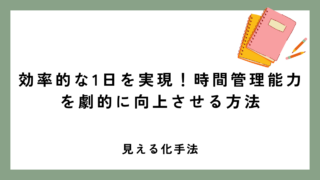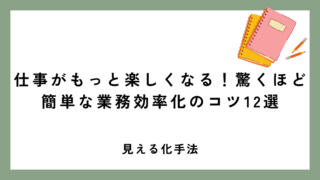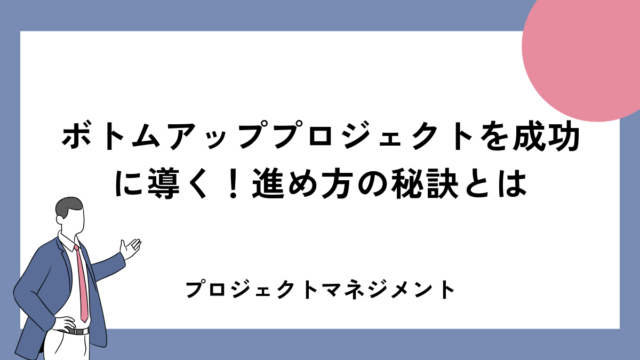たった3つのコツで変わる!わかりやすい業務標準の作成方法

(2025/4/27 更新しました)
「うちの会社の業務標準わかりにくいな」
「結局誰かに聞かないとわからないじゃん」
せっかく時間をかけた業務標準も、これではムダですよね。
実は、ちょっと工夫するだけで わかりやすくする方法があります。
それは、「業務フロー図」と「5W1Hフレームワーク」を利用することです。
私自身は「業務の標準化といえば・・・」が代名詞になる大企業の元社員です。
当然、何度も業務標準を作成していますし、多くの業務標準も見ています。
今回は、私の経験から 「わかりやすい業務標準を作成するための3つのコツ」ついて紹介します。
業務標準の目的とは:業務改善・改革のベースライン
業務標準を作成する目的は、以下2つです。
- 効率的な業務品質を維持するため
- 早く戦力となってもらうため
- 業務改善・改革のベースラインとするため
特に、③は重要です。
まずは、業務標準は「今まで行ってきた改善・暗黙知を 一旦見える化する」ために行います。
そして、業務標準は「組織内で共有し 次の改善を促すために策定する」ものです。
要は、業務改善・改革のサイクルを「組織に浸透させるため」に実施するものなのです。
また、今や5年も同じ業務をし続けることはないと思います。
実際には実施されていない業務標準を放置したままで実務者任せでは、業務改善・改革も浸透することはありません。
業務標準の目的である「業務品質の維持」も、これではバラツキますよね。
一方で、業務標準は文書であり、読むことによって 目的を果たします。
ならば、皆がわかりやすい文書を 作成する必要がありますよね。
でも、私の経験上「読んでもわからない業務標準」 結構あるのです。
まずは、「なぜわかりにくいのか」から説明したいと思います。
わからない業務標準の特徴
私の経験から、わからない業務標準の特徴は 以下3つです。
あなたの会社の業務標準と比べてみてください。
- 前後のつながりがわからない
- 目的がわからない
- 成果物がイメージできない
以下 順番に説明します。
前後のつながりがわからない
業務標準、文章で書きます。
通常①②と数字で順番つけて、策定しますよね。
なので、実施時期の前後関係はわかります。
でも、実際の業務では 並行して行うことが多くありますよね。
③の業務の前工程は、①の場合もあります。
この関係がわからない業務標準 意外と多いのです。
唐突に記載されている業務は、自分自身でつなぐ必要があります。
知らない、あるいは 初めての業務では、理解するのは 難しいのです。
目的がわからない
業務標準は通常、簡潔に文書化します。
であれば、5W1H は基本のフレームワークですよね。
では、Why(目的)を記載していますか?
実は、手順が記載されているだけの業務標準になっていることが多いのです。
何のためにやらないといけないのか、成果物の質にも影響します。
それと、目的がわからなければ その業務の存在意義もわかりません。
作成した当初は分かっていても、引継ぎの繰り返しにより いずれ目的がわからなくなります。
「業務改革で必要な業務を廃止してしまい大騒ぎ」という事例も 結構見てきています。
成果物がイメージできない
成果物を文章で書くと、項目の羅列になりますよね。
多くは、最低限やることを記載することになりますよね。
項目の羅列だけでは、中身がイメージできません。
結局、過去の事例を探すというムダな時間を使うことになります。
業務標準をわかりやすくするポイント
業務標準を「わかりやすくするポイント」を 3つ紹介します。
これだけで、大きく変わると思います。
- 業務フロー図を作成・添付する
- 業務フロー図に沿って、文書化する
- 成果物の実例を添付する
業務フロー図を作成・添付する
業務は、フローです。
先ずは、業務フロー図を作成しましょう。
業務フローを作成することにより、IN・処理・OUTの関係が明確になります。
前後工程の関係がわかり、成果物が後工程でどう処理されるか 理解することができます。
業務フロー図に沿って 文書化する
明確になったIN・処理・OUTの関係を 文書化します。
いつ・○○を受けて・○○を活用して○○書類を作成し・○○の手段で○○に送付する
業務フロー図から、ここまでは書けますよね。
あなたの会社の業務標準は以下になっていませんか?
いつ・○○書類を作成し・○○に送付する
これだけで全然違うことが実感できると思います。
あとは、これに目的を追加します。
○○のために・いつ・○○を受けて・○○を活用して○○書類を作成し・○○の手段で○○に送付する
これで、文書化は 完成です。
業務フロー図を見ながら読めば、格段にわかりやすくなったと思います。
成果物の実例を添付する
業務標準、普通は機密文書です。
ノウハウの塊ですので、関係者以外はアクセスできないですよね。
実際に過去に実施した優秀事例を、成果物として添付します。
全ての業務を対象にすると、時間・コストがかかります。
本当に重要な成果物だけでも十分です。
どうしても機密上の問題があれば、その部分は消すか、イメージがわかる言葉に修正すれば良いです。
あくまで、成果物のイメージが見ただけで理解できるようにすることです。
以上に挙げた3つを実施するだけで、業務標準は圧倒的にわかりやすくなります。
読む側の視点で見ると、業務フロー図を見ながら 個々の業務の文章を読むことができるからです。
○○のために・いつ・○○を受けて・○○を活用して○○書類を作成し・○○の手段で○○に送付する
そして、添付した成果物で「なるほど。こういうものか」と 理解できます。
また、最後まで読めば業務全体が理解できますし、自分自身の役割も理解することができますよね。
まとめ
今回は、私の経験から 「わかりやすい業務標準を作成するための3つのコツ」ついて 紹介しました。
業務の標準化は、業務品質の確保になります。
そして、業務の見える化でもあり 業務改善・業務改革のベースラインでもあります。
ならば、皆がわかりやすい業務標準を作成することが重要だとは思いませんか?
さて、今回は「わかりやすい業務標準の作成方法」について記載しましたが、「業務のどこまで適用するか」「いつ改定するか」も 大切ですよね。
以下の記事で紹介していますので、ぜひ併せて読んでみてください。
投稿記事:業務標準化の目的と効率的な適用範囲・改訂のタイミングとは
また、「業務フローの書き方」については 以下の記事が参考になると思います。
投稿記事:業務フロー作成の劇的効率化!知らないと損する成功のコツ