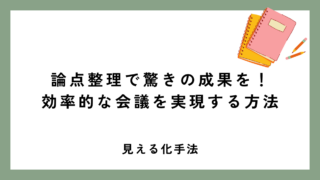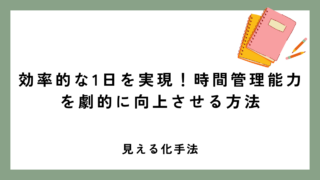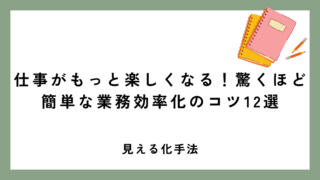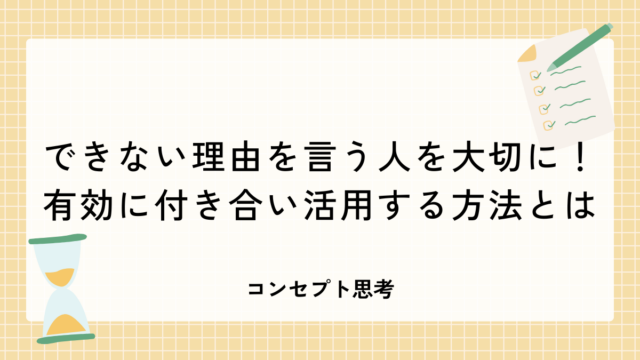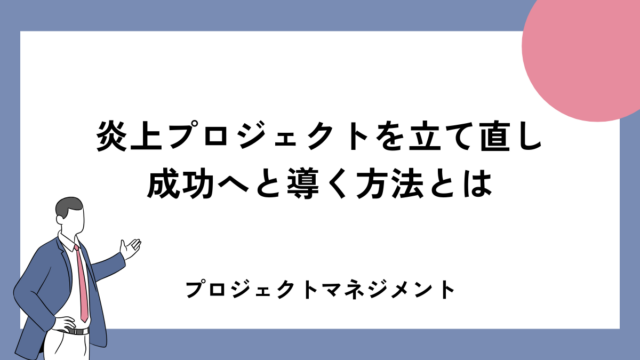業務改革で生産性UP!初心者でもわかる6つの簡単ステップ
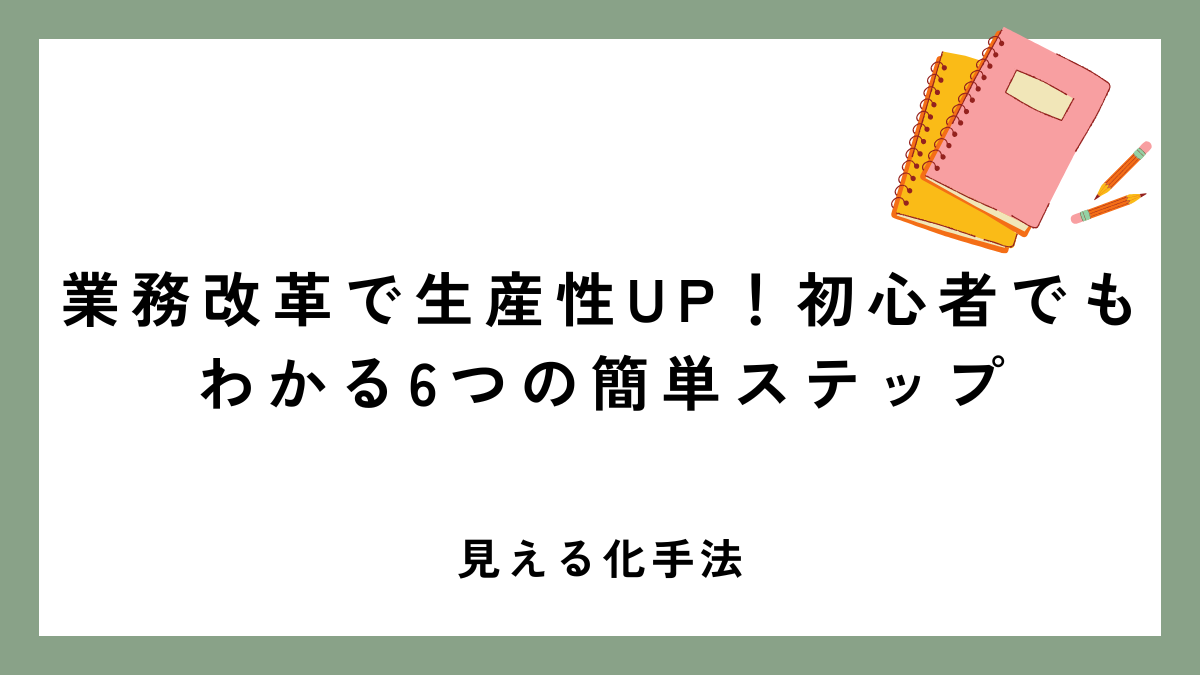
あなたのビジネスでは、業務改革を実施していますか?
業務改革は、抜本的に業務の変化を目指す取り組みです。
ビジネスは、業務プロセスの集まりで成り立っています。
であれば、競争力の源泉とも言えますよね。
今回は、初心者向けに「業務改革で抜本的に生産性を向上するための6ステップ」について紹介します。
私は、25年以上 BPRプロジェクトのリーダーを経験しています。
半減なんて普通です。
その実績に基づいています。
業務改革とは?その重要性と目的

業務改革の定義と業務改善との違い
業務改革とは、企業が利益を上げるために、業務プロセスや組織を抜本的に再設計し、大きな変化を目指す取り組みを指します。
1990年代にアメリカの学者によって提唱された「ビジネス・プロセス・リエンジニアリング(BPR)」は有名ですよね。
BPRはゼロベースでの再構築を指しますが、業務改革は抜本的に大きな変化をもたらすという点で、私自身は もう少し広い概念だと考えています。
一方で、業務改善は現状を維持しつつ、業務プロセスや作業内容を効率化することで問題の解決を図る手法です。
また、業務改革は ある程度広いスコープでプロセスの再構築を行うのに対し、業務改善は比較的狭いスコープでの微調整を中心としています。
業務改革が必要とされる背景
近年、業務改革が求められる背景には、急激な市場変化や競争激化、さらにはテクノロジーの進展などがあります。
例えば、デジタル技術の進歩により、業務プロセスの効率化や生産性向上が身近なものになりました。
また、コロナ禍を契機にリモートワークの導入が進み、従来の業務フローや組織体制では対応できない新たな課題も浮き彫りになりました。
こうした環境の変化に柔軟に対応し、ビジネスの競争力を維持するためには、業務プロセスの抜本的な見直しが必要不可欠ですよね。
そもそも5年も業務プロセスが変わらなければ、ビジネスの存続も危ういでしょう。
業務改革を成功させるメリット
業務改革が成功した際には、さまざまなメリットを得ることができます。
たとえば、効率化によって労働時間が削減され、余剰リソースを高付加価値業務に割り当てられるようになります。
同時に、効率的な業務フローは作業ミスの削減につながり、品質向上も期待できますよね。
また、顧客満足度の向上も大きな利点の一つです。
迅速かつ正確な対応ができるプロセスへと変えることによって余裕が生まれ、顧客との信頼関係を強化する活動へシフトすることができます。
さらに、従業員のモチベーション向上も重要な成功要因です。
ムダな作業の削減や働きやすい環境の実現は、従業員の満足度向上につながります。
これらの効果が相互に作用し、企業の競争力が大幅に強化されるのです。
業務改革に取り組む際の注意点
業務改革を進める際には、いくつかの注意点があります。
まず重要なのは、「ビジョンの共有」です。
経営陣や従業員が業務改革の意義を正しく理解し、目的や目標を共有することで、高いモチベーションで進めることができます。
次に、「ゼロベースからの発想」を持つことも大切です。
従来の方法にとらわれず、柔軟な思考と新たな視点を取り入れることで、より抜本的な解決策を見つけることができます。
一方で、「小さく始めること」も重要です。
大規模な変更を一度に全て行おうとすると現場に混乱を招く可能性が高いため、まずは小規模なプロジェクトから始め、徐々に全体へ波及させていく進め方が効果的です。
基本的には、アジャイルで進めていくことです。
最後に、「現場を巻き込むこと」も欠かせません。
業務改革では、実際に業務を行う従業員の協力が絶対に必要ですよね。
現場を巻き込み、改革の進め方や具体的なプロセスを共有することで、スムーズな導入が可能となります。
業務改革のステップ:成功への道筋
1. 現状把握と業務プロセスの可視化
業務改革を成功させるための第一歩は、現状の業務プロセスを詳細に把握し、それを見える化することです。
このステップでは、各業務フローがどのように進められ、どこにムリ・ムダ・ムラが存在するのかを認識することが重要です。
具体的には、実務者から日々の業務内容をヒアリングし、業務フローを描きます。
そして、どこに課題があるかを明らかにしていきます。
このステップでは、漏れなく情報を洗い出し・整理することが大切です。
この段階に漏れがあると、実行段階で予期せぬ問題が発生する可能性が高まります。
2. 課題の抽出と分析
次に行うのが、可視化された業務プロセスから具体的な課題を抽出し、それを分析するステップです。
課題には、重複作業、手待ち作業、今では必要のない作業、情報共有ミスなど、さまざまな種類があります。
これらを洗い出し、業務改革の目的に応じて優先順位を明確にしていきます。
課題分析では、単なる現象の指摘にとどまらず、その原因を深掘りすることが求められます。
「なぜなぜ」を繰り返しましょう。
具体的には、課題は「課題リスト」で整理しますよね。
課題を大分類・中分類・小分類にまとめたり、課題間の関係(上下関係・因果関係)を整理したりして、真の原因を特定して優先順位を付けていきます。
3. 解決策・改革計画の策定
課題が明確になったら、それに基づく解決策を検討します。
解決策は、過去のしがらみに捉われることなく「ゼロベース」で考えることです。
「ビジョンを達成するためにはどうあるべきか」で考えることにより、「ゼロベース」のアイデアは出てきます。
例えば、開発期間を抜本的に短縮したいとします。
このケースならば、デザインと設計が同時作業するしかないですよね。
ならば、デザインの概要を元に最初の設計を開始、その後 部位ごとに詳細化していくプロセスが考えられますよね。
4. 改革計画の策定
解決策が決まったら、改革計画の策定をします。
この計画では、具体的な目標や実施内容、スケジュールを詳細に設定することが重要です。
計画策定時には、業務改革の進め方のコツである「小さく始める」を意識し、少しずつ現場に落とし込む改革案を設計すると成功率が高まります。
また、この段階で関係部署や実務者との十分な合意形成を図り、計画がスムーズに実行できるよう準備を整えることです。
できれば、解決策を検討する際に、一緒に考えるのがベストです。
5. 実行と進捗管理
策定した改善計画を具体的に実行に移します。
この際、段取り通りに進めることは当然として、業務プロセス改革では予期せぬ課題が発生することもよくあります。
特に、人間だから柔軟に対処しているようなイレギュラー業務 必ずありますよね。
そのため、進捗状況を常にチェックし、必要であれば軌道修正を行う柔軟さが求められます。
また、従業員の協力を得るためには、適切なコミュニケーションを行い、改革の目的や必要性を再認識することが必要です。
要は、ビジョンを共有しつつ、問題があれば即時対応することですね。
信頼を得ることは、改革を実現するための重要なポイントです。
6. 効果測定と継続的改善
最後に、実行した業務改革の成果を測定し、さらに改善を進めるステップです。
どの程度の効果が得られたのか定量的な数値で把握し、成功要因や改善すべき点を分析します。
また、一度の改革で終わりにせず、継続的にプロセスを見直し、時代や環境の変化に合わせて改善を進めることも重要です。
これにより、業務改革が組織のDNAとして定着していきます。
まとめ
今回は、初心者向けに「業務改革で抜本的に生産性を向上するための6ステップ」について紹介しました。
業務改革プロジェクトが常に動いている組織って、私の経験上 やはり強いです。
業務改革で抜本的な変化を起こしましょう。
さて、今回は「初心者向けの業務改革の進め方」について紹介しましたが、以下の記事では「抜本的な業務改革の方法」について紹介しています。
こちらもぜひ併せて読んでみてください。
投稿記事:効率化目標は1/2!既存プロセスの抜本的再構築のコツ