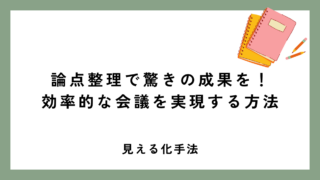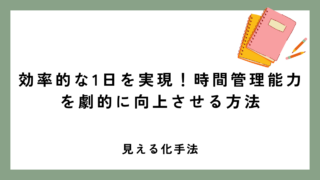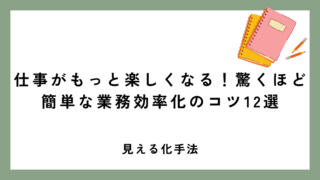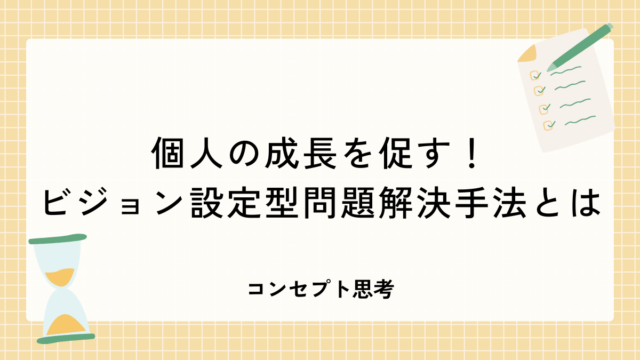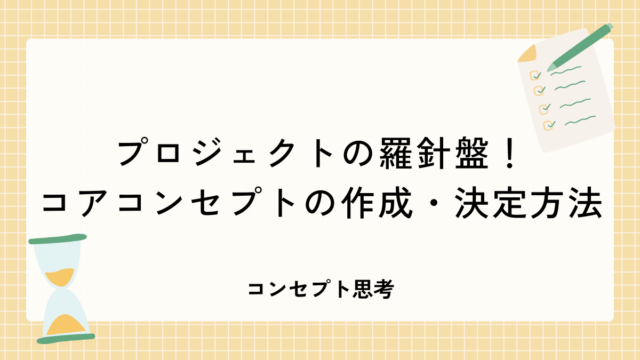複雑な問題を解決に導く!体系的・構造的に捉える方法とは
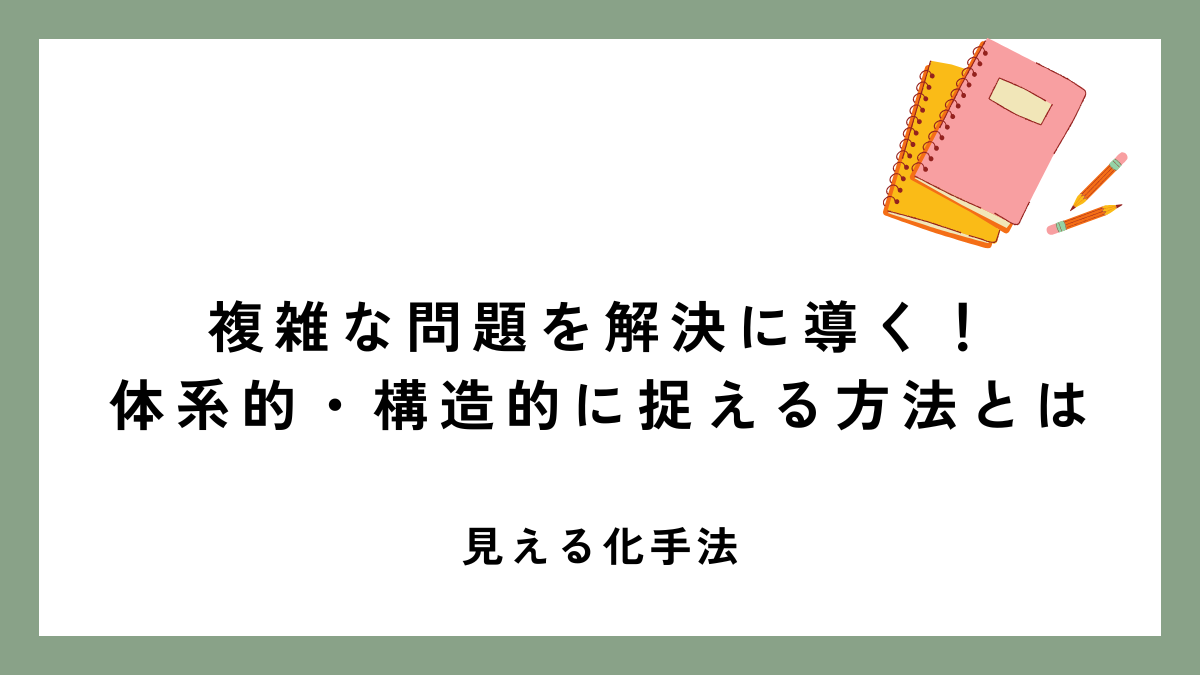
(2025/2/15 更新しました)
あなたの解決する問題、複雑になってきていませんか?
年々 実感していると思います。
理由は、シンプル。
単独な問題は、すでに解決済みになっているからです。
残っている問題は、いくつもの要因が複雑に絡み合っています。
複雑な問題に対応するには、体系的・構造的に ものごとを捉えることが必要です。
紐解いていかなければ、的確な解決策には たどり着けないからです。
今回は、私の経験から「ビジネスを体系的・構造的に捉える方法」について 紹介したいと思います。
私自身は、大企業で20年以上プロジェクトリーダーをしていました。
本質を見極めなければ、プロジェクトに成果は出ません。
その経験に基づいています。
目次
体系的・構造的に捉えることが必要である理由
まずは簡単に、体系的・構造的に捉えることの必要性について 説明します。
効率化・生産性向上!
これまでビジネスの現場で 実践・改善され続けてきました。
冒頭で触れたように、単独で存在した問題は ほぼ解決されていると思います。
いま残っている問題は、複雑に要因が絡み合っているものです。
ひとつの問題だけに注目すると、必ず他に影響を与えます。
一方で、業務は 細分化されています。
50代以降の方はご存知だと思いますが、昔は ひとりの業務範囲 とても広かったです。
私自身で言えば、最初に配属されたのは生産技術部門で 工場単位で分担が分かれていました。
工場単位ということは、担当工場で生産される車種の生産準備からライン設計まで 全ての業務を担当するということです。
生産車種の特徴がわかっているので、ライン設計にも反映させることができます。
逆に、何が問題かも ひとりで判断・解決できます。
でも今は 業務は細分化されていますよね。
生産準備とライン設計の分担が別になれば、お互いの連携が必要です。
ラインの特性に合わせて 生産準備もしなければなりません。
問題解決も ひとりではできないのです。
枝を見て森を見ないという現象は、細分化された組織では普通に起きます。
一方で、森を見て 枝がわからないという現象も起きます。
マネジメント層から見ると、細分化されすぎて何をやっているのかわからないこと 多いと思います。
これでは、複雑な要因を 紐解くことはできないのです。
そこで、体系的・構造的に捉える必要性があります。
要は、森も木も見る必要があるのです。
体系的・構造的に捉えることとは
体系化は、ものごとの関係を把握することです。
部品であれば、さらに細かいパーツがあって構成されています。
各パーツ毎に 役割がありますよね。
また、相互依存もあります。
体系化は、各パーツの役割・依存関係のように ビジネスの関係を見える化することです。
また、構造化は ものごとをブロック化することです。
部品であれば ひとつのパッケージの中に、各パーツが組み込まれています。
パッケージがインフラであり、人と接する部分があれば ユーザーインターフェースです。
構造化は、各パーツの機能のように ビジネスの成り立ちを見える化することです。
体系的・構造的に捉える方法

私自身は、30代の頃 システムの基本設計をした経験があります。
システム = 体系ですよね。
当時オブジェクト指向という概念が、システム設計手法として脚光を浴びていた頃です。
私は、概念データモデルという手法で 体系・構造を把握しています。
概念データモデルは、情報間の関係を把握する方法です。
要は、業務フローを 情報を中心にしてモデル化したものです。
現在のビジネスは、情報を中心に回っています。
そして、情報は 大切な資産です。
資産に注目するので、普通よりも早く捉えることができるのです。
とはいっても、オブジェクト指向を学ぶのは 簡単ではありません。
なので、概念データモデルは使わずに実施できる方法を 説明したいと思います。
今回は、私が実践している3つのステップを紹介したいと思います。
- キーワードを書き出し、関係を考える
- ①で考えたキーワード間の関係を広げていく
- いろいろな視点で見つめ、ヒラメキを得る
以下 順番に紹介します。
キーワードを書き出し、関係を考える
自部署でよく使われているキーワードを洗い出します。
キーワードの多くは、ある情報・データの集合体になっていると思います。
それを元に、キーワード間の関係を考えます。
そして、上位・下位関係・どうつながっているかで整理していきます。
例えば、「部品」「図面」というキーワードがあるとします。
部品に対して図面がひとつであれば、「部品」=「図面」です。
つまり、1対1の関係です。
完全に相互依存の関係ですよね。
部品に対して 異なる種類の図面があれば、1対多の関係です。
部品と図面には相互依存はありますが、図面間には必ずしも依存関係はあるとは言えないということです。
上下関係は、部品製造がメインならば 「部品」だと思います。
設計会社であれば、「図面」の方が上位かもしれません。
①で考えたキーワード間の関係を広げていく
キーワード間の関係を どんどん広げていきます。
例えば、先ほどの例に「試作品」をつなぐとします。
通常は、ある設計時点の図面に対して 試作品は出来上がります。
であれば、図面と試作品は 図面の履歴で結ばれます。
図面のバージョンと試作品は、紐付けしないと管理できないですよね。
つまり、バージョン管理というキーワードが出てくるわけです。
こうした関係を どんどんつなげていきます。
いろいろな視点で見つめ、ヒラメキを得る
つなげたキーワードは、既に体系に なっています。
当たり前ですよね。
関係に注目して つないでいるのですから。
さて、次に問題を体系図にマッピングします。
体系のつながりを見れば、問題がどこまで影響するかがわかります。
この影響範囲が、相互依存している範囲になります。
要は、解決すべき範囲ということです。
ただ、これだけだと 枝を見える化したに過ぎません。
ここから、森にする必要があります。
森にする方法ですが、ほとんどヒラメキに近いものがあります。
私自身も、最後はヒラメキです。
突然 空から降ってくるという感じです。
と言っては身も蓋もないので、そのためにどういう作業をしているかを 以下記載します。
ちなみに、空から降ってくる時は コンセプトやアイデアも同時に降りてきます。
「こういうことかあ」と思うことと「こうすれば良いかな」と思うことが 同じ瞬間であることって、意外と多いですよね。
- つなげたキーワードをいろいろな視点で大きく括る
- 括ったものに名前をつけ、ひたすら書いて さらに関係を探る
- 煮詰まってきたら 放っておいて、降ってくるのを待つ
- 誰かに説明してみる
つなげたキーワードをいろいろな視点で大きく括る
キーワードをいくつかまとめて、大きく括ってみます。
自部署のミッション・ビジョン・お客様(後工程)視点・自部署都合視点など、視点を変えて 括ることを実施します。
特に、自部署都合視点でくくること オススメします。
効率化・生産性を意識している組織ほど、意外と 自部署都合って多いものです。
また、大きく3つに分類・整理するのも 有効です。
人間の脳って、3つぐらいしか理解できないということに関係しています。
上流・自部署・下流とか インフラ・手続き・各機能とか3階建てでシンプルに考えると、早く気づくこともあります。
括ったものに名前をつけ、ひたすら書いて さらに関係を探る
括ったグループに名前をつけ、それらを ひたすら書きます。
つけた名前どうしをくっつけたり離したり、基本アイデアを出すのと同じ方法です。
私の場合は、先ずは 紙になぐり書きしています。
ある程度整理できてきたら ホワイトボードを使っています。
実際に言葉にして書くことが重要です。
頭の中だけではなく、視覚も利用するのです。
そして、言葉には意味があります。
意味から刺激を受け、インスピレーションが生まれること とても多いのです。
煮詰まってきたら 放っておいて、降ってくるのを待つ
多くのケースでは、すぐには見えてきません。
これもアイデア出しと同じです。
煮詰まってきたら、いったん放り出しましょう。
頭の片隅には、必ず入っています。
ある時 突然降ってきます。
人それぞれ、アイデアが出やすい空間・場を持っていると思います。
私の場合は、帰宅途中のクルマの中。
急に、閃くんですよね。
その空間・場に浸りましょう。
誰かに説明してみる
ある程度まで ひとりで考えたら、他の人に説明してみるのも良いです。
説明している最中に、急に気づくこともあります。
また、相手の発言で 思いつくこともあります。
場合によれば、一緒に作り上げる機会になることもあります。
やる時は、ホワイトボードが最も適しています。
修正しながら、書き上げていきましょう。
まとめ
現在のビジネスでは、単独ではなく いくつもの問題が複雑に絡み合っています。
複雑な問題に対応するには、体系的・構造的に ものごとを捉えることが必要です。
今回は、私の経験から ビジネスを体系的・構造的に捉える方法について紹介しました。
木も森も見る 3つのステップです。
- キーワードを書き出し、関係を考える
- ①で考えたキーワード間の関係を広げていく
- いろいろな視点で見つめ、ヒラメキを得る
そして、最終的に森を見つけるためのステップも紹介しました。
- つなげたキーワードをいろいろな視点で大きく括る
- 括ったものに名前をつけ、ひたすら書いて さらに関係を探る
- 煮詰まってきたら 放っておいて、降ってくるのを待つ
- 誰かに説明してみる
ビジネスを体系的・構造的に捉えることができれば、絡み合う問題を紐解くことができます。
そして、相互に関係する問題を解決する方法を 見つけることが可能です。