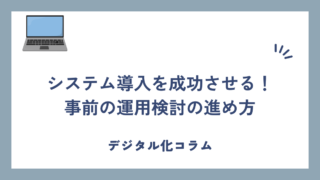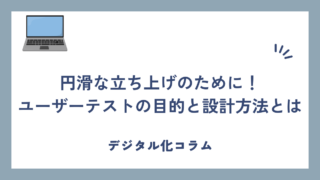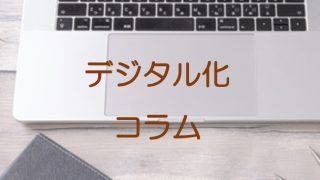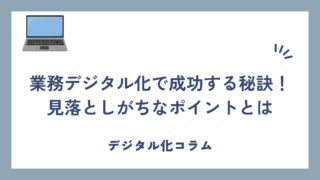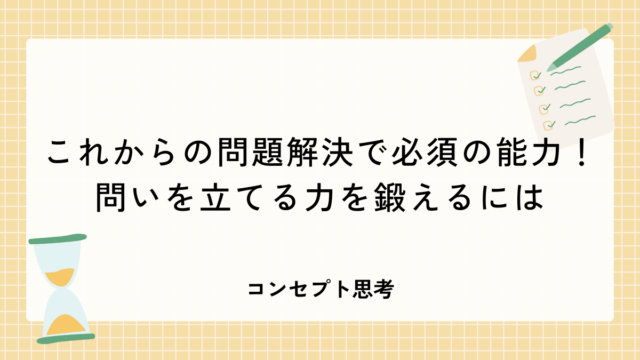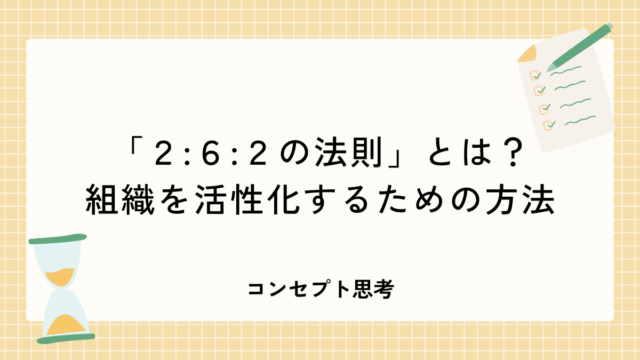システム導入の費用対効果:説得力がアップする算出方法とは
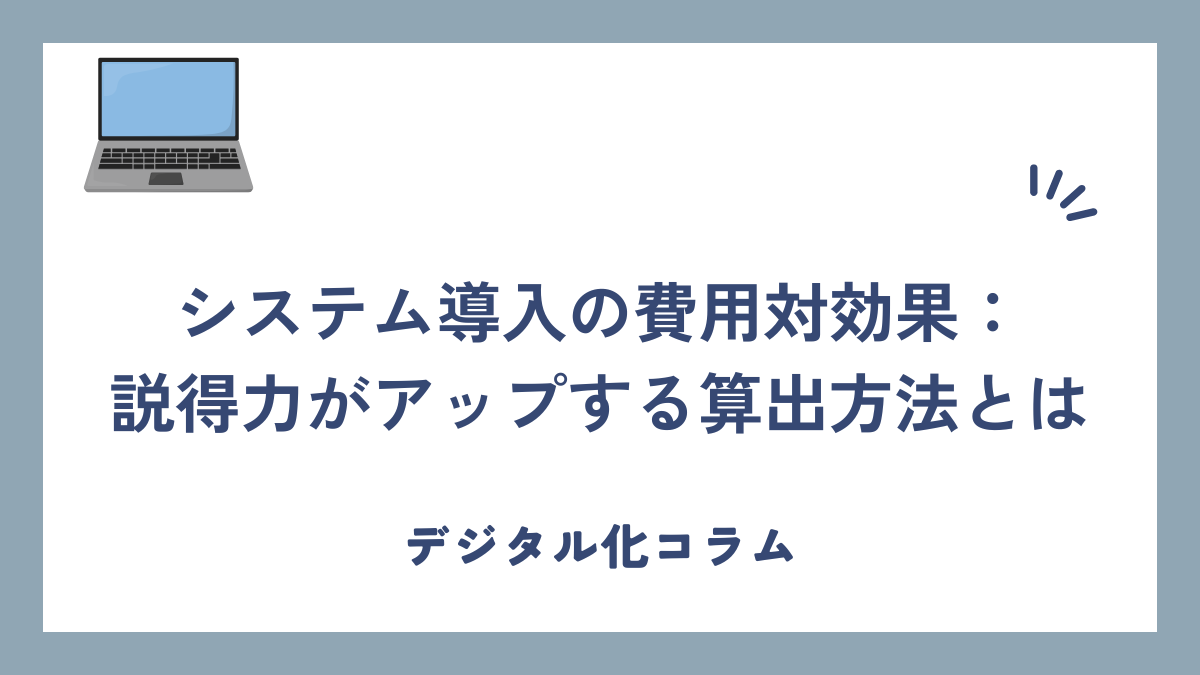
(2025/4/10 更新しました)
システム開発・導入の前に、決裁を受けますよね。
そして、決裁の判断材料として「費用対効果」を記載していますよね。
その際、「工数低減」を メインで記載していませんか?
私自身は、「工数低減」では決裁資料として説得力・インパクトはないと考えています。
なぜなら、システム導入の本当の目的ではないからです。
今回は、システム化プロジェクトの費用対効果について「説得力を向上させるための効果予測の立て方」について紹介します。
私は、システム化プロジェクトを立ち上げ、何度も決裁を受けてきた経験があります。
その実績に基づいています。
費用対効果の基本的な考え方

費用対効果とは何か?
費用対効果とは、システム導入に伴うコストと、それによって得られる効果を比較し、その価値を見極める考え方です。
具体的には、投入した費用に対して どれだけの利益や効率化を得られるかを測定するものです。
たとえば、1000万円をかけたシステム導入で業務効率化によって2000万円/年の価値が生まれた場合、費用は1年で回収できたと評価できます。
このように、システム導入の成果を定量的に把握することが可能になり、適切な投資判断をサポートします。
システム導入時に費用対効果が重要な理由
システム導入時に費用対効果が重要な理由は、限られた予算やリソースを適切に活用し、最大限の投資効率を図るためです。
特に、企業の競争力を高めるためには、業務効率化やコスト削減、新しいビジネスチャンスの創出が欠かせないですよね。
費用対効果をしっかりと分析することで、システム導入が実際にどの程度利益を生むのか、あるいはどのようなコスト削減が見込めるのかを具体的に理解できます。
その結果、投資に対する適切な判断を下すことができます。
実際には、それぞれの企業において投資判断の基準がありますよね。
私が在籍していた会社の場合、費用の2年回収がひとつの基準となっていました。
費用(コスト)と効果の内訳の理解
費用(コスト)と効果を細分化して理解することは、費用対効果を正しく算出するための前提条件です。
システム導入における費用には、初期費用(開発費や設定費用)、運用コスト(ランニングコスト)などが含まれます。
一方、効果には、定量的な効果と定性的な効果があります。
定量的な効果とは、コスト削減や売上増加、業務時間の短縮など、具体的に数字で表せるものです。
これに対し、定性的な効果は、ブランド価値の向上や従業員の付加価値業務への移行など、数値化が難しいものを指します。
これらを総合的に分析し、適切な費用対効果の算出方法を確立することが成功の鍵となります。
とは言っても、費用対効果算出では数字がメインになるため、定性的効果を織り込むことは難しいですよね。
特に予算稟議の場合には、定量的な効果で示さなければ判断が難しいことがあります。
効果的な費用対効果の計算方法
システム化の効果は工数低減?
システム化の効果として、よく使われるのは 工数低減です。
システムは、人の作業を置き換えるものと考えれば、こうした発想になります。
でも、本当に そうでしょうか?
笑い話のような話しをします。
私が在籍していたような大会社でも、システム化の効果を工数低減にしていた時期があります。
20年も経てば 従業員ゼロになるような累積計算になっていました。
でも、従業員は 今も普通にいます。
つまり、システム化は 人の作業の置き換えではないのです。
そもそも、システムを導入する目的は何か考えてみましょう。
例えば、新たな法規制に対応するため人員を当てる必要があるのだが、その工数がない。
新たなビジョン・戦略を実現するために人員を当てる必要があるのだが、その工数がない。
こういう目的の方が 多くありませんか?
確かに 「工数確保」だけで考えれば、工数削減かもしれません。
でも、本来の目的は 違いますよね。
私自身は、 システム化の効果は 効率でなく 価値向上だと考えています。
システム化プロジェクトの本来の目的も 価値の向上ではないでしょうか?
工数低減を費用対効果で考えると
システム開発・導入の費用対効果の判断基準は、各企業で決まっていますよね。
例えば、私が在籍していた会社の基準「2年回収」で考えてみます。
1億円の投資の場合、1年で0.5億の効果必要です。
労務費5,000/Hrとすると、年間10,000時間の削減効果が必要です。
50人の社員がいれば、ひとり200時間ですよね。
よほどの社員がいる大会社でない限り、工数低減で効果をあげるのは無理ですよね。
低減できる工数を、チマチマ積み上げるのは 得策とは思えません。
また、激動のビジネス環境です。
今どき 工数低減が目的では、説得力に欠けるのではないでしょうか。
効果的な効果予測の立て方
システム導入プロジェクトの本来の目的から、効果を算出します。
先ほどの例でいえば、「新たな法規制に対応するため」「新たなビジョン・戦略のため」です。
そして、3つの視点から 効果を見積もります。
- 新たな脅威・機会そのものの効果
- 目的を実現するために必要な工数・コスト
- 現行業務を低減する工数・コスト
以下 順番に紹介します。
新たな脅威・機会そのものの効果
そもそものシステム開発・導入の目的に立ち返って考えます。
システム開発・導入の構想ストーリーは、起案前のプロジェクト構想で 既に出来上がっていますよね。
この構想ストーリーから 効果算出します。
例えば、新たな法規制であれば、問題が発生すれば多大な被害を受けますよね。
こうした場合に使うのは、いわゆる「リスク評価」です。
被る被害*発生する確率です。
また、新たなビジョン・戦略の場合では、実際に戦術を実行した場合の効果です。
どれぐらいの利益が見込まれるでしょうか。
但し、夢物語のような数字では 説得力ないので、論理的に正しいと思われる数字を使うことです。
新たなことを実施するので、当然どうなるのかはわかりません。
でも、構想ストーリーに説得力があれば、目標は 論理的に説明できるはずです。
目的を実現するために必要な工数
新たな脅威・機会に立ち向かうための工数を見積もります。
例えば、新たな法規制であれば、絶対に対応しないといけません。
今手作業でやるとしたら、どれぐらいの工数になるでしょうか?
新たなビジョン・戦略の場合、戦術にどの程度の工数が必要でしょうか?
それを算出しましょう。
そして、これら工数は「工数増加の抑止効果」として訴求することになります。
「何もツールがない状況で実施すれば、これだけの工数がかかる。それを、○○程度の工数増ぐらいに抑えたい。」
訴求のポイントですね。
現行業務を低減する工数・コスト
最後に、システムを適用する範囲の現行業務の低減効果を算出します。
新しいシステムの導入には、業務プロセスの見直しと最適化は欠かせませんよね。
これらの効果を、積み上げで算出します。
まとめ
今回は、システム化プロジェクトの費用対効果について「説得力を向上させるための効果予測の立て方」について紹介しました。
私自身が、実際に活用してきた方法です。
そして、決裁用資料には 目的と効果を訴求するストーリーで作成しましょう。
説得力は、随分変わると思います。
今回はシステム開発・導入をトピックにしましたが、全ての決裁資料でも同じことだと思います。
決裁は、今後のビジネスの方向を決める重要な場です。
決裁する側・決裁される側が、同じ土台で議論することが大切ですよね。
目的・実施事項・効果があって初めて 共通の土台ができるのだと思います。
さて、今回の記事の中で 費用対効果の元になる「構想ストーリー」について触れました。
以下の記事では「構想企画の進め方」について記載していますので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。