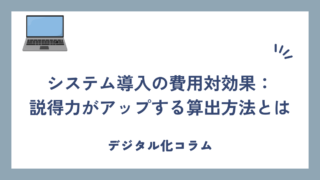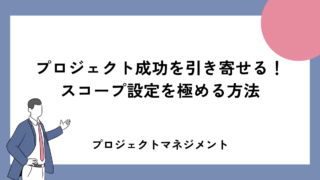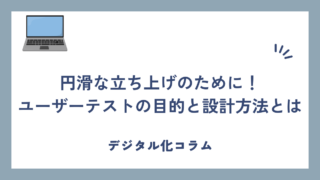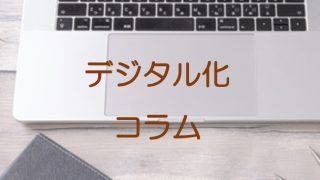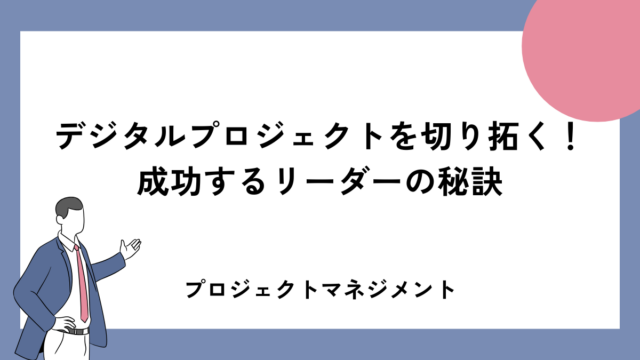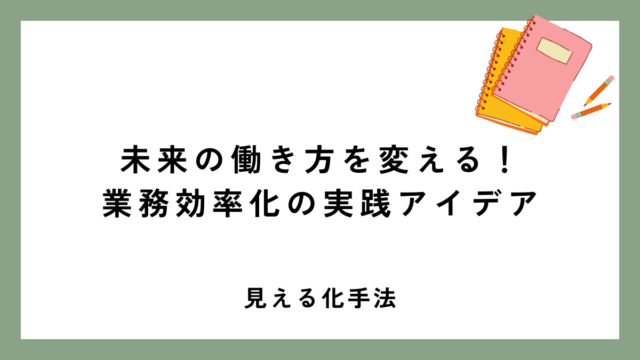システム導入を成功させる!事前の運用検討の進め方
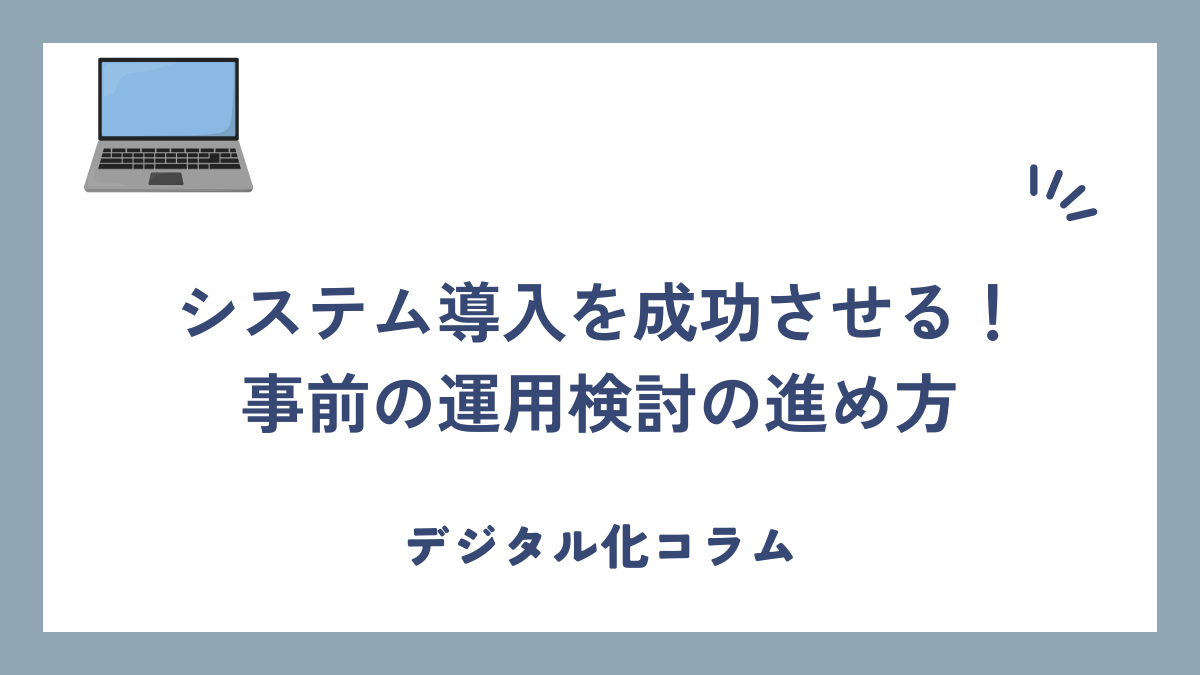
(2025/3/24 更新しました)
システム導入でドタバタしていませんか?
円滑なシステム導入には、実務を廻すために「事前の運用検討」が重要です。
システムは、ツールです。
ツールは、使い方次第ですよね。
今回は「円滑にシステム導入するための事前の運用検討の進め方」について紹介します。
私自身は、大企業で20年以上プロジェクトリーダーをしていました。
何十億のシステム導入の経験もあります
その経験に基づいています。
運用検討の概要と重要性

運用検討とは何か?
運用検討とは、システムが安定して稼働し続けるための仕組みを構築するプロセスを指します。
これはシステム導入後の運用段階において、トラブルを未然に防ぎつつ、効率的かつ継続的にシステムを利用できるようにするために非常に重要です。
この検討では、システム利用者の役割、連絡方法など、さまざまな観点を考慮しながら、具体的な業務フローや運用ルールを策定します。
運用検討がしっかりしていることで、業務効率化とシステムの安定稼働が実現されます。
また、システム導入の目的も達成することができます。
運用検討がシステムの安定稼働に必要な理由
システムは、ツールです。
ツールは、使い方次第ですよね。
システムは導入後も長期間にわたり運用され、日々利用されるものです。
事前に運用検討を適切に行うことで、日々の運用が効率的に廻り、システムの可用性向上につながります。
例えば、システム導入後に以下のような状況になったとします。
- 使い方わからないよ
- 私は いつ何をするの?
- 後工程から苦情が来たのだけど なぜ?
これでは、せっかくシステムを導入したとしても、当初の目的は果たせないですよね。
そのため、運用検討はシステム稼働の土台となり、安定した運用を支える鍵となります。
運用設計と開発設計の違い
開発設計と運用検討は、それぞれ異なる目的を持っています。
開発設計は主にシステムの機能やスペック、サービス内容を決定するための設計です。
一方で、運用設計はシステムがどのように運用されるか、誰がいつどこでどのように利用するかを考えるものです。
また、開発設計は システム部門が主であり、運用検討は ユーザー側が主で行うものです。
運用検討により、ユーザー部門とシステム部門の連携がスムーズになり、運用業務の効率化とトラブル回避が可能になります。
これらの相違点から、運用検討が開発設計を補完し、システムのライフサイクル全体を支える役割を果たしていることがわかりますよね。
システム開発と運用検討の進め方
運用の準備は、システム開発と並行して行います。
開発段階に合わせて、運用検討も 徐々に詳細化していきます。
システム開発のプロセスは、通常以下です。
- システム構想
- 要件定義
- 詳細設計
- 設計・プログラミング
- システムテスト
- ユーザーテスト
- 立ち上げ
4. 5. は、システム部門の作業になりますので ユーザー部門には関係ありません。
また、購入の場合は、3 〜5. は 調達〜システムセットアップになりますね。
運用検討は、システム開発の各フェーズと 並行して進めていきます。
以下に、各開発フェーズとその際に決めるべき運用項目について 概要を紹介していきます。
システム構想フェーズでの運用検討のポイント
通常、現行の業務フロー図作成します。
そして、問題箇所を明確にします。
どこに問題があるか、そして、どう対策するかを検討します。
この際に、システムで対策すること・運用で対策することを分けて考えることが重要です。
システムは、所詮ツールです。
ツールだけでは、解決ができません。
「運用で対策すること」を必ず明確化します。
そして、新側の業務フロー図を作成します。
システム導入後の業務フロー図です。
ここに、運用で対策することを織り込みます。
このフェーズでは、まだシステム仕様は決まっていません。
ルールも、まだです。
対策を織り込むと「こういう業務フローになる」という姿を描いていきます。
要件定義フェーズでの運用検討のポイント
システム仕様を決める際に、ルールは必要です。
例えば、伝票に記載する番号は 西暦+月+追番といったものです。
運用検討では、ルールを決めていきます。
また、このフェーズは ユーザー側の要求事項を システムに織り込む段階です。
システム仕様中心になりがちですが、運用も並行して検討します。
「このシステム仕様で運用が廻るか」の視点です。
本来は、運用をこうするので システムの仕様はこうする という順番が正しいです。
要は、運用を決めるのが先です。
ただ、システム開発に入ると そこまで手が回らないというのが実情だと思います。
システム仕様と運用を 同時に検討していきます。
そして、新側の業務フロー図に落としていきます。
構想段階の業務フロー図では、IN側にシステム名を記載していると思います。
これをシステムのメニュー・システムの機能に修正するイメージです。
また、イレギュラー業務もありますよね。
システム仕様に織り込むことはもちろんですが、運用も決めておきます。
「○○が発生した場合のシステム運用方法」として、文書化していきます。
詳細設計フェーズでの運用検討のポイント
詳細設計の段階になると、システムの画面が決まってきます。
画面が決まれば、業務手順まで検討できるようになります。
業務手順がなければ、システムは動かせないですよね。
システムの画面を活用しながら、システムの操作マニュアルと同時に、運用マニュアルも作成します。
ユーザーテストフェーズでの運用検討のポイント
ユーザーテストは、これまで検討してきた業務フロー・業務手順に沿って 行います。
ユーザーテストは、実務として運用が廻るのかのテストです。
システムが正常に動くのかをテストするのではありません。
これを勘違いしている人、本当に多いのです。
そして、ユーザーテストの結果も折り込み、システム稼働前に運用検討を完成させることが必要です。
これぐらい準備しても 大きなプロジェクトの場合、導入後2〜3ヶ月は、ドタバタします。
では、準備していなかったら。。。容易に想像できますよね。
システム導入でもっとも大切なことは、事前に運用を決めることなのです。
まとめ
システム導入には、実務をまわすために「事前の運用検討」が重要です。
そして、運用検討は システム開発と並行して行うことです。
今回は「円滑にシステム導入するための事前の運用検討の進め方」について紹介しました。
せっかく開発したシステム、購入したシステムです。
立ち上げからドタバタ、効果も出ない状況にはしたくないですよね。
「システム導入でもっとも大切なことは、事前に運用を決めること」
これだけで、安定した運用が可能となります。
さて、今回の記事の中で「ユーザーテストのやり方」について触れました。
以下の記事では、その詳細を紹介していますので、ぜひ併せて読んでみてください。
投稿記事:円滑な立ち上げのために!ユーザーテストの目的と設計方法のポイント