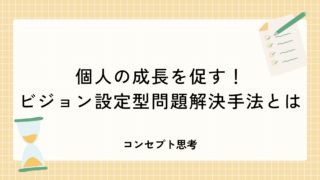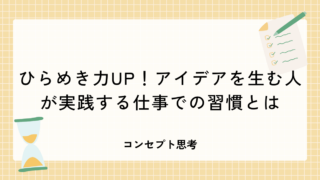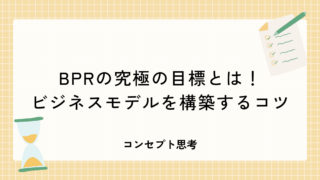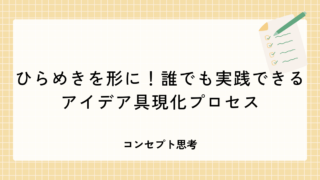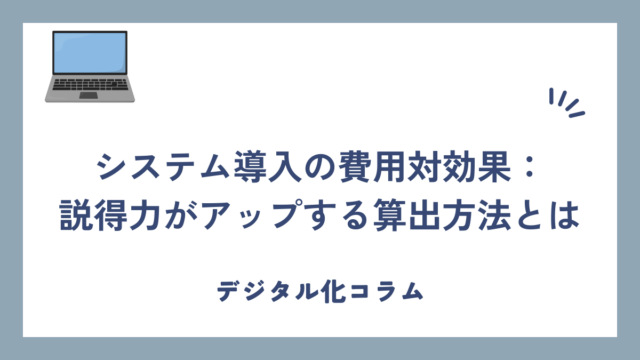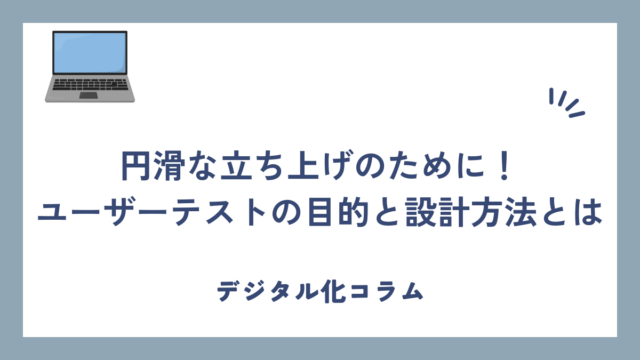「2:6:2の法則」とは?組織を活性化するための方法
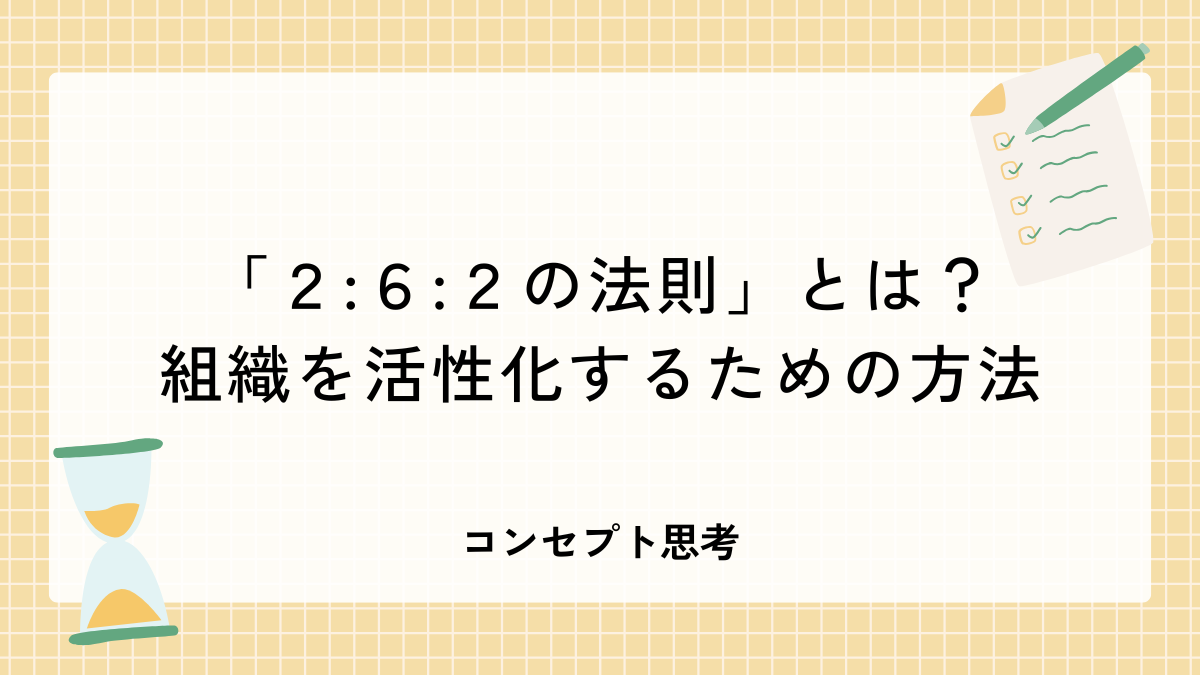
(2025/4/11 更新しました)
2:6:2の法則、知っていますか?
2:6:2の法則は、どんな組織でも存在します。
私が在籍していた日本を代表する大会社でも、事実存在しているんです。
であれば、組織は2:6:2を前提にして、マネジメントする必要がありますよね。
今回は「2:6:2の法則を前提とした組織を活性化させるマネジメント」について紹介します。
私自身は人材開発の専門家ではありませんが、会社在籍中に人材開発部に提言していた内容に基づいています。
2:6:2の法則とは?その基本とパレートの法則との関係

2:6:2の法則の概要
2:6:2の法則とは、組織や集団においてメンバーを上位2割(優秀なグループ)、中間6割(平均的なグループ)、下位2割(成果が低いグループ)に分けた際のバランスを示す法則です。
あなたの組織でも、2:6:2の法則は当てはまるのではないでしょうか?
この割合は、自然界や人間社会のさまざまな領域で観察される現象に基づいていて、放っておいても組織内で自然になる状態です。
この法則を活かすことで、組織のパフォーマンスを効率的に引き上げることができます。
パレートの法則との共通点
2:6:2の法則とよく比較されるのが、パレートの法則です。
パレートの法則は「20%の要素が80%の成果を生み出す」という考え方で、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートによって提唱されました。
一方、2:6:2の法則は、組織内での人材や行動の分布に焦点を当てています。
ただ、着目点が異なるだけで、基本的には同じことではないでしょうか。
2割の人が収益の80%を生むというのは、現実の組織では普通にありますよね。
なぜこの法則が組織に重要なのか
2:6:2の法則の構成要素は、それぞれ組織において異なる役割を担います。
上位2割は高いスキルやモチベーションを持っていて、組織の成果を最大化する原動力となります。
中間の6割は目立たないものの、組織の安定性・継続性を保つ中核を担っています。
そして下位2割は、適切に誘導することによって組織を強化するポテンシャルを持っています。
この分布を正確に理解し、適切に活用することで、組織全体のパフォーマンスを向上させることが可能です。
上位2割の活用方法:人材の力を最大限に引き出す
上位2割が組織に与える影響
組織における上位2割のメンバーは、他の構成員と比べて圧倒的な影響力を持っています。
この層は、高い能力や実績を通じて目標達成に大きく貢献し、組織全体をリードする存在です。
また、自律的に行動するメンバーであり、その行動力が中間の6割の層にも影響を与え、組織を活性化させる存在でもあります。
ハイパフォーマーへの適切なマネジメント方法
上位2割のメンバーに適切なマネジメントを行うことは、組織の成長に直結します。
基本的なマネジメント方法は、方向性を示して自由にさせることです。
できれば 個々の組織のビジョン策定に参加をさせ、共有します。
彼らは方向が決まれば、自ら戦略・戦術を考え実行してくれます。
後は、彼らが創造性を発揮しながら 生き生きと仕事ができる環境を創ることですね。
また、彼らは自己実現欲求が強いので、一律の評価や管理ではなく個別に目標を設定することが重要です。
そして、適切なフィードバック・評価を行うことで、モチベーションを維持・向上させることです。
上位2割を中心としたリーダーシップ
上位2割のメンバーは、リーダーシップを発揮することで組織の中核を支える重要な役割を担います。
これらのメンバーが牽引役となることで、中位6割のメンバーも刺激を受け、全体のモチベーションが向上する効果が期待できます。
そのため、リーダーとしての役割を明確にし、彼らの強みを活かした組織的な仕組みづくりが必要です。
具体的には、彼らの自発的な提案をプロジェクトとして実施することなどが挙げられます。
プロジェクトリーダーとして、中位6割のメンバーを刺激しつつ、成果を上げていくことが期待できます。
中位6割のポテンシャルを引き出す方法
中位6割が果たす重要な役割とは
中位6割のメンバーは、組織全体のバランスを保つ中心的な存在です。
上位2割が注目されがちですが、実際には中間層の働きが組織全体を支えています。
このメンバーが日々の業務を着実に進めることで、安定的・持続的な成果が生まれているのです。
また、彼らのパフォーマンスを少し向上させるだけで、大きな影響を組織全体にもたらします。
このため、この層を活かす方法を検討することは、とても重要なことです。
目標達成を支えるテーマ設定手法
中位6割が持つ潜在能力を引き出すには、「組織が目指すべき方向にむけたテーマ」でマネジメントすることが効果的です。
トップダウン形式の指示だけではなく、組織の現場レベルからの改善提案や新しいアイデアを引き出し、実施すべきテーマを決めます。
または、上位2割が発案したプロジェクトのメンバーにするのも有効です。
これらにより、メンバーが主体性を持って目標達成に向けて行動できるようになります。
それに、上位2割の発案を実際に業務として動かすのは、彼らです。
運用を定着させ、改善を促しましょう。
また、決めたテーマは、達成できるように適切なフィードバックを行うことも重要です。
小さな成功体験の積み重ねにより、モチベーションも高まり、やがては上位2割になっていく可能性があります。
下位2割の存在意義と対処法
下位2割が組織全体に与える影響
組織における下位2割のメンバーは、一見課題と捉えられることが多いですよね。
確かに「嫌々働いている人」がいれば、周囲のモチベーションも下がります。
一方で、組織の中で そうなる原因があるのかもしれないのです。
例えば、下位層の課題を解消することで、全体のパフォーマンスが底上げされる可能性があります。
また、組織の中での役割を再考する機会を提供し、より活性化につながる場合もあります。
組織異動によって、「別人のようになった」人を見た経験ありますよね。
適切な評価と再配置のポイント
下位2割のメンバーを評価する際は、ただ成果が低いだけで評価するのではなく、その原因を分析し適切な再配置を検討することも重要です。
彼らのスキルや適性に応じた仕事に再配置することで、埋もれていた才能を引き出すことができるかもしれません。
このような柔軟な配置変更は、組織全体を活性化させるカギとなります。
モチベーションの低いメンバーへの支援策
モチベーションが低いメンバーには、テーマを与えるマネジメントが有効です。
少なくてもテーマがあれば、やらざるを得ませんよね。
そして、より頻度を上げてフィードバックを行い、小さな成功を達成させることが大切です。
また、チームの一員として、チーム活動に参加させるのも有効です。
一緒に目標に取り組むことによって、帰属意識も出てきます。
何らかの貢献ができれば、自己肯定感を高めモチベーションも上がるかもしれません。
一方で、現状をよく聞き取り、環境や業務内容を見直すことも検討します。
下位2割のメンバーを「切り捨てる」のではなく、メンバー一人ひとりに対する支援策を講じることで、組織全体ののポテンシャルを引き上げることができます。
まとめ
今回は「2:6:2の法則を前提とした組織を活性化させるマネジメント」について紹介しました。
2:6:2の法則は、どんな組織でも存在します。
であれば、それを前提にマネジメントするべきですよね。
そして、組織のポテンシャルを上げ活性化させることが、これからも大切だと考えています。
尚、もうひとつ会社在籍中に提言していたことに「アウトローの扱い方」があります。
これは結構面白いので、別投稿したいと思います。