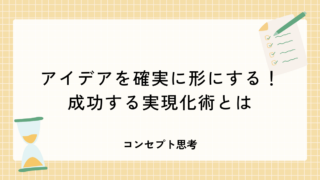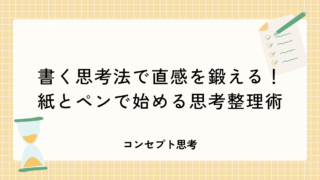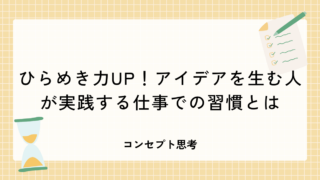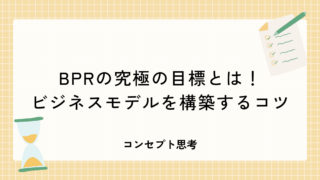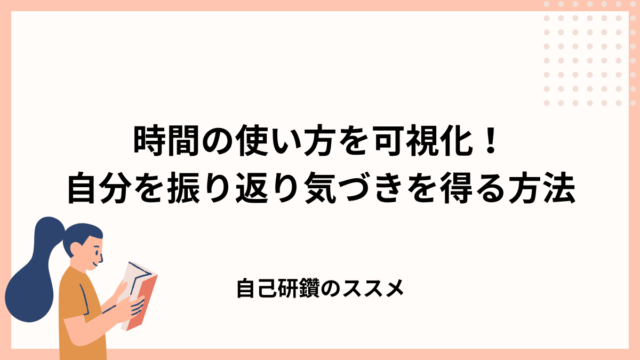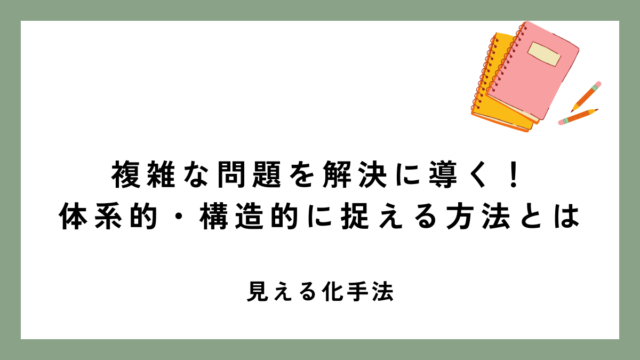個人の成長を促す!ビジョン設定型問題解決手法とは
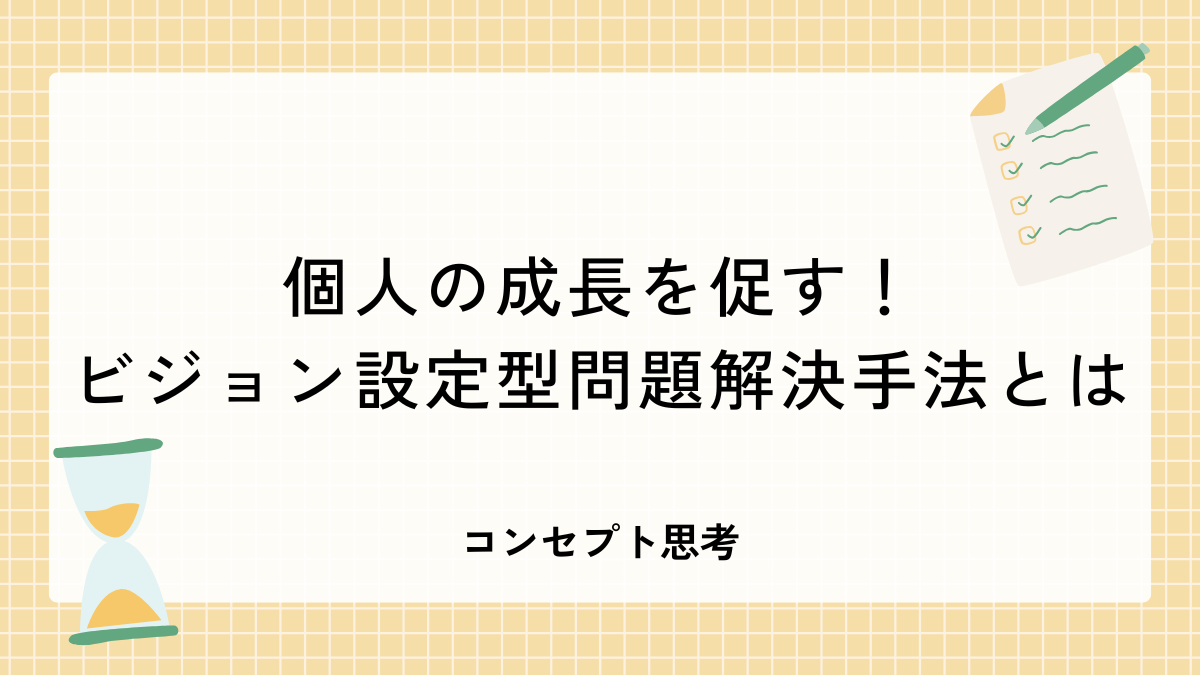
(2025/2/12 更新しました)
問題が発生しました。
この時
「将来を考えると こうなんだけど、今やるならば こっちだよね」
こんな問題解決を行なっていませんか?
これって、組織にとって 本当に良い解決策なんでしょうか?
あなたも 疑問を感じているから こんな発言が出るんですよね。
組織って、ビジョンを達成するために日々活動しています。
それには、組織の中のひとりひとりが ビジョンに一歩でも近づくための問題解決を選択することだと思います。
そして、結果として個人の成長につながります。
なぜならば、あなた自身が 自己決定(自ら考え作っている)をしているからです。
今回は、「問題解決において、ビジョンに一歩でも近づける方法」を紹介したいと思います。
ビジョン設定型問題解決手法の応用・アレンジ版です。
私は、20年以上 自ら企画したボトムアッププロジェクトで 問題解決をしてきました。
全ての問題解決で、ビジョン設定型を応用して活用しています。
その経験に基づいています。
ビジョン設定型問題解決とは
すでに知っている方は 飛ばしてください。
ここでは、簡単に説明します。
ビジョン設定型問題解決とは、ビジョンを設定し 現状とのギャップを問題と捉える考え方です。
そして、ギャップを埋めるために対策を考えます。
ビジョンとは、将来のあるべき姿・なりたい姿です。
ミッション・経営理念を採用している組織もあると思いますが、これらを具現化した姿を指します。
そして、組織全体のビジョンは 個々の組織・事業・業務に落とし込まれています。
要は、どの業務(事業)レベルでも ビジョンはあるのです。
普段は、あまり意識していないのかもしれません。
でも、こんな会話ありませんか。
「うちの目指している姿とは違う」
どこの組織でもある証拠ですよね。
さて 問題が発生しました。
原因を調査し、対策を考えますよね。
通常の問題解決手法の出番です。
ただ、通常の問題解決手法は 現時点で可能なことを選択する傾向にあります。
一番現実的な解決になるからです。
その際、将来から考えてみませんか?
ビジョンに一歩でも近づく対策を選択することです。
あるべき姿・なりたい姿を 少しでも考える、対策も変わっていきます。
以下、ビジョン設定型問題解決手法(アレンジ版)の手順について 紹介します。
ビジョン設定型問題解決手法(アレンジ版)の手順
- 問題を把握する
- ビジョンからのギャップを把握する
- 目標を設定する
- 問題の原因を特定する
- 対策案を検討する
- 対策案を評価・対策を決定する
- 対策を実施する
- 対策結果の評価をする
- 標準化する
通常の問題解決手順に、2.を追加しただけです。
ただ、3. 〜6.の考え方が変わります。
本来のビジョン設定型問題解決は、1. が「ビジョンを設定する」ですよね。
問題発生がトリガーになっていますので、この順番にしています。
個々について、概要を紹介します。
ビジョンからのギャップを把握する
先ずは、ビジョンを明確にする必要あります。
上位のビジョンから、解決する問題を取り巻くビジョンへ落とし込みます。
自分自身の業務(事業)です。
多くの場合、頭の中にあると思います。
それを頭の中から取り出し、言語化・明文化することです。
言語化するのは、整理するためです。
頭の中では、いろんなことが絡み合っています。
過去・現在・未来もあります。
自分自身の感情もあると思います。
絡み合った情報を 未来視点で吐き出し、どうあるべきかに具現化することです。
そして、上位のビジョンとの整合性を確認します。
どうでしょうか?
組織の経験が長ければ、上位ビジョンとのズレは ほとんどないと思います。
逆に、+αのビジョンもあると思います。
自分自身の業務(事業)を一番知っているのは、組織の中では あなただけだからです。
次に、具現化したビジョンと現在のギャップを見つめます。
多くの場合、大きく離れていると思います。
私が勤めていた大企業でさえ、そうです。
なので、現場路線を優先させる動機付けができてしまうのです。
でも、それで良いですか?
大きく離れているからこそ、やるべきではないでしょうか?
最終的には、問題を把握した当事者の判断になります。
ただ、改善にしろ・改革にしろ・変革にしろ「最初は たったひとりから始まる」ということを 認識して欲しいと思います。
そして、組織の中では あなただけができるということも 認識して欲しいと思います。
ギャップが大きいのは、普通なのです。
自己決定が、あなたの成長を促します。
目標を設定する
どうあるべきか、どうなるべきかが分かれば、到達点は見えてきます。
到達点に近づくための目標を設定します。
ビジョンに一歩でも近づく目標を立てることです。
「今回は、このぐらいの地点まで近づこう」でも十分です。
私の経験では、大きなギャップは 複雑な要因が絡み合った構造的な問題であることが多いです。
一度で埋めることは、時間・コストがかかることが多いです。
プロジェクトを起こして問題解決する場合でも、構造の「ある特定部分」に焦点を当てています。
構造的な問題は、ステップを分けて考えるのが良いと思います。
問題の原因を特定する
なぜなぜを繰り返して、真因を探ります。
通常の問題解決と同じです。
但し、ビジョンとのギャップを埋めるには という視点で探すことになります。
私は、将来と現時点の業務シーンを絵に描くことを よくやっています。
ギャップを把握する際も、原因を探る際も、絵を比較しながら検討しています。
絵にした時点でギャップはわかりますよね。
それと絵にすると、業務(事業)間の関係もわかります。
ギャップの原因も、網羅性を確保しつつ 広い視点で捉えることができます。
対策案を検討する・評価する
対策案を検討することは、通常の問題解決と同じです。
ただ、ここでも視点は ビジョンとのギャップを埋める対策です。
また、評価指標に ビジョンに対する達成度が入ることになります。
そして、対策案を 評価・選択します。
ビジョン達成型問題解決は、一度きりで終わりになることはないと思います。
前述した通り、一気にビジョン達成することは 難しいからです。
また、試行錯誤も必要です。
未来に対する対策です。
正解は、やってみないとわからないものです。
逆に言えば、通常の問題解決との1番の違いです。
まさに醍醐味であり、あなたの成長を促す糧となります。
そして、次に進みましょう。
まとめ
組織に正のスパイラルを起こし、ビジョン達成に向けて すばやく動く。
競争に打ち勝つためには 必要ですよね。
今回は、そのための手法として「ビジョン設定型問題解決の手順」について 紹介しました。
手順は、以下です。
個々について、概要を紹介しました。
ビジョン設定型問題解決の手順
- 問題を把握する
- ビジョンからのギャップを把握する
- 目標を設定する
- 問題の原因を特定する
- 対策案を検討する
- 対策案を評価・対策を決定する
- 対策を実施する
- 対策結果の評価をする
- 標準化する
これから、組織の中の「個人の力」 ますます大切だと思います。
それには、組織の中のひとりひとりが ビジョンに一歩でも近づくための 問題解決・対策を選択することが重要なのではないでしょうか。