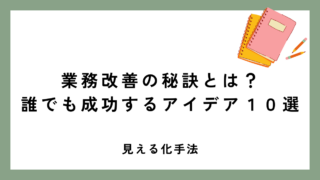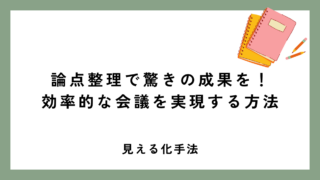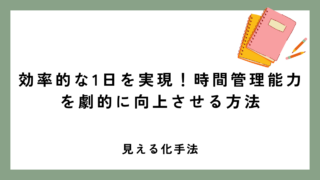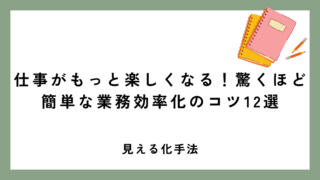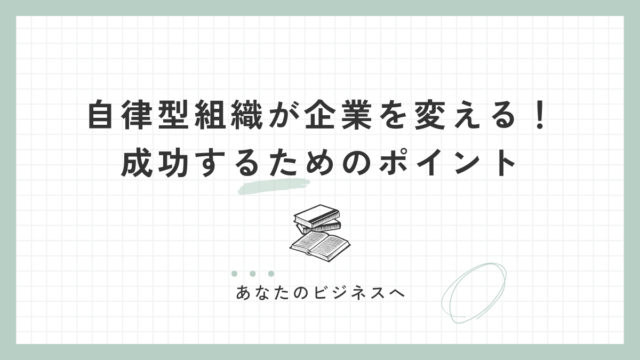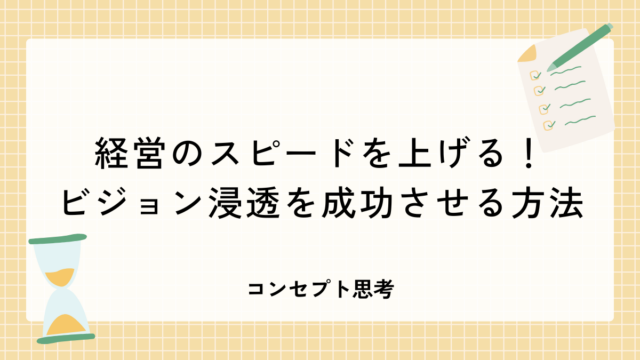「見える化」で業務革命!組織力を最大化する方法
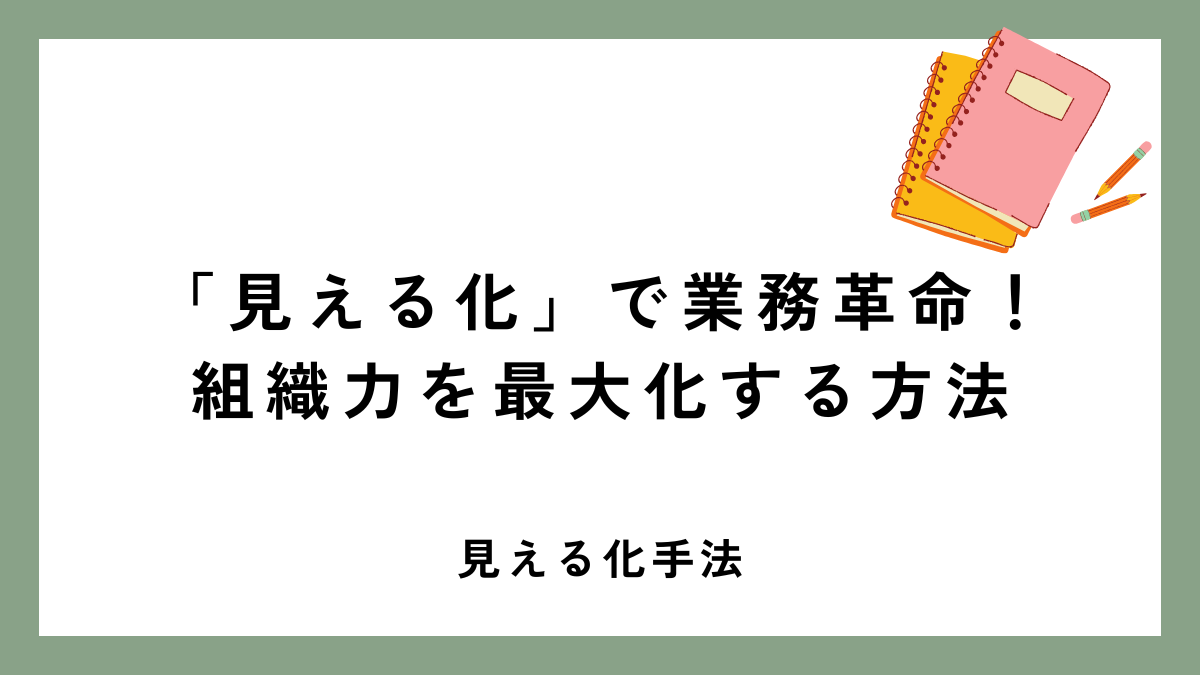
(2025/3/4 更新しました)
- あなたの部下、どんな業務をしているか説明できますか?
- 一緒に 業務について、話し合いしていますか?
- 人事考課のフィードバックの際に、部下の成長 きちんと説明できていますか?
意外とできていないのではないでしょうか。
「見える化」は、組織の中での社員一人ひとりの役割を明確にします。
役割を理解することで自主性を促し、組織に活力を与えます。
今回は「見える化によって組織力を上げるための方法 及び 具体的な進め方」について紹介します。
尚、私自身はBPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)プロジェクトを何度も経験しています。
その経験に基づいています。
「見える化」とは何か?その基本概念と重要性

見える化の定義と目的
「見える化」とは、業務やスキル・情報など 普段は見えにくい要素を視覚化し、誰もが理解しやすい形で表現するプロセスを指します。
目的としては、業務の透明性を高め、属人化を防ぐことで、組織力の強化や一人一人が成長できる環境の構築が挙げられます。
また、社員一人ひとりのスキルや業務状況を把握しやすくすることで、適材適所の人材配置を実現する役割も果たします。
見える化がもたらす組織強化の効果
見える化を導入することで、組織全体に多くのメリットが生まれます。
まずは、業務の効率化が挙げられます。
複雑な業務プロセスを明確にすることで、ボトルネックを発見しやすくなり よりスムーズな業務運営が可能となります。
業務って、暫くすると どんどん複雑化しますよね。
重複する業務やムダな業務を発見することもできます。
また、スキルの差異や不足を特定することで、スキルギャップを解消しやすくなります。
これにより、組織の生産性を向上させるだけでなく、社員の成長を促進する効果も得られます。
結果として、全体的な組織力の強化が図れます。
個人から組織へ:暗黙知の共有方法
組織内における暗黙知の共有は見える化の重要なテーマです。
暗黙知とは、個人の経験や直感など、言語化されていない知識を指します。
実際に組織の中には、いっぱいの暗黙知が存在します。
なぜなら人は工夫する生き物だからです。
この暗黙知を共有するためには、スキルマトリックスの活用や情報の一元管理が効果的です。
たとえば、特定の業務を担当している個人が持つノウハウを明確なプロセスとして残し、誰もがアクセス可能な形で運用することで、全体の知識の底上げが図れます。
このような取り組みにより、組織は個人の力に依存する状態から脱却し チーム全体としての成長が可能になります。
導入に向けた準備のポイント
見える化を成功させるためには、導入前の準備が非常に重要です。
具体的には、現状を正確に把握するための調査や分析が必須です。
業務の流れやスキルの現状を見極めた上で、共有すべきデータを明確にする必要があります。
また、見える化のためのツール選定も重要な要素です。
例えば、業務の標準化システムやタスク管理ツール・スキルマネジメントシステムなど、組織の課題に合った適切なツールを選ぶことで、導入後の効果が大きく変わります。
さらに、全員が共通の目標を持ち、理解を深めるためのコミュニケーション戦略も欠かせません。
準備段階で適切なステップを踏むことが、見える化の成功の鍵となります。
「見える化」が解決する課題とは?
属人化の解消:スキルと業務の具体化
ビジネス環境の変化が激しい中、属人化は多くの企業が抱える課題の一つです。
属人化が進むと、特定の個人だけが業務内容やプロセスを把握している状態になり、社員の退職や異動時に業務が滞るリスクが高まります。
「業務の見える化」を活用することで、属人化を解消し、組織力を強化することが可能です。
具体的には、スキルマトリックスなどのツールを用いて社員一人ひとりのスキルを整理・可視化し、全員が共有できる形にします。
これによって、適材適所の人材配置が可能となり、スキルギャップの解消にも繋がります。
また、業務プロセスを明確化することで、他のメンバーが同じ業務を引き継ぎやすくなるため、組織全体の生産性が向上します。
このように、スキルと業務を具体的に示すことが組織の成長において重要なステップとなります。
業務プロセスの可視化がもたらす効率改善
業務プロセスを可視化する取り組みは、組織の効率改善に直結します。
具体的には、業務の流れをフロー図やタスク管理ツールで明確化し、どのステップで時間やリソースが浪費されているのかを把握することが可能です。
可視化による効率改善のメリットとして、無駄な作業の削減や業務プロセスの最適化が挙げられます。
また、現状の業務フローが明らかになることで、ボトルネックとなる箇所の特定も容易になり、迅速に改善策を講じることができます。
このプロセスを通じて、組織全体の生産性が向上し、組織力の強化に繋がります。
「見える化」は単なるデータ化だけでなく、効率的で柔軟な働き方の実現にも寄与します。
コミュニケーションの円滑化と情報共有の促進
「見える化」を取り入れることで、組織内のコミュニケーションが円滑化し、情報共有が活性化します。
明確なデータやビジュアル化された情報があることで、各メンバーが共通認識を持つことができ、不要な誤解や手戻りが減少します。
例えば、プロジェクトの進捗状況やタスクの優先順位が全員に共有されていれば、関係者間で同じ目標に集中することができます。
このように、情報が共有されている環境は、チームメンバー間の信頼構築を促し、協力作業をスムーズに進める土壌を形成します。
そして、「見える化」は 社員の自主性を促します。
情報共有されれば、ひとりひとりが考えるようになりチーム・組織の活性化が期待できます。
また、適切なツールを活用することで、社員が遠隔地にいながらもリアルタイムで最新情報にアクセスしやすくなるため、チームの一体感が高まります。
在宅勤務でも、効果を発揮します。
課題の早期発見とボトルネックの特定
業務の「見える化」によって、課題が早期に発見できるようになります。
特に、日常業務の流れや成果データが可視化されることで、異常値や停滞が一目で分かり、迅速な対応が可能になります。
具体的には、プロジェクトの進捗を定期的にモニタリングできる仕組みを構築することで、ボトルネックとなる要素をいち早く特定し、解決に向けたアクションを検討することができます。
これは、組織全体が長期的な成長を続けるための重要な基盤となります。
また、課題が可視化されることで、社員一人ひとりが自らの役割やタスクに対して責任を持つ意識が高まり、組織力の向上に寄与します。
業務の「見える化」の具体的な進め方

基幹系業務を見える化する
あなたの組織では、業務標準が揃っていますか?
業務標準があっても5年も変更されていなければ、実態とは かけ離れていると思います。
でも対策として、個々の業務標準をいきなり作成することは オススメできません。
先ずは、基幹系の業務を見える化すべきです。
組織は、相互依存によって成り立っています。
一番相互依存がある業務というのは、基幹系業務です。
見える化により、各チーム・組織の位置付けがわかります。
各チーム・組織が、どう関わり動いているのか 全体を把握することができます。
そうすると、社員一人ひとりの立ち位置もわかるようになります。
わかれば、人の意識は 変わるものです。
意識が変われば、行動も変わります。
自分ごと化する準備も できあがるのです。
社員一人ひとりの役割を見える化する
組織がどう動き、組織の中の位置付けがわかったのであれば、次は 社員一人ひとりの役割を考えてもらいましょう。
マネジメントから「あなたの役割はこうだ」と一方的に押し付けるのではなく、組織の中で あなたは何ができるのか・何で貢献できるのか 考えてもらうのです。
もちろん この中には、課題への取り組みも含まれています。
そして、よく話し合いをしましょう。
組織の目標と社員一人ひとりの役割・目標のすり合わせです。
自ら設定した役割・目標です。
社員一人ひとりが自らの役割やタスクに対して責任を持つ意識が高まり、組織力の向上に寄与します。
マネジメントを見える化する
マネジメントは、社員一人ひとりの自主的な取り組みをサポートします。
注意することは、マネジメントはコントロール(管理)ではないことです。
ひとりひとりに合わせて サポートのレベルを柔軟に設計しましょう。
具体的には、進捗報告の方法・頻度などのマネジメント計画を 社員一人ひとりとすり合わせて 見える化します。
チームで共有することによって、一体感も生むことができます。
そして、絶対にやり遂げさせる覚悟で サポートすることが大切です。
やりきったという実績は、必ず個人の成長につながります。
また、当然のことですが、適切なフィードバック・評価に利用することです。
まとめ
今回は「見える化によって組織力を上げるため方法及び具体的な進め方」について紹介しました。
「こんなの当然だよね」と思われた方、多いのかもしれません。
でも、私が在籍した大企業でさえ 意外とできていないのですよ。
組織を活性化するには、社員一人ひとりの当事者意識が不可欠です。
そのためには、まずは自分の役割を認識する必要があります。
もちろん長期的視点で、繰り返し実践する必要があります。
ただ、確実に 組織力は上がり、自主的・自律的な組織の文化・風土になっていきます。