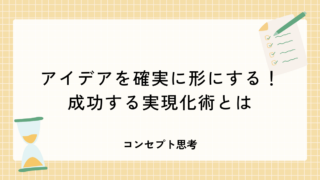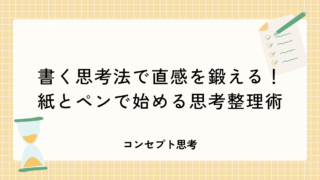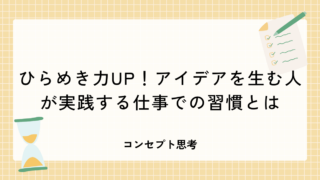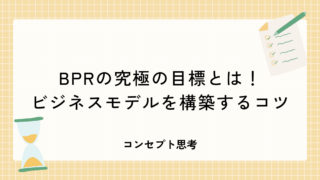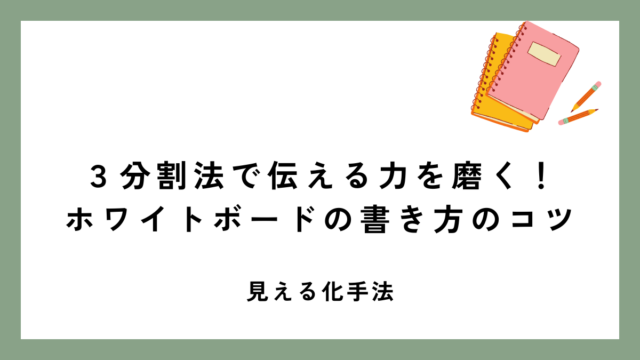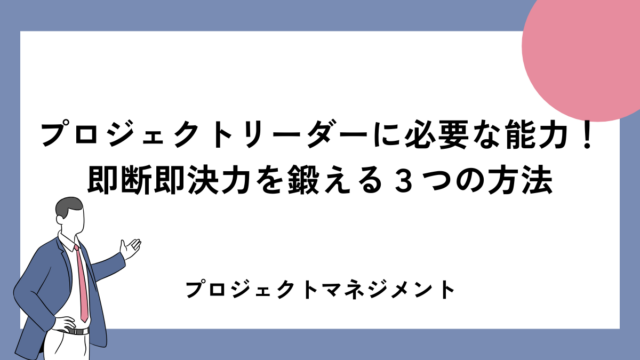アイデアを具現化する!仮説検証PDCAの4つのコツ
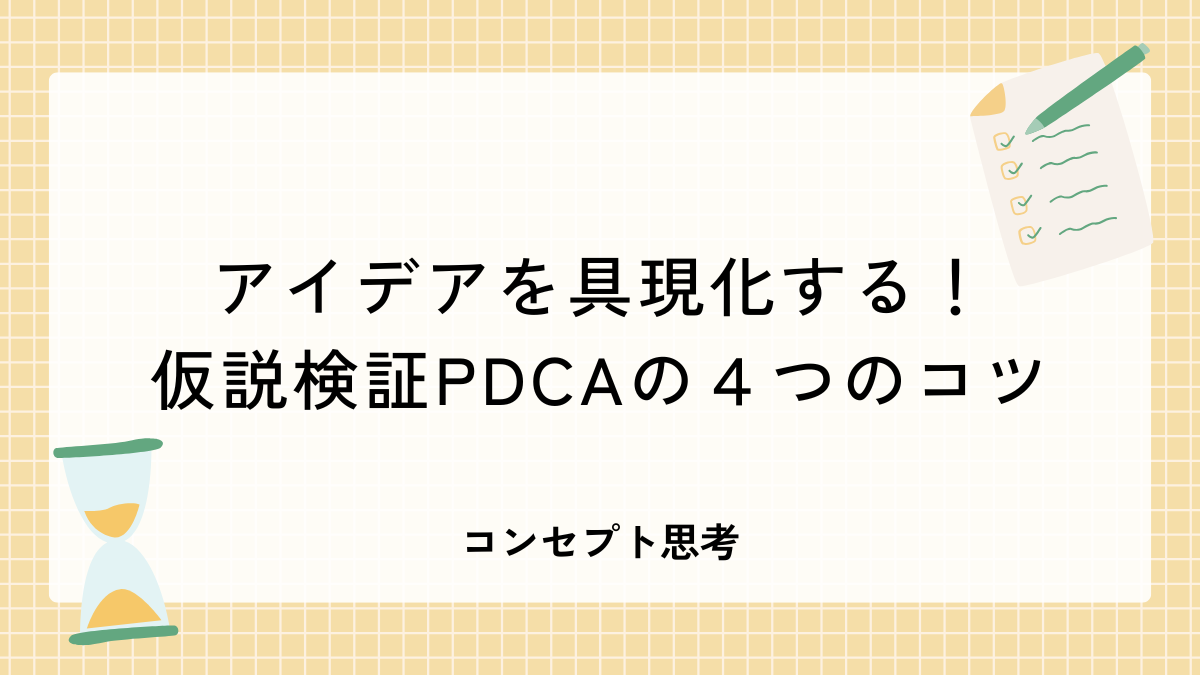
突き抜けたアイデア。
従来と抜本的に異なる「もの・サービス・オペレーション」です。
早く検証し導入することが 大切ですよね。
ビジネスは、競争の世界です。
最初に始めたものが、 先行者利益を受けることができます。
ならば、すばやく仮説検証サイクルを廻し 人を動かし 導入することです。
今回は、私が行った社内の抜本的オペレーション変革の経験から「アイデアを具現化するための仮説検証PDCAの4つのコツ」について紹介したいと思います。
ちなみに、抜本的オペレーション変革は 海外で賞も取っています。
目次
仮説検証が必要な理由

突き抜けたアイデアというのは、従来とは全く異なる「もの・サービス・オペレーション」です。
まだ誰も経験したことがないものです。
具体的な姿にしなければ、何もわからないというのが現実です。
そもそもアイデア自体が仮説ですよね。
素早く検証しましょう。
具体的な姿にして、見せるのです。
そこで初めて、評価が生まれます。
そして、フィードバックを受ける。
更に アイデアがアイデアを呼ぶ循環ができます。
一方で、突き抜けたアイデアは 簡単には組織に受け入れられません。
ほとんどの人が、懐疑的だと思います。
人を動かすことが必要です。
そのためには、効果を証明する必要があります。
良い循環を生み出す・人を動かすために必要なステップが、以下に説明する仮説検証PDCAです。
また、スタートアップだけが対象ではありません。
大企業でも 中小企業でも、どんなビジネスも対象になります。
突き抜けたアイデア、最初は たったひとりから生まれます。
ビジネスの規模は 関係ありません。
仮説検証PDCAとは
通常のPDCAとは
Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクルです。
一般的な製品開発、サービス開発、事業開発などで使っている手法です。
いわゆるウォータフォール型の開発で行われるものですね。
仮説検証のPDCAは、
Plan(計画)→Do(試作)→Check(評価)→Action(実行)だと考えています。
このサイクルをすばやく廻し、Do(試作)を Action(実行)に移行することです。
仮説検証のPDCA
- Plan:仮説に基づき 試作計画を作る
- Do:試作品を作り 実際に試してもらう
- Check:その場でフィードバックを受け、計画見直し・試作に戻る
- Action:検証結果により、実際の「もの・サービス・オペレーション」にし 世に出す
仮説検証PDCAを廻す際の4つのコツ
今回は、4つ紹介したいと思います。
- P(計画)→D(試作)へすばやく動く
- D(試作)は数回試す
- C(評価)は数字で測定、コンセプトを大切に
- A(実行)で世に出す
以降で、順番に説明いたします。
P(計画)→D(試作)へすばやく動く
ビジネスでは、計画がもっとも重要。
私たちは、ビジネスの基本として ずっと教えられてきています。
なので、時間をかけて綿密に計画を練りますよね。
でも、突き抜けたアイデアの場合、先が読めません。
もちろん勝算あってのものです。
ただ、実際に受け入れられるのか 確証はありません。
そして、その後の展開も 多くはわからないのが 普通です。
先ずは、最初のPDCAを廻す計画を立てるだけで十分です。
P(計画)は、アイデアの核心の部分を具体化します。
枝葉では、効果わかりません。
そして、革新部分の試作に さっさと取り掛かります。
とにかくスピード優先です。
例えば、私が実践したオペレーション変革の場合、経験してもらわなければ 何もわかりません。
オペレーションには ツールが必要ですよね。
でもツールは、既存のもので構いません。
工夫して使えば良いのです。
そもそもツール開発しても、それが使えるものになるかわからないですよね。
時間のムダです。
D(試作)は数回試す
最初の試作品は、必要最低限のものです。
実際に利用してもらうと、いろいろな意見がでます。
すぐにP(計画)に戻し、D(試作)を行いましょう。
私が行った社内のオペレーション変革の場合は、3回以上は行っています。
利用者は 初めて経験します。
人って、好奇心持っていますよね。
それにビジネスです。
仕事であれば、必ず意見は出てきます。
「ここ、わかりにくいなあ」
「こうすると、もっと効果あるかも」
こんな意見 普通に出てきます。
フィードバックを受けたら、すぐにPに戻り 修正しましょう。
そして、もう一度試すのです。
サイクルは 短期間で、大切なポイントです。
C(評価)は 数字を測定、コンセプトをもっとも大切に
P(計画)の段階で、効果測定する項目は決めます。
やはり、数字になるものは必要です。
特に、日本のビジネスは 数字を もっとも重要視します。
組織・人を動かす必要がありますよね。
数字がないと 説得力に欠けます。
アイデアによって、評価指標は異なります。
もっともそのアイデアを表す指標を選ぶことになります。
オペレーションの場合は、工数・コスト・期間が 一般的なものになります。
ただ突き抜けたアイデアです。
期間であれば、1/3に短縮ぐらいのインパクト必要です。
実際に、私のオペレーション変革の場合は「期間1/3の短縮」でした。
一方で、アイデアには コンセプトがあると思います。
コンセプトこそが、もっとも重要です。
コンセプトを達成しているか、コンセプトに近づいているか もっとも大切な評価指標です。
コンセプトの多くは、定性効果です。
なかなか数値に落とすことは、難しいです。
それと日本のビジネスでは、あまり評価されません。
アイデアを出した本人にしか わからないものです。
数値という定量効果は 説得用として、コンセプトの方を重視しましょう。
A(実行)で 世に出す
Aは、本来のPDCAでは 改善に当たります。
ただ アイデアを仮説検証する場合、アジャイルで進めていくことが多いと思います。
アジャイルであれば、次のサイクルのP(計画)になります。
一旦できたものは 世に出すことです。
もの・サービスであれば、実際に提供することです。
オペレーションであれば定着化(標準化)し、活用していくことです。
どんなに検証したとしても、市場の評価は 約束されていません。
であれば、実際に市場に出すことが必要です。
そして、生のフィードバックを得ます。
特に、アイデアがオペレーションの場合は、どんどん変革していくことになります。
仮説検証して効果があれば、定着化(標準化)し 実務として行う。
次の仮説検証PDCAのサイクルに、生のフィードバックも織り込む。
そして、次のサイクルでの成果を 定着化(標準化)し 実務として行う。
小さく始め スパイラルに昇華していくことで、効果を最大にしていくことができます。
まとめ
突き抜けたアイデア。
従来と抜本的に異なる「もの、サービス、オペレーション」です。
早く導入すること重要ですよね。
ならば、すばやく仮説検証PDCAを廻すことです。
今回は、私が行った社内の抜本的オペレーション変革の経験から「アイデアを具現化するための仮説検証PDCAの重要な4つのコツ」について紹介しました。
仮説検証PDCAを廻す場合の重要なポイント
- P(計画)→D(試作)へ すばやく動く
- D(試作)は 数回試す
- C(評価)は 数字で測定、コンセプトをもっとも大切に
- A(実行)で 世に出す
せっかく気づいたアイデアです。
世の中を変えることができるのかもしれません。
仮説検証PDCAを廻し、世に出しましょう。
さて、今回は「仮説検証PDCAのコツ」について記載しましたが、一方で 人を動かすことも重要です。
以下の記事では「人の動かすポイント」について紹介していますので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。
投稿記事:アジャイルで抜本的改革を成功するための「人を動かす」ポイントとは