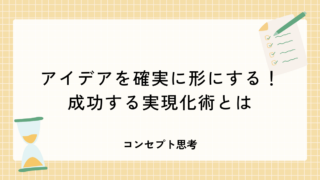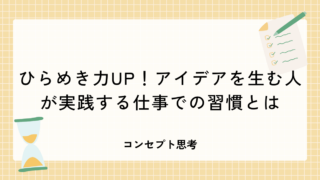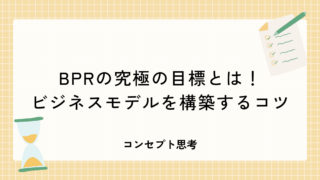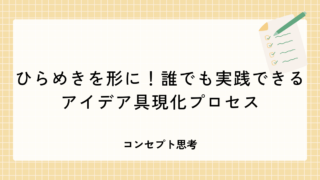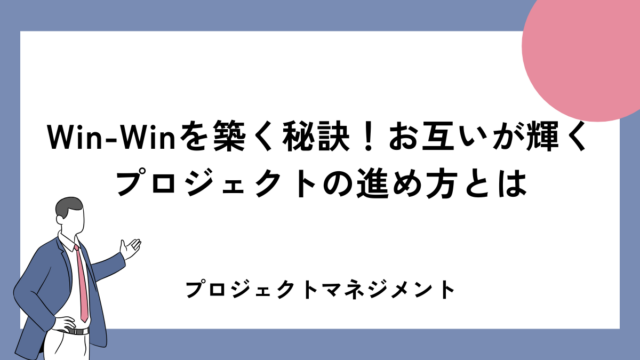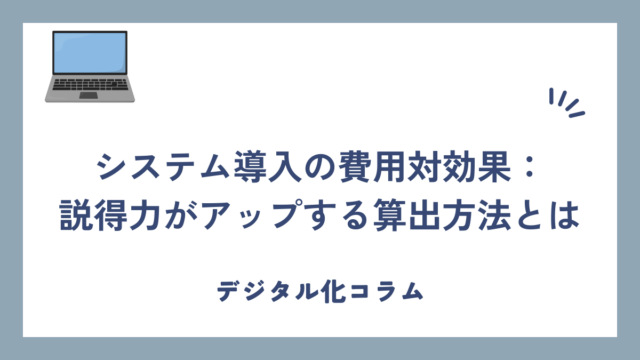これからの問題解決で必須の能力!問いを立てる力を鍛えるには
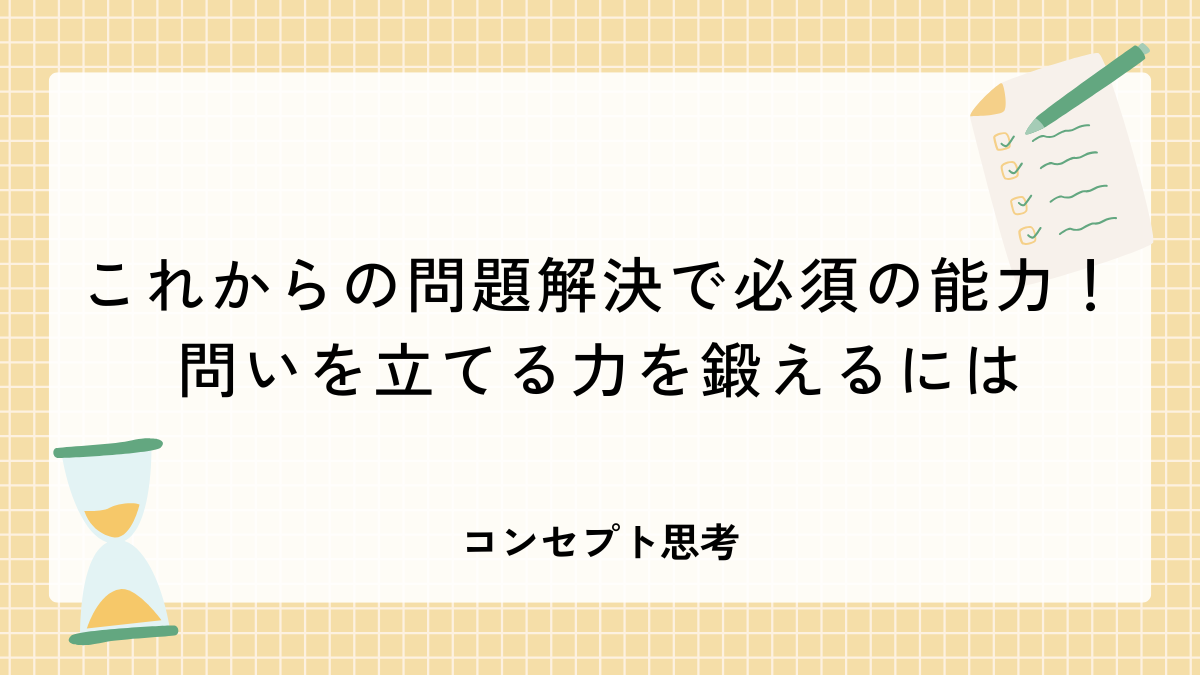
(2025/4/9 更新しました)
問いを立てることは、問題解決の大前提ですよね。
そして、問題解決は「問いを立てる力」によって、全く異なる結果になります。
今回は、これからの問題解決手法に必須な能力である「問いを立てる力を伸ばす方法」について 紹介します。
私は、「問題解決手法といえば。。。」という会社出身です。
そして、数多くの問題解決を実践しています。
だからこそ、「問いを立てる力」が必須だと考えているのです。
「問いを立てる力」とは何か
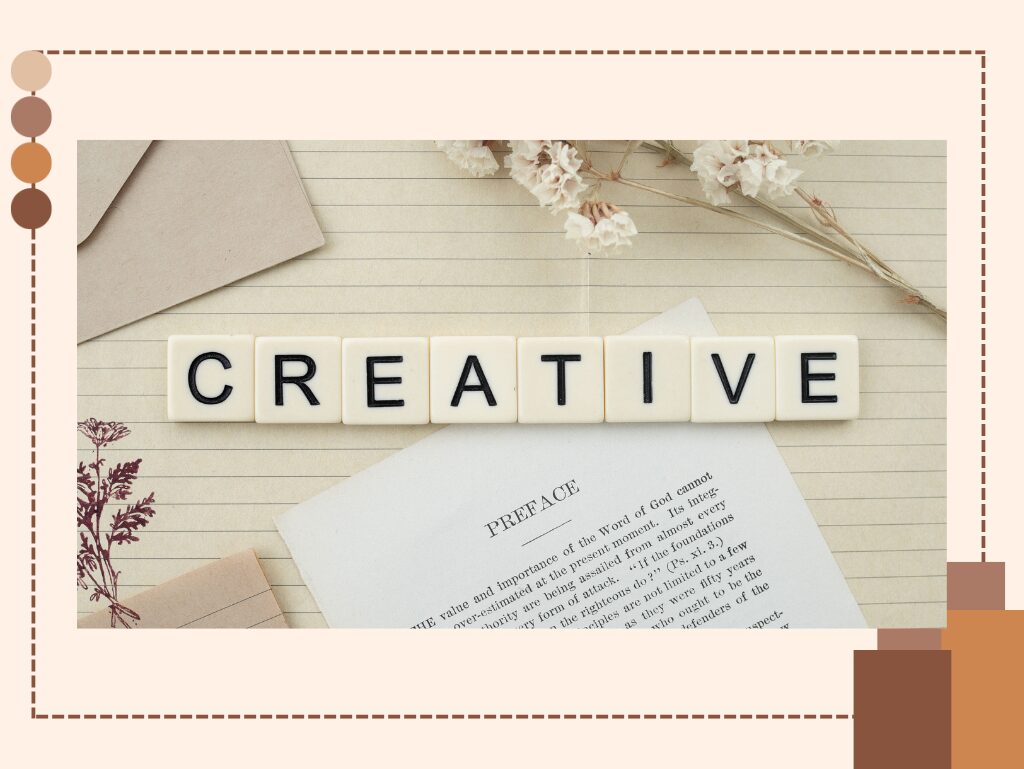
問いを立てる力の基本的な考え方
「問いを立てる力」とは、単なる質問を投げかけることではありません。
それは課題や疑問を明確にし、新たなアイデアを考え行動につなげる力を意味します。
この力は、現状の認識を深め、最適な解決策にたどり着くための出発点となるものです。
たとえば、「なぜこれが問題なのか」「何が本当の問題なのか」など、本質的な核心を突く問いを立てることが重要です。
このような問いが明確になることで、問題解決の指針が形成されていきます。
問題解決における問いの重要性
問題解決において、正しい問いを立てることは非常に重要です。
なぜなら、問いは問題の本質を明らかにするツールとなるからです。
正しい問いを立てることで、現状と理想のギャップを特定し、次のステップである解決策を明確にすることができます。
正しい問いからしか、有効な解決策は導き出せません。
解決に向けた正しいスタート地点を見つけるためにも、問いを立てる力を鍛えることが求められます。
また、現在ではAIの目覚ましい進歩がありますよね。
以下に問題解決手法のステップを挙げますが、どこに人間の強みがあるでしょうか。
- 問題を把握する
- 目標を設定する
- 問題の原因(真因)を特定する
- 対策案を検討する
- 対策案を評価・対策を決定する
- 対策を実施する
- 対策結果の評価をする
- 標準化する
1〜3までですよね。
今のところ、問いを立てるのは人間しかできません。
問いを立てることで得られるメリット
問いを立てる力を鍛えることで、多くのメリットが得られます。
まず、問題の本質を見抜きやすくなり、効率的に効果的な解決策を探ることができるようになります。
要は、人間の強みである洞察力が鍛えられます。
また、状況を新たな視点で捉えられるため、独創的かつ本質的なアイデアが生まれやすくなります。
問いを起点とした問題解決プロセス
問題を特定するための適切な問いとは
問題解決の第一歩は、適切な問いを立てることで問題を把握していくことです。
問題を正確に把握するためには、「何が問題なのか」「誰の問題なのか」「影響はどれぐらいか」といった具体的な問いを投げかけることが重要です。
たとえば、ビジネスにおける売上減少に直面した場合、「いつから」「どの商品・サービスが」「どのエリアで」といった問いからはじめ、課題の範囲を明確にすることが求められます。
原因追求への問いの繰り返し
一度問題を把握したら、その原因を深掘りするための問いを繰り返し行う必要があります。
この段階では「なぜその問題が起きたのか」を突き詰めることが鍵となります。
例えば、売上減少の原因を探る場合、「顧客のニーズが変化したのか」「価格競争が影響しているのか」といった具体的な問いを立てることが効果的です。
そして、さらに本質的な真因を掴む問いを繰り返します。
このような問いの繰り返しは、真因を明確にし、本質的な問題解決に向けた方向性を示してくれます。
解決策を発見するクリエイティブな問い
原因が明らかになった後は、それを解決するためのクリエイティブな問いを考える段階に進みます。
このプロセスでは、「どうしたら本質的・抜本的に解決できるのか」といった仮説的な問いを立てることが重要です。
また、視点を変えることで新たな解決策が浮かび上がることもあります。
たとえば、「顧客に新しい価値を提供する方法は何か」「効率化しつつ短納期が同じ価値・新しい価値を提供できないか」などの問いを投げかけることで、具体的かつ実現可能な解決策を見つけ出すことができます。
問いを立てる力を鍛えるには
観察力を磨く重要性
「問いを立てる力」を高めるためには、まず観察力を磨くことが重要です。
観察力とは、周囲の事象や変化に対して注意深く目を向け、異変に気づく力のことを指します。
問題解決において課題を発見するためには、まずは現状を把握していることが必要ですよね。
そのため、観察力は「問いを立てる」の出発点となります。
観察力を鍛える方法としては、日常生活やビジネスの現場で「なぜお客様はこれを購入するのか」「どうやってビジネスは成り立っているのか」といった問いを持ち、対象に意識を向け続けることが挙げられます。
特に、現在は 便利が当たり前の世の中になっています。
意識して観察しないと、「なぜ」「どうして」は出てきません。
感受性を高める重要性
問いを立てる力を鍛えるには、常日頃から情報に対する感受性を高めることが重要です。
感受性とは、外界の情報を感じとる能力を指します。
また、他人の気持ちを感じ取ったり共感できたりする能力も意味します。
要は、人間にしかない能力です。
感受性を高めるには、まずは情報にいっぱい接することです。
そして、自ら考え、取捨選択をする。
この繰り返しにより、感じ取る能力が高まります。
また、さまざまな人とコミュニケーションをとることにより、視点も増えます。
視点が増えれば、物事の本質をより深く理解し、より多様な解決策を導き出すことができます。
私は会社時代、常に先回りして、これから必要となることを検討していました。
「えっ、いつの間にやっていたの?」「どうして、こうなることがわかっていたの?」と良く言われたものです。
私が実施していたこと 3つ紹介します。
- 常にアンテナを立て、キーワードを拾う
- 社内外ネットワークを築く
- コミュニケーション力を磨く
以下に、概要を紹介します。
常にアンテナを立て、キーワードを拾う
「常にアンテナを立て、キーワードを拾う」のは、情報収集力の強化ですよね。
会社の中にいれば、いろいろな情報が入ってきます。
自分とは関係ないと思い、捨てていませんか?
同じ会社にいて、関係のない情報というのはないです。
そして、情報には、必ずキーワードがあります。
常にアンテナを立て、キーワードを意識して拾うことです。
そして、キーワードを少しでも多く拾うには、全方位に意識を散らしていることが必要です。
散らすというのは、先入観を持たずに「こういうことがあるんだ」と素直に受け入れる姿勢を表しています。
私は、少なくとも興味を持つこと、「知らなかった、面白いなあ」と思うこと、疑問を持つこと、自分が楽しむこと、常日頃から 習慣にしています。
最初の頃は、意識して実施していましたが、継続すれば 習慣になります。
社内外ネットワークを築く
社内外のいろいろな分野の方々と 良い関係を構築し、常に最新の情報が入手できるようにネットワークを構築しておくことです。
できれば、各組織のキーパーソンと関係を築くことをおススメします。
私は、10万人以上従業員のいる大会社に在籍していましたが、ほぼ最新の情報を 常に入手していました。
正規ルートより、ずっと早くに です。
これは、会社生活の最後まで最高の財産となっていました。
コミュニケーション力を磨く
情報収集する為には、色々な方々から 必要なことを引き出さなければなりませんよね。
私の場合は、「信頼の場を創る」ということを常に意識してきました。
信頼があれば、質の良い情報が入ってきます。
また、他人の気持ちを感じ取ったり共感できたりする能力も高まりますよね。
まとめ
今回は、これからの問題解決手法に必須な能力である「問いを立てる力を伸ばす方法」について 紹介しました。
テクノロジーは、凄いスピードで進化しています。
これから問題解決方法も変わるでしょう。
各種センサーによって、膨大なデータを取得できます。
AI・ロボットは、人間では考えられないような対策案を 瞬時に出すようになります。
ただ、どんなに進化しても「問いを立てることができるのは 人」です。
正しい問いを繰り返し、問題解決の質を上げましょう。
さて、今回は「問いを立てる力を鍛える方法」について紹介しましたが、問題解決の質を上げる方法は他にもあります。
以下の記事では「問題解決の質を上げる方法」について紹介していますので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。
投稿記事:問題解決手法の質を高める!使いこなすための3つのコツ