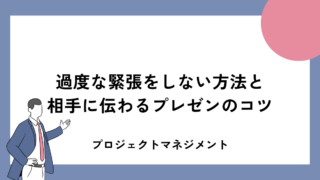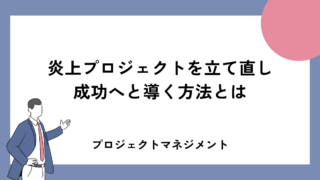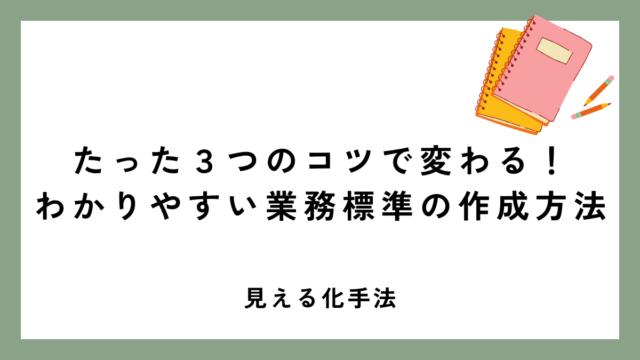プロジェクト実行段階で重要!課題管理の方法と対応方針
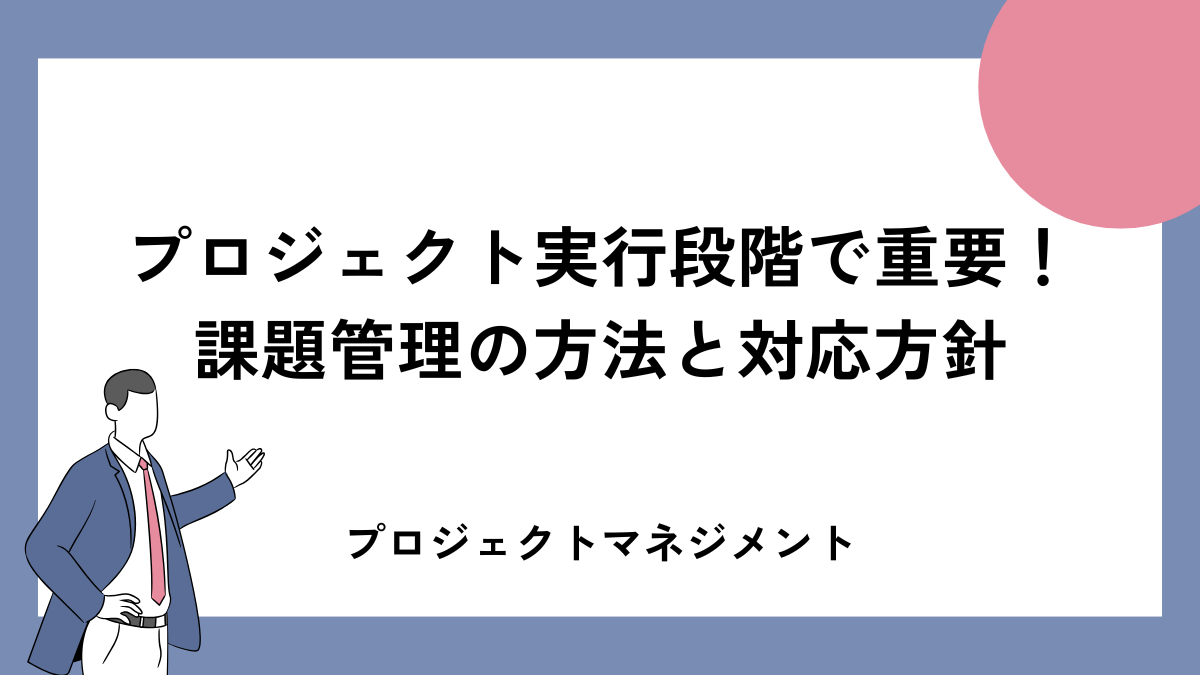
(2025/5/2 更新しました)
プロジェクトの実行段階では、課題管理は重要ですよね。
なぜなら、プロジェクトの納期・コスト・品質に 直接影響を与えるからです。
一方で、課題への対応方針を事前に決めておくことも必要です。
特に、コンセプトに影響がある場合には、プロジェクトの成否に関わってきますよね。
今回は「課題管理の方法とコンセプトに影響する課題に対する対応方針の考え方」について紹介します。
私は、25年以上プロジェクトリーダーを経験しています。
対応方針については、私の実例を紹介します。
課題管理の重要性と基本概念

課題管理とは?その定義と目的
課題管理とは、プロジェクトの進行中に発生する課題を特定し、改善に向けた具体的な対策を講じるプロセスを指します。
通常 課題は、プロジェクトの進捗や成功を阻む問題点として浮き上がってきます。
それを放置すると、進行が大幅に遅延したり、最終成果物の品質が低下したりするリスクにつながっていきます。
そのため、課題管理の目的は、問題を迅速に明確化し、影響を最小限に抑える対策を実施することにより、スムーズなプロジェクトの進行と目標の達成を確保することにあります。
課題管理によるチームの一体化
課題管理は、チームを一体化させるための強力な手段でもあります。
課題を共有し、解決に向けたプロセスをチーム全体で進めることで、メンバーの責任感が高まり、連携が強化されます。
プロジェクトには、必ず乗り越えなければならない壁があります。
チーム全体で乗り越えることによって、一体感はさらに強固なものになります。
また、課題管理を通じて各メンバーの役割分担が明確になるため、チームの効率性を大幅に向上させることもできます。
効果的な課題管理プロセスの流れ
課題の特定と記録
課題管理のプロセスにおいて最初のステップは、課題を適切に特定し記録することです。
具体的な方法としては、課題管理表を活用し、課題のタイトル、詳細、発生日、担当者を記録することが挙げられます。
これにより、課題が見落とされたり放置されるリスクを減らし、次のアクションを迅速に決定できます。
また、プロジェクト内での透明性が向上し、チーム全体で課題を共有することが可能になりますよね。
優先順位を決定する
すべての課題を同時に対応することはリソースが限られたプロジェクトでは難しいため、課題の優先順位を設定することが重要です。
緊急度と重要度を基準に、例えば「緊急かつ重要」「重要だが緊急ではない」などのマトリックスを作成する方法が一般的ですよね。
この分類を基に、対策の優先度を設定して進めることで、スケジュール遅延やリソースの無駄を防ぐことができます。
解決策の策定と実施:チームで動く方法
課題が特定され優先順位が決まったら、次に解決策を策定し実施するフェーズへ移ります。
このステップでは、課題の原因を分析し、具体的かつ実現可能な解決策を明文化することが大切です。
チーム全員が共有可能な形で文書化することがポイントですね。
また、解決策を実行する際には担当者を明確化し、定期的な進捗確認を行うことで、対応が確実に進むようにサポートすることが重要です。
プロジェクトリーダーの重要な役割のひとつですね。
課題対応の進捗管理
プロジェクトを正しい方向に導くには、課題対応の進捗を管理することが不可欠です。
進捗状況を「未着手」「進行中」「完了」といったステータスで簡潔に把握できる課題管理表を用いることで、状況を可視化・共有できます。
また、課題対応の状況を定期的にレビューし、課題の遅延や未解決が発生していないか確認する仕組みを設計することも必要です。
通常は、プロジェクトの進捗ミーティングの際に実施することになります。
課題の対応方針の明確化

事前に判断基準を決めておく必要性とは
プロジェクトは、期間・コスト・品質を守る必要があります。
でも、プロジェクトには必ず課題は発生します。
一番多いケースは、当初の検討範囲にモレが見つかった・想定外に仕様が膨らんだ などではないでしょうか。
先ず行うことは、期間・コスト・品質に「どの程度影響を与えるか」見積もることになります。
また、並行して「コンセプトに与える影響」も精査します。
そして、見積もり結果とコンセプトに与える影響を比較し対応を決めることになりますよね。
とはいっても、課題が発生するごとに このサイクルを回していては、課題は どんどん積み重なっていきます。
そのためには、事前に判断基準を設計しておく必要があるのです。
特に、コンセプトに影響がある場合の判断基準は、プロジェクトの成否に影響します。
以下に、私が活用していた判断基準について紹介します。
通常の課題が発生したケースの判断基準
コアコンセプトに影響を与える場合
コアコンセプトは、プロジェクトの最も基幹になるコンセプトです。
プロジェクトの本来の目的と言っても 過言ではありません。
この場合には、発生した課題の解決を優先します。
プロジェクトの期間・コストは 犠牲にします。
品質は、コアコンセプトに直結するものであれば 確保します。
そして、課題解決に取り組みます。
並行して、ステークホルダーと 期間・コストの調整をしていきます。
コアコンセプトは、絶対に貫きます。
これが崩れたら、なんのためのプロジェクトなのか 意味がわからなくなります。
私自身は、コアコンセプトまで影響したケースは 経験していません。
でも、もし遭遇していたら 中止にしたと思います。
個々のコンセプトに影響を与える場合
個々のコンセプトへの影響度によって、妥協点を探します。
問題への対策と期間・コスト・品質との妥協点です。
そして、妥協点調整を進めます。
個々のコンセプトの場合、優先順位があります。
優先順位の低いコンセプトであれば、切ることも考えます。
また、コンセプトの範囲内で実施することの内容調整をします。
コンセプトに影響が小さいものを 落とすことも考えます。
いわゆる実施事項の入れ替えですね。
この際の注意点が一つ。
プロジェクトリーダーだけで決めるのは 避けましょう。
必ず、メンバーと話し合うことです。
説得ではなく、納得を得ましょう。
利害調整が発生したケースの判断基準
人が絡む課題のケースです。
プロジェクトのメンバーは、組織の各機能単位で選ばれることが多いと思います。
なので、各メンバーの上司も絡んできます。
コアコンセプトに影響を与える場合
絶対に、譲りません。
プロジェクトを止めてでも、絶対に守ります。
プロジェクトリーダーは、語ってなんぼ です。
あらゆる手を駆使して、守ります。
そのためにも、普段から 積極的にコミュニケーションをしておくことです。
譲れない境界が浸透していれば、コアコンセプトに影響するケースは発生しないと思います。
事実、私は経験したことがないです。
個々のコンセプトに影響を与える場合
人との妥協点調整です。
コアコンセプトに影響しない範囲で 妥協点を見つけます。
そのためにも、常日頃のコミュニケーションは重要です。
コンセプトの意義について、何度も語っておくことです。
妥協できる位置が変わります。
環境の変化が起きたケースの判断基準
プロジェクトの構想段階に、一旦戻ります。
コアコンセプト・コンセプトを考えた際の根拠を見つめます。
そして、影響度を 精査します。
コアコンセプトに影響を与える場合
プロジェクトを 最初の段階に戻します。
コアコンセプトも変更します。
プロジェクト構想・計画も 最初から見直しです。
ただ、それまで行ってきたことは、全くムダにはならないケースが多いです。
期間・コストは、+αで 見積もることが可能です。
また、影響度によっては、中止という判断もあります。
コアコンセプトに影響を与えるほどの環境の変化、相当インパクトのあるものです。
逆に、環境の変化を取り込むプロジェクトに変更すべきです。
もう一度、変化の本質を見極め、新しいプロジェクトとして起こす。
変化を機会にできます。
個々のコンセプトに影響を与える場合
コンセプトを変更し、プロジェクトを継続します。
変更した部分は、やり直しになります。
当然、期間・コストは、見直しです。
環境の変化は、機会を増強するチャンスです。
脅威を機会にできるかもしれません。
メンバーを鼓舞して、モチベーションを維持・向上させましょう。
まとめ
今回は「課題管理の方法とコンセプトに影響する課題に対する対応方針の考え方」について紹介しました。
対応方針については、私の実例で紹介しています。
プロジェクトは、期間・コスト・品質を守る必要があります。
でも、プロジェクトには必ず課題は発生します。
課題管理をプロセスとして設計し実行すれば、スムーズなプロジェクトの進行と目標の達成が可能です。
また、事前に対応方針を決めておけば、最短のルートでプロジェクトを成功させることができます。
さて、今回はプロジェクトの実行段階である「課題管理」について紹介しましたが、それより重要なのは「コアコンセプトの策定」ですよね。
以下の記事では「コアコンセプトの策定方法」について記載していますので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。
投稿記事:プロジェクトの羅針盤!コアコンセプトの作成・決定方法