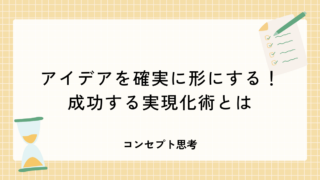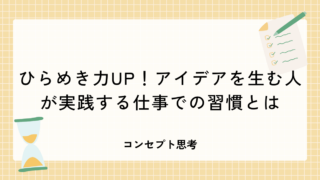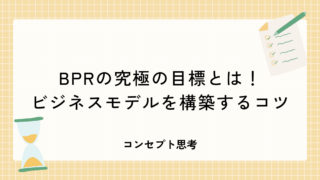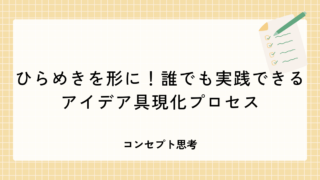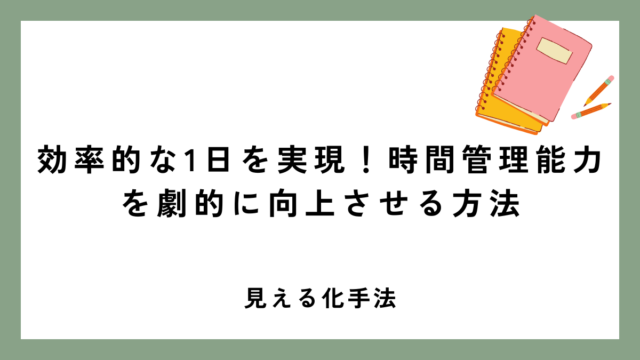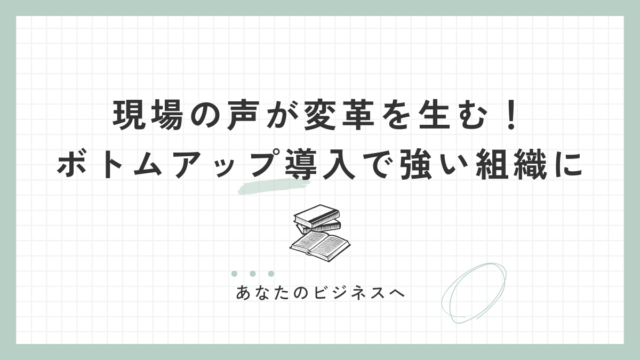アジャイルで抜本改革を!成功するための4つの方法
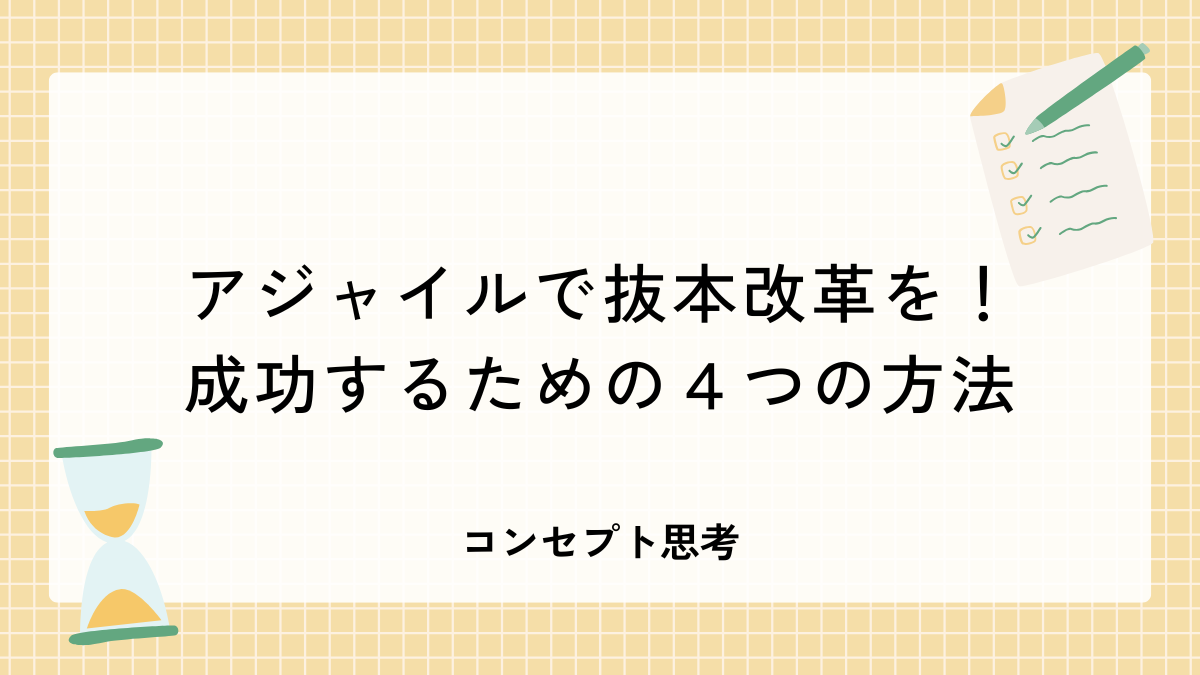
(2025/3/14 更新しました)
突き抜けた革新的なアイデアは、組織に抜本的な変革を起こします。
でも、アイデアだけでは 組織は動かないですよね。
この時 利用できるのが「アジャイル手法」です。
今回は「抜本的な改革を実現するためのアジャイル手法の進め方」について紹介します。
私自身が行ったDX(デジタルフォーメーション)の事例から 教訓として得たものになります。
アジャイルとは何か:その基本概念とビジネスへの適応

アジャイルの基本原則:従来型プロセスとの比較
アジャイルとは「迅速」や「機敏」を意味し、もともとはソフトウェア開発で利用される手法として広まった考え方です。
その基本原則には、変化への柔軟な対応、短期間での価値提供、継続的な改善が含まれます。
これに対し、従来型プロセスであるウォーターフォール型開発では、計画から設計、実装、リリースまでの各ステップを順番に行うアプローチが取られます。
このため、変更に対する適応力が低いため、一度決めた計画を進め続ける中で、環境やニーズが変化しても対応が難しくなることが多くあります。
一方、アジャイルは短い反復プロセスを特徴とし、段階的に進めながらフィードバックを得て修正を繰り返します。
この方法により、変動するビジネス環境に適応できるほか、価値の提供を迅速化できます。
そもそも日本には、改善文化が浸透していますよね。
そういう意味では、アジャイルは新しい概念ではないと考えられます。
変化への柔軟な対応、短期間での価値提供、継続的な改善は、改善文化そのものですよね。
抜本改革でも、適用するだけのことです。
アジャイルとイノベーションの関係性
アジャイルはイノベーションを促進する手段にもなります。
理由は、アジャイルが持つ反復的で改善志向のプロセスが 新しいアイデアや方法を生み出す土台を提供するためです。
従来型のプロセスでは、最初に大枠を決めてからそれを最後まで維持することが一般的でした。
この方法では、新たなビジネスチャンスや市場での変化に対する柔軟性が不足し、変革の余地が限られてしまいます。
また、技術の進化のスピードには 目を見張るものがあります。
一方、アジャイルでは、小さな単位でプロトタイプや仮説を検証し、それをもとに改良を加えながら前進することで、常に新しい発見や可能性が追求されます。
また、アジャイルのプロセスでは、チーム間や利害関係者との密接なコミュニケーションが推奨されるため、異なる視点やアイデアが融合しやすくなります。
このような環境下では、業務改革や新たな方法の導入がスムーズに実行でき、結果的にイノベーションの創出が加速します。
新しい技術との連携:DXやAIとの接続
アジャイルは、新しい技術との連携においても非常に有用な方法論です。
特にデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や人工知能(AI)の導入といった局面で、迅速な試行錯誤と柔軟な適応が求められる場面が増えています。
例えば、AIを活用した業務改革においては、短期間でプロトタイプを作成し、フィードバックを得て改良を重ねるアジャイルの手法が適しています。
また、DXの取り組みにおいても、アジャイル手法を活用して段階的に改善を進めることで、技術と業務プロセスの適合性を高めることができます。
このように、アジャイル手法はDXやAIとの接続を円滑にし、業務改革の成功率を向上させる手段として重要な役割を果たしています。
私自身の実例でも、アジャイル手法を活用してDXを実現しています。
アジャイル手法の進め方の4つの秘訣

ビジョンを明確にする
アジャイルにはデメリットも存在します。
たとえば、明確な計画がない場合には進捗が不透明となりやすく、全体像を把握しづらいため、プロジェクトがスコープの逸脱や方向性の不一致に陥る可能性があります。
そのためには、ビジョンですよね。
羅針盤となるビジョンを作成し、チームメンバー全員で共有する必要があります。
また、長期的な展望を示す計画と短期間で達成可能な目標を設定します。
これにより、チームメンバーでの一体感ができあがり モチベーションも高まります。
なお、長期計画は 現時点でビジョンを達成するためのストーリーで十分です。
短いサイクルで 成果を出す
アジャイルは、すばやく・機敏に、試行・検証するものです。
それでも、あえて挙げているのは 本当に大切なポイントだからです。
少なくても 半年に1回は、成果を出す必要があります。
抜本的改革には、抵抗勢力が必ずいます。
そして、意外と反対する人は 権限を持っていたりします。
長々と検討しているだけでは、まず潰されます。
この環境で 進めるには、はっきりと目にみえる成果が必要です。
プロセスに実際に落とし、こんなに変わるんだ という見せ方の工夫も必要です。
そして、成果は インパクトがなければいけません。
「えっ、こんなことできるんだ」という驚きが 必要です。
先ずは、最初の成果を何にするか考え 最短で実施することに全力を挙げるべきです。
そして、それ以降は 少なくても半年毎に 同じように成果を上げていくことです。
成果のレベルですが、ヒットを継続し 1年に1回は 大ヒットを出すことが必要です。
可能性を示しながら、次のステップへ一気にジャンプするのです。
そうすることで、徐々に風が吹いてきますし、流れも変わっていきます。
実際に 実運用に落とし込む
出来上がった成果は、実運用に落とし込む必要があります。
人は 実際にやってみることによって、効果がわかるものです。
組織のビジネスモデル・プロセスを変え、実際に廻して実績を作っていきます。
実績ができれば、人の考えは 徐々に変わって行きます。
積み重ねれば、やらざるを得ない状況にも なっていきます。
こういう状態を創り上げること。
これが最初のステップの目標となります。
共感を得る
実運用を廻した際に、共感を得ることを目指しましょう。
最初に試行する際には、実施する人を選んだ方が良いです。
選択する人は、抵抗勢力の人でも構いませんが、共感の影響力が大きい人を選ぶべきです。
影響力の大きい人の共感は、他の多くの人にも伝達されます。
要は、巻き込む人を増やすことができます。
実際に 私が実施した事例の時は、「画期的で、従来のやり方よりもダントツに早い」と共感してもらえました。
これにより、一気に 流れは変わっています。
また、共感してくれた人は、その後 助けてくれます。
こうなれば、更に拡がり 好循環になります。
まとめ
今回は「抜本的な改革を実現するためのアジャイル手法の進め方」について紹介しました。
変化が激しい現在、従来のように 全てが決まってから改革する方法では 変化を取り込むことはできません。
また、正解がわからない時代でもあります。
そのためには、アジャイル型での改革が 必要だと考えています。
特に、突き抜けた革新的なアイデアを実現するには、すばやく実施し成果を挙げることが必要だと考えています。