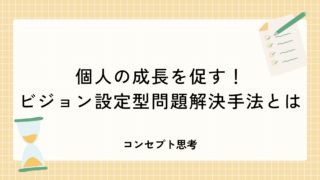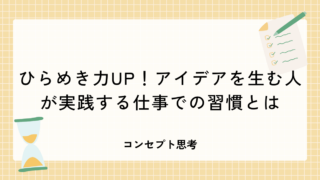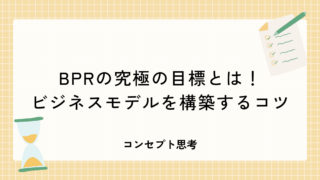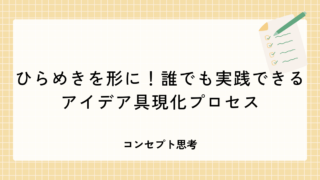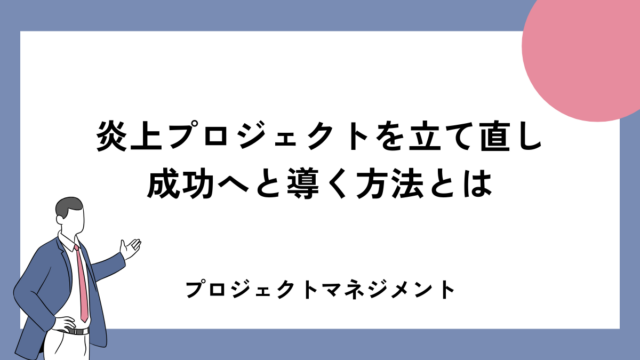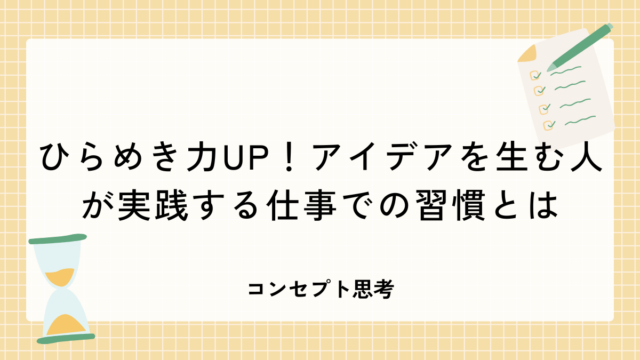失敗は成功の近道!学びの秘訣と成功へのステップ
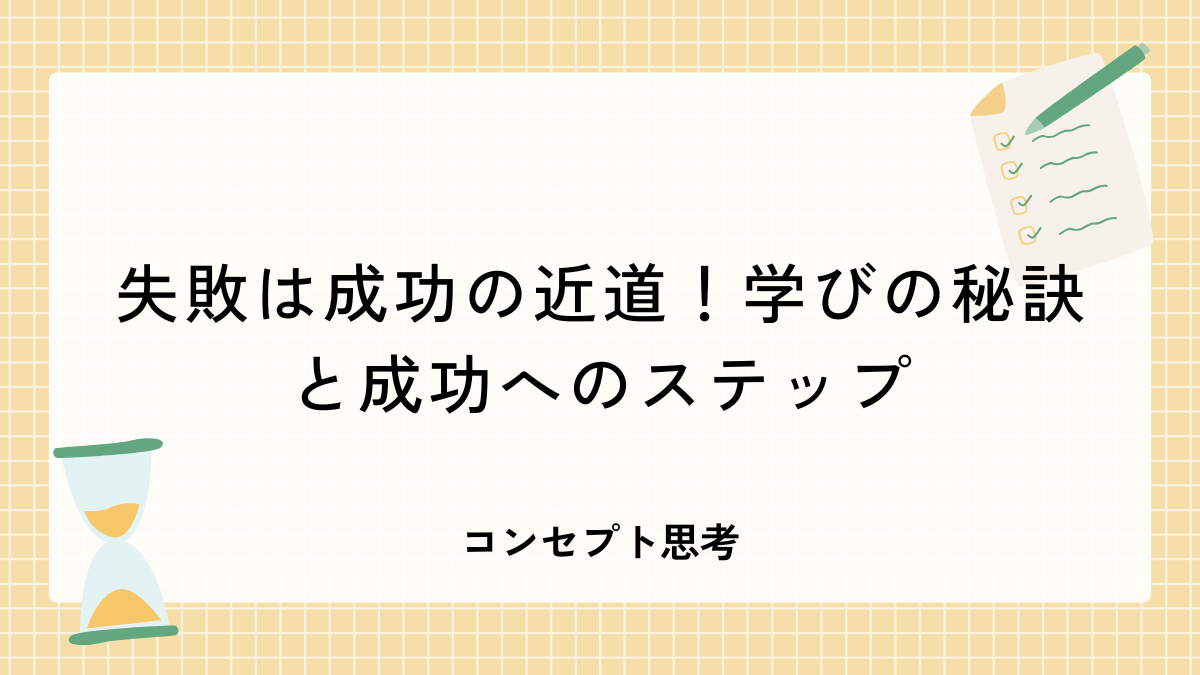
(2025/4/19 更新しました)
「失敗は恥」
「失敗は評価を下げる」
「失敗は避けるべきもの」
日本における失敗という言葉は、否定的な言葉につながりますよね。
でも「失敗は成功のもと」なんですよ。
逆に言えば「成功の背後には失敗が必ず存在する」のです。
そもそも仕事をやっていれば、失敗はつきものです。
ましてや、新しいことに挑戦すれば 失敗は常にあります。
失敗は、そこから学ぶことが重要なのです。
今回は「失敗から学ぶ方法と学びを組織に展開する方法」について紹介します。
実際にあった私の事例をもとに記載しています。
なぜ失敗は成功へのステップなのか?

失敗が持つ本質的な価値
失敗は、できれば避けたいものと考えますよね。
でも、失敗には本質的な価値が隠れています。
失敗することによって、自分の限界や問題点を確認する機会を得ることができます。
日々順調ならば、何の刺激もなければ振り返ることもないですよね。
失敗の経験は、成功へ導く大事なプロセスとして捉えるべきです。
具体的には、失敗を通して新しい視点を手に入れたり、再発防止によって次への行動の精度を高めることができます。
また、ビジネスでは目標に届かなかったり、やりたいことができなかったりすることがあります。
そのような状況に直面したときこそ、プロセスを振り返り学ぶことが重要です。
失敗から学ぶことで、自身の問題解決能力も向上します。
そして、長期的にみると自分自身の大きな成長につながるのです。
成功者が語る失敗の重要性
多くの成功者たちは、「成功の背後には失敗が必ず存在する」と語っています。
たとえば、ビジネス界のリーダーは、失敗を重要なプロセスとして捉え、それを繰り返し経験する中で成功をつかんでいます。
特に、アメリカでは「失敗は恥」という考えがないため、書籍でも普通に語られていますよね。
成功者の共通点は、失敗を単なる過ちとは捉えず、それを自己成長の機会として生かす姿勢です。
彼らは、失敗を徹底的に分析し、プロセスや結果を改善していく習慣を持っています。
このように、成功者にとって失敗はなくてはならない重要な学びであり、前向きに活用する姿勢が成功へ導くカギとなっています。
私自身の失敗事例
もう少し身近な事例として、私自身の失敗について紹介します。
私は、新しい製品モデル開発の業務を 生産技術部門としての立場での経験があります。
新しいモデルなので、必ずなんらかの新しい挑戦があり、知らないこともあります。
先ずは、相談しながら進めますよね。
それでも常に聞いていることもできないので、自身の判断で行う機会も出てきます。
例えば、図面検討。
常に一緒に検討できるほど、同僚の時間はないので最終的には一人での確認です。
当時は2D図面で、意匠面と裏面が一緒に描かれていたのです。
私が裏面だと思った線が 実は意匠面だったことがありました。
試作品が出来上がってきて見た時に愕然、とても量産できるものではありません。
その後は、関係部署にひたすら誤り なんとか設計変更をしてもらいました。
この失敗から学んだことは、いっぱいありますし、それ以外にも多くの失敗をしています。
そして、これらの失敗が「DXによるビジネスモデル変革」へつながっています。
失敗を学びに変えるプロセス
失敗を客観的に振り返る方法
失敗を学びに変えるためには、感情的になるのではなく、客観的に振り返ることが重要です。
失敗に直面すると、どうしても自分を責めたり、気持ちが落ち込んだりしますよね。
他者の責任を転嫁したくなる気持ちもあると思います。
これでは、次の行動を考えることはできないですよね。
冷静に客観的に、「何が起きたのか」を徹底的に振り返りましょう。
具体的には、失敗の事実をプロセス毎に時系列で書き出すと効果的です。
「どの時点で」「どのような状況の中で」「どういう根拠で判断した」結果が「どういう」失敗につながったのかを整理することで、失敗を客観視しやすくなります。
このように客観的に振り返ることで、失敗を「学びのプロセス」として捉えやすくなります。
原因分析と問題の特定
次のステップは、その原因を分析し、具体的な問題を特定することです。
適切な原因分析を行うことで、次に同じミスを繰り返さないための指針が得られます。
主な方法としては「なぜなぜを繰り返す」です。
「なぜ、その結果になったのか」を繰り返し問い続けることで、表面的な原因だけでなく根本的な問題に気づくことができます。
このプロセスを経ることで、失敗から学ぶ具体的な方法が見えてくるはずです。
行動プランを立てるステップ
最後に、失敗を成功へ導くための方法として欠かせないのが、具体的な行動プランを立てることです。
そして、失敗から得られた学びを次の挑戦に活かします。
まず初めに、「次回は具体的に何をどう変えるのか」を明確にします。
例えば、私の事例では「意匠線は赤色にして区別する」のが再発防止としては有効ですよね。
そして行動プランには、その場の再発防止だけではなく「もっと先の行動プラン」に落とし込むことも重要です。
以下に、その方法を紹介します。
学びを組織に展開する方法
再発防止から改善へつなぐ方法
上記した再発防止は、あくまでも自らの再発防止ですよね。
学んだことは 横展開しましょう。
失敗を業務改善として共有し、皆で再発防止をするのです。
業務標準があるのならば、確実に改善内容を織り込みます。
なければ、関係者を集めて 展開しましょう。
自分中心ではなく、皆で共有することが業務改善です。
そして、次から行動を変えることです。
改善から改革へつなぐ方法
小さな業務改善が積み上がっていくと、業務の重なりが起きてきます。
特に、失敗から改善した場合は 業務が増える傾向にありますよね。
例えば、部署単位で見た場合 2重・3重に同じことをしていたりすることもあります。
場合により、スキマ業務も発生しているのかもしれません。
一度棚卸しをする必要があります。
また、変化が激しいビジネス環境です。
変化に追従する必要もありますよね。
そもそも5年も同じ業務をしているとしたら、事業リスクは大きくなっています。
失敗から学び 業務改善が起こっている組織であれば、業務・事業改革をする素地が整っているはずです。
組織をスルーで見て、業務・事業改革を起こしましょう。
具体的には、プロジェクト化し 組織のメンバーを巻き込み実施します。
また、デジタル化は 必ず検討することです。
業務・事業をデジタルにシフトすれば、次のイノベーションにつなげることができます。
改革からイノベーションへつなぐ方法
ここまでは、失敗から「やり方を変える」について記載してきました。
最後は、失敗から「やることを変える」です。
例えば、図面検討についての私の事例を挙げました。
意匠面と裏面を間違えたという事例です。
最初から意匠面と裏面を現物のように見えることができたら どうでしょうか?
図面検討そのものが必要なくなりますよね。
そして、浮いた時間は 違うことをすれば良いのです。
実際に私の事例では、デジタル技術を使って「過去に自分自身が失敗したこと」全てを一瞬でわかるプロセスに変えてきました。
失敗の経験からイノベーションにつなげた事例です。
失敗には、イノベーションにつながるヒントが いっぱいあります。
改革の繰り返しによって、変化が普通になります。
変化が普通になれば、イノベーションのアイデアも出てくるものなのです。
失敗を恐れず行動するための心構え
失敗を受け入れるためのマインドセット
失敗を恐れず行動するためには、まず「失敗は成長の糧である」というマインドセットを身につけることが重要です。
失敗ってネガティブに捉えがちですが、それを「学びのチャンス」として位置づけることができれば、新たな挑戦への意欲を持ち続けることができますよね。
重要なのは、失敗を単なる結果として終わらせるのではなく、自分の判断や行動を見直すための「学びの宝庫」として活用することです。
日本の企業にいると「失敗すれば犯人探し」という文化に必ず直面しますが、その時点の立場より自分自身の成長の方が大切ですよね。
それに、その時点の立場なんて、すぐに逆転できます。
私は、こんなくだらないことに時間を費やすぐらいならば「犯人は私です」って手をあげていましたね。
自己肯定感を高める方法
自己肯定感を高めることは、失敗を恐れない挑戦の土台を作ります。
まずは自分がこれまで築いた成果や、努力のプロセスを振り返り、日々の行動を肯定的に捉える習慣を持つことです。
そもそも「できない人」なんて存在しません。
最初は、向き・不向きがあるだけです。
不向きなことでも、小さな成功の積み重ねで、やがては大きなことにも挑戦できるようになります。
例えば、目標を達成するたびに「よくやったな」と自分に語りかける時間を作ってみましょう。
また、失敗によって落ち込むのではなく、「自分には改善の余地がある」という建設的な考え方を持つことも大切です。
「今日は、こんなことを学べてラッキー」と言ってみましょう。
私がよくやっていた方法です。
まとめ
今回は「失敗から学ぶ方法と学びを組織に展開する方法」について紹介しました。
失敗は自己成長の大切な機会です。
失敗から学び、行動を変えましょう。
そして、学んだことを組織に展開しましょう。
改善があるから、変化に強くなり 改革につながる。
改革があるから、変化が普通になり 抜本的なイノベーションにつながります。
私自身が会社生活の中で 実感したことです。